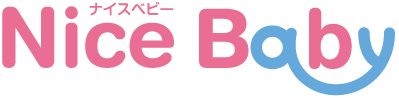ベビー用品
夏に快適なメッシュ抱っこ紐10選!選び方のポイントと暑さ対策体験談
陽射しが照り注ぐまるで夏のような日。 いつものように抱っこ紐で買い物に出かけた時、ふと真夏への不安が頭をよぎりませんか? 「今これだけ暑いのに、この抱っこ紐で真夏はどうなるの?」「真夏の抱っこ、暑さ対策はみんなどうしてるの?」 その抱っこ紐、暑すぎですよね?! 真夏日は外出を控えるのが賢明ではありますが、予防接種や家族の用事、ましてやワンオペのママや車を持たないご家庭では、赤ちゃんを抱っこして外出せざるを得ない状況も多々あることと思います。 では、抱っこ紐で夏場をのりきる方法にはどんな手段があるのでしょうか? まず、重要なのは抱っこ紐選び。既にお持ちの抱っこ紐が暑すぎると感じる方は、夏用を用意することをおすすめします。これから抱っこ紐の導入をされる方は、一年を通して快適に使えるものを選ぶなど、機能性に注目してみましょう。 ここでは、どんな機能の抱っこ紐だったら暑さをしのげるか、夏用抱っこ紐の選び方のポイントを解説、通気性に優れたおすすめ抱っこ紐をタイプ別に紹介していきます。また、夏を経験した先輩ママに聞いた、夏場の暑さ対策も合わせて紹介しますので、是非参考にして下さい。 夏の赤ちゃんとのお出かけが少しでも快適なるよう、この記事が役に立てたら嬉しく思います。是非最後までお付き合いくださいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 夏用抱っこ紐選びで知っておきたい3つのポイント 夏場の外出、日が高いうちに出かけるのは、赤ちゃんにもママにも負担が大きくなります。時間帯を調整できるのであれば、できるだけ涼しい時間帯を選ぶことも重要です。とはいっても、通院や上の子の都合などでどうしても赤ちゃんを連れていかなければならない時はありますよね。 そんな夏場の外出に使う抱っこ紐は、蒸れを防止する通気性のよいもの、吸汗・速乾性のある素材、着脱のしやすさなど機能性に注目して選ぶことが重要です。まずは、夏用の抱っこ紐選びのポイントを3つ観点から解説していきます。このポイントをしっかり押さえれば、夏場の抱っこはかなり快適になりますので、是非参考にしてくださいね。 1-1. 通気性の良いメッシュ素材で蒸れを防ぐ 夏用として、通気性の高い素材を選ぶと快適度もぐっとアップします。特に、汗っかきの赤ちゃんにとっても抱っこするママパパにとってもメッシュ素材ならベタつきを感じにくく、サラッとした清涼感を保つことができます。 夏場だけでなく、実は汗ばむことは一年を通して多々あります。暖房の効いた屋内で厚着をしているといつの間にか汗びっしょりになっていることも。通気性がよくムレにくい素材を使っているかどうかも、抱っこ紐選びの大事なポイントです。 1-2. 速乾性のある素材でいつも清潔を保つ 夏日のお出かけから帰ってきた時に、抱っこ紐が汗で湿っているときがあります。自分と赤ちゃんの汗、よだれやミルクの吐き戻しなど、見えない汚れも付いてきます。 そんな時、洗濯機で丸洗いできる抱っこ紐なら気軽に洗うこともできて安心。いつも清潔を保つことができます。また、速乾性にも注目!お手入れのしやすさも重要なポイントです。 1-3. 抱っこの着脱が楽なタイプ 装着が面倒というのは抱っこ紐を使用する上で多く聞かれる悩みです。ひとりでは脱着しづらかったり、時間がかかったりする抱っこ紐はそれだけでストレスになります。汗ばむ夏場に、着脱に時間がかかってしまうのはママにも赤ちゃんにも大きな負担になってしまうことも。 誰でも簡単に装着でき、体格差を想定したサイズ調整のしやすい抱っこ紐を選ぶ、また、思い切ってママ用とパパ用を用意するなど、使い勝手のよいもの、ご家庭に合ったよい方法を選びましょう。 2. 【タイプ別】使い勝手のいい夏用抱っこ紐厳選10選! 筆者おすすめの夏に浸かってほしい抱っこ紐を、キャリータイプとスリングなどのタイプ別に紹介します。各商品の特長も解説していきますので、商品選びの参考にしてくださいね。 2-1. 夏もメッシュ素材で快適!万能キャリータイプ ベビーキャリアMINI Air【ベビービョルン】 ベビーキャリーミニ 81tDPcPgE5L._AC_SL1500_ 81cj4gJ1oxL._AC_SL1500_...
三輪ベビーカーは驚くほどスムーズに走る!絶対に見てほしい検証動画
三輪ベビーカーは、四輪ベビーカーと比べてスタイリッシュなデザインが多く、見るたびに羨ましく思う人も多いかと思います。 三輪ベビーカーを押しているママやパパの姿を見かけると、赤ちゃんとの時間を優雅に過ごしている印象があって、子育て楽しそうだなぁと明るい気持ちになります。 数年前まではあまり見かけなかった三輪タイプのベビーカーですが、最近街中で見かける機会が増えたなと感じます。しかし、主流はまだまだ四輪ベビーカーです。 思わず目を引くベビーカーにも関わらず、なぜ三輪ベビーカーを使う人があまり多くないのでしょうか? 見た目から憧れを抱く三輪ベビーカーですが、「値段が高い」「重い」「デカい」というイメージが大きく、コンパクトで軽量な四輪ベビーカーが使いやすいとはじめから思い込んでしまう人が多いのです。そのため、ベビーカー購入検討の時点で三輪ベビーカーは早々に除外されてしまいます。 確かに、日本の住環境、生活環境を考えると場所によっては四輪ベビーカーが使いやすいと思います。 しかし、『軽いもの=使いやすい』というイメージは間違っていることをここで断言します。 軽量タイプの四輪ベビーカーは、タイヤが小型で構造も簡素化され、走行性能よりも軽量化を重視されているために、実は、それが「使いにくさにつながる」原因でもあります。 四輪ベビーカーを使用した経験のある方からは、 「道の段差が越えにくい、つまずく」 「タイヤが溝にハマりやすい」 「移動中の走行音がうるさい」 といった感想をよく聞きます。 筆者も初めての育児の時にA型四輪ベビーカーを使用していたので同じことを思いました。 『段差が越えにくい』というのも5~6㎝の段差ではなく、2~3㎝のほんのわずかな段差です。 「あーもう、なんでこんな段差で引っ掛かるの。」と思ったことは何度もあります。 一番困ったのはベビーカーで横断歩道を渡る時でした。 歩道に乗り上げる際、段差でつまずき「信号が赤になる!どうしよう!」とヒヤヒヤしました。せっかくの楽しい外出が、移動中の障害によって帰宅するころにはストレスいっぱいでぐったり。 軽量化が重視されているために不便を感じることもあるのが現実です。私はそう思いました。 対して、三輪ベビーカーは構造にもこだわった大型のゴムタイヤを採用し、走行性能が重視されています。 四輪ベビーカーでは引っ掛かってしまう2~3cmほどの段差も三輪ベビーカーなら軽々乗り越えることができますし、ガタガタ道でもスムーズにスイスイ進むことができます。 三輪ベビーカーの『重さ』にはちゃんと理由があるのです。 四輪ベビーカーの『軽量』という魅力が強い分、三輪ベビーカーの良さは見落とされてしまっているように感じます。 「値段が高い」「重い」「デカい」とマイナーイメージが強く、敬遠されがちな三輪ベビーカーですが、ここでは三輪ベビーカーの良さを最大限にアピールさせていただきます! 三輪ベビーカーは機能が充実しているのはもちろんですが、おしゃれで多種多様なモデルがあることも魅力の一つ。豊富なデザインからベビーカーを選ぶ楽しみも増え、ますます赤ちゃんとの外出が待ち遠しくなること間違いなしです。 皆様のベビーカー選びの参考になればと思います。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 三輪ベビーカーが段差や悪路に強い4つの理由 三輪ベビーカーの最大の魅力は、なんと言っても走行性・操作性が優れていることです。 四輪ベビーカーでは押しづらいこんなジャリ道やデコボコ道でもスイスイ進むことができます。...
ベッドメリーはいつからいつまで?生後すぐから使うべき理由と体験談
ベビーベッドを用意すると「ベッドメリーもほしいな」と思う方、多いと思います。ベッドと一緒にセットすると赤ちゃんを迎える気分もグッと上がってきますよね。また、ベビーベッドに寝ている赤ちゃんを楽しませてあげたい!とベッドメリーを用意する方も多いことと思います。 赤ちゃんがまだ自分で動くことのできない、ベッドで寝ている時間の長い新生児期に大活躍してくれるベッドメリー。赤ちゃんが生まれて初めて出会うおもちゃで、五感を刺激し発達を促す効果があるとも言われている知育玩具でもあります。出産祝いとしても人気が高く、昔から人々に愛され続けている安定のベビー用品ですね。 一般的にベッドメリーの使用開始時期は「誕生~つかまり立ち前まで」との説明書にかかれています。生まれてすぐの赤ちゃんにベッドメリーを見せても、一見反応していないように見えるかもしれません。しかし、ベッドメリーは、目で見るだけでなく、耳で聞く、触るなどの五感を刺激することができるため、新生児期の赤ちゃんにピッタリの知育玩具なのです。生後すぐからたくさん使ってあげることでその威力を存分に発揮することできます。 そこで今回は、ベッドメリーを生後すぐから使用することをおすすめする理由を4つの視点から分析。その効果や役割について詳しく解説していきます。また、実際に使った経験のある先輩パパママは、一体いつからいつまで使っていたか、赤ちゃんが見せてくれた反応についてアンケート調査を行いました。その結果と体験談も紹介していきますので、是非参考にしてください。 心も身体も急成長を遂げる生後数ヵ月間。赤ちゃんにとってより良い発達を促すことができ、忙しいママパパのかわりに赤ちゃんのお相手にもなってくれるベッドメリーを存分に活用くださいね。 1. 生後すぐからの使用がおすすめな4つの理由 ベッドメリーは五感をたくさん刺激してあげることができる、最適な知育おもちゃです。 生まれたばかりの赤ちゃんは、一見何もできないように見えますが、実は弱いながらも五感(味覚・嗅覚・聴覚・視覚・触覚)が備わっています。この時期の赤ちゃんには、やわらかくて心地よい刺激をたくさん同時に与えてあげることで、心身の成長、脳の発達を促すことがわかってきました。 では、ベッドメリーは新生児期の赤ちゃんにとって、どのようなことに良いとされているのかおすすめの4つの理由について解説していきます。 1-1. 赤ちゃんの視覚の発達に役立つ 赤ちゃんの視覚は、生後間もない時期はぼんやりと見える程度と言われています。見ることを続けるうちに、徐々に見えるようになり、顏の認識ができ、表情まで判別できるようになっていきます。生後2ヵ月ごろからピントを合わせて見たり、動くものを追視したりする目の動きが発達してきます。これにより、左右の目を同時に使う機能が働き、遠近感や立体感がわかるようになります。特に、色の濃いものに反応し始めるため、マスコットやモチーフは、はっきりとした色のものがより良いとされています。 以下の表のように、生まれてから生後6ヵ月ぐらいまでに急激に発達していることが分かります。将来、大人になってから文字を書くことや絵を描くことに繋がる能力です。この大切な時期に発達を促すためにも、ベッドメリーは有効なアイテムと言えます。 参考:公益社団法人 日本視能訓練士協会 1-2. 寝かしつけや泣き止ませ効果がある 赤ちゃんはママのおなかの中にいた時から、すでに聴覚は完成しているので、生まれた時から聴くことができます。ゆっくりとしたオルゴール音を聞くと、気持ちを穏やかにし落ち着かせてくれるだけでなく、静かに寝てくれることもあります。さらに、ぐずり出した赤ちゃんに音楽を聞かせると泣き止むことも。産院などでもオルゴール音楽を常に流していることもあり、赤ちゃんが安心するのかもしれませんね。 また、生後すぐから寝かしつけの際にオルゴール音楽を聴かせることで、「オルゴール音楽=寝る」という認識となり、寝かしつけに役立つという声もあります。早い時期からの利用ならではのメリットですね。 1-3. お世話する大人へのヒーリング効果が期待できる 新生児期は昼夜問わずお世話に忙しいママ。やらなければならないことが沢山あって、いつも時間に追われている感覚があると思います。はじめての赤ちゃんならなおさらですね。そんな慌ただしいお世話の中でも、ゆっくり回るメリーを眺めたり、優しいオルゴール音を聴いたり歌ったりすることで、いつの間にか心が穏やかになることがあります。 ベッドメリーを使うことで「ヒーリング効果があった」「ベッドメリーは自分の癒しのために使っていた」との声も多く聞かれました。 赤ちゃんのためのおもちゃが大人のヒーリンググッズになる。親子で癒されるなんて素敵なアイテムですね。 1-4. ねんね期赤ちゃんとの遊びのきっかけになる 生まれたばかりの赤ちゃんは、大人の声掛けにすぐ反応してくれるわけではありません。 「小さい赤ちゃんとの関わり方がよくわからない」「どうあやしていいかわからない」など、慣れない育児で悩みを持つママパパも多いようです。 そんな時、ベッドメリーが近くにあると、ねんね期の赤ちゃんとコミュニケーションをとる手段としてとても有効です。 例えば、メリーをゆらゆらさせて声掛けをしたり、音楽を流して口ずさんだり、会話にならなくても親と子を繋ぐツールとして活用することで、温かい関わり、親子の絆をつくることができます。 参考 「東京都教育委員会」「脳とここの発達メカニズム」 EVP「こどもの目の成長期は8歳まで」 赤ちゃんが聞いている音・ことば、そして音楽...
ベビーカーっていつまで使うの?先輩ママとパパの意見が解決になる!
これから出産準備で色々とベビー用品を揃えようと考えてるママやパパの中にはベビーカーを検討している方も多いと思います。 近所の公園や街中でママやパパたちがベビーカーを押している光景をよく見かけますが、それを見ると必然的にベビーカーは必須アイテムで準備しておかないと…って思いますよね。 自社のアンケートでは実に約9割の先輩ママパパが「ベビーカーは必要だった。」という回答結果が出ています。 アンケート結果からもベビーカーが必要であることは明確ですが、では実際のところベビーカーはいつまで使えるものなのでしょうか? 高価な買い物ですし、失敗は絶対に避けたいですよね。 具体的にベビーカーの使用期間が分かれば、そういった不安も解消できると思います。 今回は、子育て経験のある先輩ママパパ達にアンケート形式で話を聞いてみました。 「ベビーカーはいつまで使ったのか?」 「ベビーカーを卒業した理由(エピソード)とは?」 先輩ママパパ達のリアルな体験談をもとに、ベビーカー選びの参考にしてみてくださいね。 本題に入る前に、まずベビーカーの基礎知識を簡単に解説します。 現在市販されているベビーカーは、大きく分けてA型とB型の2タイプに分類されます。 「ベビーカーはいつまで使うか?」を知る上で重要な分類ですので、初めて聞いた人は覚えておきましょう。 タイプ A型 B型 月齢 1ヵ月(または4ヵ月)~最長48ヵ月 7ヵ月~最長48ヵ月 リクライニング 最も立てた状態で100°以上 最も倒した状態で150°以上 最も立てた状態で100°以上 リクライニング機能は無くても良い 特徴 両対面式のものが多い。 サイズが大きく、重さがある。 価格が高め。 軽くて持ち運びやすい。 価格が安め。...
あると便利!前向き抱っこ紐が必要な理由と使用上の注意点を徹底解説
赤ちゃんの顔が前を向くよう抱っこ紐を使用している方を見たことはありますか? 動物園や水族館、テーマパークなどでよく見かける前向き抱っこ。ニコニコ楽しそうに抱っこされている姿がなんとも愛らしいスタイルですよね。そんなご家族を見て前向き抱っこをしてみたい!と思う方も多いことと思います。 前向き抱っこは、多機能タイプの抱っこ紐に備わっていることが多い機能です。最近では、新生児期専用の抱っこ紐に、対面と前向き抱っこに対応しているタイプもあり、その需要の高さがうかがえます。 やってみたいな~と思いつつも、実際に必要な機能なのか、使う時は多いのか、など、もう少し前向き抱っこについて情報を得たいと思いますよね?実際、前向き抱っこもできる抱っこ紐は、多機能な分もちろん価格が上がるので、慎重に選びたいという気持ちはよくわかります。 そこで今回は、使用経験者の口コミを元に前向き抱っこができて良かったシチュエーションの紹介、使用する際に必ず知ってほしい注意点を解説します。また、ナイスベビーラボおすすめの前向き対応抱っこ紐8選も紹介していきます。 前向き抱っこは、正しく使うことでとっても便利で赤ちゃんとのお出かけがもっと楽しくなる機能です。是非最後まで読んでいただき、その魅力を知ってくださいね! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. あってよかった!前向き抱っこの3つの魅力 まずは、使用体験者のアンケートを元に、実際に使用したからわかるリアルな声から読み解く、前向き抱っこの魅力について解説します。では、早速みていきましょう! 1-1. 前向き抱っこ経験者の77%が「必要」と回答 「機嫌が悪いときに前向き抱っこでお散歩するとお花や車で気を紛らわすことができて、すぐにご機嫌になりました。この時期は特に寝グズリが酷かったので本当に助かりました。」(生後6ヵ月頃) 「お散歩中に休憩するときに前向き抱っこなら、抱っこしたままベンチに座れて、そのまま飲み物をあげられるので助かりました。こぼしてしまっても自分の洋服が汚れないのも良かったです!」(1歳頃) 「自分から主人や祖父母に抱っこしてもらう時に、前向きなら子供の向きを変えることなく抱きかかえられるのでスムーズなのが良かったです。」(生後8ヵ月頃) 「動物園では、対面抱っこやおんぶだと動物が見にくいと思い、前向き抱っこで使っていました。動物にも触れられて子供も大喜びでした♪」(1歳頃) 前向き抱っこ機能を備えた抱っこ紐を使用していた、先輩ママパパ150人に「前向き抱っこ」機能の必要性についてアンケート調査を行いました。 その結果は上図の通り、77%が「必要」と回答しました。 この結果から、前向き抱っこは経験者のほとんどが「あって良かった」と感じる便利な機能ということが分かりますね。 ここからは、なぜこれほど多くの方が必要性を感じたのか、前向き抱っこ機能の3つの魅力を紹介していきます。 1-2. ぐずり対策にも!赤ちゃんの機嫌が良くなる 今回のアンケートで必要と回答した方の理由として「機嫌が悪いときに助かった」という声が最も多くあがりました。 前向き抱っこは一気に視野が広がるため、周りのモノに意識が向きやすく、あっという間にご機嫌になることもあるようです。「お花かわいいね~」「お空が綺麗だね~」など声をかけることで気持ちが落ち着いてくることもありますので、前向き抱っこ紐を使用する際はぜひ試してみてくださいね! 1-3. 好奇心を刺激する!大人と同じ目線で景色を楽しめる 前向き抱っこができるようになるのは、首と腰がしっかりとすわる生後半年頃。色々なものに興味を示し始める時期ですね。 ママの顔を見ながら抱っこされていた対面とは大きく異なり、前向き抱っこでは赤ちゃんの目には様々なモノが飛び込んできます。視覚が刺激されることで、興味の幅が広がり、考える力や記憶力が良くなるとも言われています。 手を前に伸ばすこともできるので実際に触れてみたり、何よりママパパと同じ目線で景色を楽しむことができます。 特に動物園やテーマパークなどに行った時は、周りをしっかりと見せてあげることもできて大活躍間違いなしの機能です。 毎日見たことないモノ、知らないことに日々出会う赤ちゃんにとって、お出かけはたくさんの出会いが待っている絶好のチャンスです。前向きの抱っこ紐で色々な景色を見せて、好奇心や興味を刺激してあげてくださいね。 1-4. とくかく可愛い!写真撮影もお顔がしっかり写る 前向き抱っこはその抱っこされ姿がとにかく可愛い!抱っこ紐からお顔がヒョコっと出ている愛らしい姿に、思わず声をかけたくなる方も多いかも(笑) また、写真撮影も前向き抱っこならお顔がしっかり写るのでとっても便利。赤ちゃんの向いてる方にママの体の向きを変えてポーズして~~とか、面倒なことは必要なし!シャッターチャンスはたっぷり、決定的瞬間を逃さず押さえることが叶うのもうれしいポイントですね!...
インテリアに馴染む!おしゃれなベッドメリーとモビール厳選22選!
インテリアを彩るおしゃれなベッドメリーをお探しですか? ベッドメリーは、生まれて間もない赤ちゃんが、ゆらゆら動くメリーを目で追うようになったり、音に反応するようになったり、視覚や聴覚の発達を促す知育玩具。寝かしつけのお手伝いや遊び相手をしてくれる、赤ちゃんにとってはじめて出会うおもちゃです。 赤ちゃんのためのおもちゃなのですが、実は、大人も癒されるヒーリングアイテムであることが体験者の声からわかってきました。 毎日の忙しい育児中でも、くるくる回って優しい音を奏でるベッドメリーを見ていると、不思議とほんわか優しい気持ちになってくるもの。特にインテリア性の高いおしゃれなベッドメリーは、ベビールームを優しく彩り、見た目の可愛さでも家族みんなを幸せな気持ちにしてくれます。 ベッドベリーには、電池やネジ巻きでくるくる回るタイプと、空気の動きでやさしくゆれるモビールの2タイプがあります。どちらもおしゃれで可愛いデザインのものがたくさんあり、ベビールームづくりには取り入れたいアイテムですね。 そこで今回は、世界中のママパパから高評価を得ているベッドメリーをPICK UP!動的にまわるベッドメールとインテリア性重視のモビールにわけて厳選アイテムを紹介していきます。どれも自分自身で購入した際の満足度が高く、贈り物としても評価が高いものを選びました。また、インテリアの参考に、世界中のおしゃれなベビールームも集めてみましたので、後半で紹介していきます。是非最後まで読み進めてくださいね。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 癒し効果バツグン!おしゃれなベッドメリー10選! それでは早速おしゃれなベッドメリーをみていきましょう! まずは、動的に回るベッドメリーから紹介していきます。くるくる回りながら優しい音楽がながれる機能に、インテリアにも馴染むおしゃれなデザインと、三拍子そろったベッドメリーです。電動式タイプとネジ巻き式タイプがありますので、購入の際はよく確認してください。 ベットメリー TATO【nanan】 サイズ 44×49×40cm メロディ オルゴール「ブラームスの子守唄」 メーカー国 イタリア 回転 電動 価格 13,838円 おしゃれママのインスタグラムで話題!イタリアのブランドnana’nのベッドメリーです。人気ベッドメリーはのまあるいフォルムの可愛いクマのぬいぐるみと月や星の夜空をイメージしたモチーフがとってもキュート。ホワイトを基調としたシンプルで高品質なメリーは、ベッド周りをトータルコーディネイトしたいママにとくにおすすめです! やさしいオルゴールのメロディにあわせて、ゆっくり回るメリーが眠りへと誘ってくれます。オルゴールはネジをいっぱいに巻いて約3分半、ブラームスの子守唄のメロディが流れます。 > 詳細はこちら(amazon) ベッドメリー・フリースムートン オルゴール【トラセリア】...
おんぶで子育てしたい!おんぶ紐抱っこ紐おすすめ6選と選び方ポイント
そろそろ抱っこが重たくなってきた~>< 首もしっかりしてきたし、おんぶで家事効率を上げたい!抱っこよりおんぶがしてみたい! おんぶできることで子育てがグンと楽になるというのは、たくさんのママから聞く声です。 家事中におんぶすれば同時に寝かしつけもできてしまう、忙しいママには大助かりのスタイル。両手があくことで、とにかく色んなことができるようになり、重たくなってきた赤ちゃんも背負うことで、ママが感じる重たさもググっと軽減されます。 リュックを前にするより背中に背負う方がラクであることと同じように、おんぶはどの抱き方よりもカラダへの負担を軽減できるので、多くのママが「おんぶ派」になるのも納得ができます。 おんぶには、専用のおんぶ紐と、多機能型の抱っことおんぶ兼用タイプの2種類のキャリーがあります。 ・既に抱っこ紐はあるけどおんぶできるものがほしい ・抱っこ紐の購入を検討している ・おんぶ専用のおんぶ紐がほしい など、状況は様々かと思いますが、ここでは『おんぶ機能』に注目したおすすめの商品を紹介していきたいと思います。 「おんぶはいつから?」「おんぶできる抱っこ紐はどんなものがあるの?」「商品選びでどんなところを注意すればいいの?」などおんぶに対する不安や疑問を解消しながら、ご自身の環境にマッチするおんぶ紐抱っこ紐選びができるよう、順を追って解説していきます。 おんぶで子育てをもっとラクにしちゃいましょう! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. おんぶは首が完全にすわってから【生後4ヶ月頃~】 おんぶは一般的に、赤ちゃんの首がしっかりとすわった生後4ヶ月頃からの使用が推奨されています。 「両手が自由になる」「動きやすい」「カラダへの負担が少ない」といったメリットが多いので、できるだけ早い時期からおんぶを実現したいところですが、ちょっと待ってください!首すわり前のおんぶは、赤ちゃんの首へ大きな負担がかかり、思わぬ事故に繋がるリスクも高くとても危険。まずは赤ちゃんの首がしっかりとすわるまで時期を待ちましょう。 最も大切なことは「安心して使用できること」。 メーカーによっては、生後6ヵ月頃からとされている場合もあるため、必ず取扱説明書を確認して使用ルールを守りましょう! 2. おんぶができるキャリーは2タイプ おんぶには、「おんぶ専用タイプ」と「おんぶ・抱っこ兼用タイプ」の2種類があります。 購入時期や使用用途によって、使いやすさが大きく変わります。納得のいく商品選びをするためには、それぞれの特長をしっかりと把握した上で選ぶことが重要です。 ここからは、それぞれの特長やどういったシチュエーションに向いているのか、メリットデメリット含めて詳しくご紹介します。ぜひ、さいごまで読み進めてくださいね! 2-1. おんぶ専用タイプの「おんぶ紐」 「おんぶ紐」という言葉をご存じでしょうか? 今ではあまり馴染みのない言葉かもしれませんね。昔のママたちはおんぶ紐でおんぶをしながら子育てに奮闘していました。 現在では、抱っこバリエーション機能が豊富な多機能型が主流のため、おんぶ専用タイプはあまり見かけません。ただし、おんぶのみに特化しているために、おんぶでのフィット感と使いやすさはバツグン!価格の安さも魅力です。 抱っこよりもおんぶの頻度が増えたご家庭やセカンド用としてお探しの方におすすめのタイプです! ★ こんなママにおすすめ ★...
ベッドメリーおすすめの5条件を完全にクリアした究極の1台はコレだ!
赤ちゃんがはじめて出会うおもちゃの代表的なものとして「ベッドメリー」があげられます。 カラフルで音の鳴るメリーは、視覚と聴覚を刺激し、見ること、聞くことの発達によい影響を与えてくれると言われています。赤ちゃんをあやすためだけではなく、知育玩具として生まれた時から是非触れさせてあげたいおもちゃでもあります。 その見た目の可愛さからもベビーベッドとセットで準備したい!と思うママパパも多いことと思います。人気キャラクターが勢ぞろいしたキュートなタイプ、モノトーンのオシャレなタイプ、形を変えて長く使える多機能タイプなど種類も様々あり、どんなベッドメリーがおすすめなのか気になりますよね! そこで、今回は、数あるベッドメリーの中から「この機能があれば間違いない!」という5つの条件を紹介。年間約800台のベッドメリーをお客様のもとへお届けしているナイスベビーで、人気ナンバー1、そして、この5つの条件を満たす一押しのベッドメリー「やわらかガラガラメリーデラックスプラス」の魅力を徹底解剖していきます。 その他にも、今人気の電動式ベッドメリー5つを厳選、さらに、実際にベッドメリーを使用した先輩ママたちの体験談、ナイスベビーの安心なレンタルについてもあわせて紹介します。 赤ちゃんにとって楽しい環境を、忙しいママパパに癒しの時間を、ベッドメリーと共に手に入れてくださいね。 お気に入りメリーとの出会いに、この記事がお役立ていただけたら最高です! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. おすすめのベッドメリー5つの条件! おすすめのベッドメリーとは、赤ちゃんの成長のサポートとママパパの癒しとしても機能する育児アイテムです。ベッドメリーは、抱っこ紐のように何個も購入するものではありませんよね!選び方を失敗しない為にも、まずここで紹介する5つの条件を確認していきましょう! 1-1. 自動で回転する!電動式が断然おすすめ ベッドメリーは、一般的に電動(電池式)かネジ巻式の2タイプあります。おすすめは断然電動式です。 ネジ巻の場合は、一般的に回転が数分間しか続かないため、都度巻きなおす手間がかかります。そのうち面倒で回さなくなってしまうことも考えられます。 その点、電動であれば10~15分程度、長いものは20分と連続使用が可能。ベビーベッドで赤ちゃんがおとなしく一人遊びをしてくれる時間、それがわずか15分であっても、ママの手が空く時間をつくれるのは魅力ですね。 1-2. しっかり固定できる!安定感のあるものがおすすめ ベッドメリーを購入する前に、使用しているベビーベッドに取り付けできるか必ず確認しましょう。 固定方法は、ネジで締めて固定するタイプやクリップではさんで固定するタイプが一般的です。木製の柵のあるベビーベッドには、しっかり取り付けられるように設計されているものがほとんどですが、布製の簡易ベビーベッドには取り付けできないことが多くあります。 不安定な状態での取り付けは、小さい赤ちゃんの顔におもちゃが倒れたり、覆いかぶさってしまうなど、思わぬ事故を引き起こすこともありますので、取り扱いには十分注意しましょう。 1-3. おもちゃは丸洗いOK!清潔を保てるものがおすすめ ベッドメリーには、ゆらゆら揺れて赤ちゃんをあやしてくれる可愛いおもちゃやマスコットがぶら下がっています。手を伸ばして掴んだり、口に入れてなめたりすることもありますので、丸洗いでき清潔を保てる素材のものがおすすめです。サッと取り外せてすぐ取り付けられるものなら、ママの手間もかからずお手入れも躊躇なくできますね! 1-4. メロディ&ランプ付き!お世話しやすい機能がおすすめ ベッドメリーは、赤ちゃんの為に用意される方が多いと思いますが、実は、お世話するママパパの為という意見が多くあるアイテムなんです。機能面で是非おすすめしたいのが、音楽が流せたり電灯が付くタイプ。 音に敏感な赤ちゃんは、機嫌や気分に合わせて音楽を流してあげればご機嫌に。夜中の授乳やおむつ替えは手元を照らしてくれる電灯があれば、とってもお世話しやすくなります。 1-5. 濃い色味がGOOD!視覚の発達を促すカラーがおすすめ 生まれてすぐの赤ちゃんは、30cm先がぼんやりと見える程度と言われています。色を認識して動いているものを目で追うことで、視覚の発達を促すと言わせています。特に赤や黒などの色の濃いはっきりした原色から見え始めますので、おしゃれ重視のモノトーン系よりは、カラフル系を選ぶことをおすすめします! 2. 5つの条件を満たすベッドメリーは「やわらかガラガラメリーデラックスプラス」 前章で解説した5つの条件をすべて満たし、最もおすすめしたいのが、ナイスベビーで一番人気!タカラトミーの「やわらかガラガラメリーデラックスプラス」です。電動式で多機能なベッドメリーのため、手動式のメリーに比べるとお値段は高めですが、十分に納得できる商品です。ではその特長を詳しく解説していきますね! 2-1. 視覚の発達を促す斜め回転する電動式 動くものを見ることで徐々に視力が発達してきます。斜めに回転してマスコットが不規則に動くことで興味をひきつけるように設計されているので、赤ちゃんの視覚運動をサポートします。電動式になっていて自動で回転するため手巻きの手動式と比べてまわし直す手間がなく便利。さらに自動的にOFFになるオートタイマー付きで、もし消し忘れてしまっても安心です。 2-2. ベビーベッドと床置きにも対応した安全設計...
エルゴのおんぶはこれで完璧!背負い方から降ろし方まで画像で一挙解説
エルゴベビーの抱っこ紐を持っていてこれからおんぶに挑戦しようと思っている方、エルゴの購入を検討している方でおんぶも視野に入れている方。エルゴでのおんぶは「いつからできるの?」「どうやって装着するの?」などの疑問をお持ちでしょうか。 対面抱っこから始まる抱っこ紐の使用も、赤ちゃんが大きくなるにつれて、おんぶの必要性を感じる方も多いことでしょう。首が完全に座ればおんぶへの切り替えはOK!家事の効率UP、体への負担軽減など、おんぶによって楽になることが沢山あります。おんぶできる日を待ちに待っていた方も多いことと思います。 エルゴ抱っこ紐でおんぶをする場合、どの抱っこ紐であっても、まずは対面抱っこからおんぶへ切り替える必要があります。赤ちゃんをクルッと背中側へ移動させるのですが、慣れるまではかなり難しい...という声は多く、はじめての方は特に不安に感じると思います。 また、おんぶスタイルは、ママパパ側から赤ちゃんの様子を見ることができないため、抱っこよりもより注意が必要。装着方法や使用方法をしっかりとマスターしなければなりません。 そこで今回は、エルゴ抱っこ紐でのおんぶの方法を画像付きで詳しく解説していきます。 「いつからできるの?」などのおんぶ事前知識や、先輩ママパパが危険を感じた「ヒヤッと体験」も紹介します。 こちらの記事を読み終えた時には、エルゴでのおんぶをしっかりとマスターすることができます。安心で安全な正しいおんぶを目指して、ぜひ、最後まで読み進めてくださいね! 1. 安全におんぶするために知っておくべき注意点 エルゴでのおんぶ方法を紹介する前に、まずは、事前に知っておいてほしい3つの注意点をお伝えします。安全面にも大きく影響する内容ですので、しっかりとチェックしていきましょう! 1-1. おんぶは首が完全にすわってから【生後6ヶ月頃~】 おんぶの絶対条件は「首が完全にすわってから」の使用。首が完全にすわっていない時期での使用は、思わぬ事故につながる可能性もあり危険!必ず首が完全にすわってから使用しましょう。 また、取扱説明書には「生後6ヶ月(体重7.8kg)から」と表記がありますが、これはあくまでも目安です。6ヶ月を過ぎていても体型によっては、抱っこ紐に埋もれてしまうケースもありますので、赤ちゃんの成長に応じて判断するようにしてください。 1-2. まずは大人ふたりで協力プレイ! おんぶスタイルに初めて挑戦する際は、まずは大人ふたりで協力して行うことをオススメします。 エルゴの抱っこ紐は、必ず対面抱っこの状態からおんぶへ切り替える流れとなります。一人で赤ちゃんを支えながら前から後ろへ移動させるのは、慣れるまで難しい動作です。初めての時は誰もが「えっ?このまま後ろにまわすの??怖っ!」と感じると思います。実際に筆者の私も、はじめてチャレンジした時はかなり手こずりました。人形を使っての練習とはいえ、冷や汗をかく場面もありました。 最初から一人でのチャレンジはかなりハードルが高いので、慣れるまでは、他の人に赤ちゃんを支えてもらいながら行うと安心です。おひとりでチャレンジする場合は、クッション性のあるソファやお布団の上で行うとよいでしょう。 1-3. 長い髪は結わきましょう 髪の長いママはおんぶする前に必ず結わくようにしましょう。 髪をおろした状態でおんぶすると、赤ちゃんのお顔に髪があたり、目や口に髪の毛が入ってしまう危険性があります。肩ストラップに髪が挟まったり、赤ちゃんが引っ張ったりすることもあります。 できるだけ高い位置にコンパクトにまとめるか、毛先が体の前面にくるような結わき方をするよう工夫しましょう。 2. おんぶの仕方【アダプト・オムニ360】 エルゴの抱っこ紐でおんぶする際は、対面抱っこの状態から赤ちゃんをクルっと背中側に移動させるため、慣れるまで少し手こずるかもしれません。 そこでここからは、初心者でも安心して使えるよう、1コマずつの画像と共におんぶの仕方を紹介していきます。 1-1. 抱っこ紐装着前に必ず行う基本準備 アダプトとオムニ360を装着する前に必ず準備しなければならないのが、抱っこ紐の大きさを赤ちゃんの「体型に合わせる」こと。 この工程を行わないと、どんなに装着の手順が合ってようとフィットせず、安全に使用することができません。しっかりと事前準備からはじめていきましょう! 2-1-1. 身長に合わせてシートアジャスタータブを調節する 自然なすわり姿勢とは赤ちゃんの足が「M字型」姿勢になるのが理想的。赤ちゃんの成長に合わせてアジャスターを調節することで、どの月齢でもM字型姿勢を保つことができます。 では、ウエストベルトの内側についている「シートアジャスタータブ」を赤ちゃんの身長に合わせて調節しましょう! 従来のエルゴ抱っこ紐は、新生児に使用する際にインサート(新生児クッション)で赤ちゃんを包み込んでから装着する必要がありました。しかし、シートアジャスタータブ機能の採用により、赤ちゃんの身長に合わせてアジャスター位置を変更することで、お尻の沈み込みが調整できるので、インサートがなくても新生児期の小さなカラダを守ることができるようになりました。また、股幅が調整できることで、自然なすわり姿勢のM字型姿勢を保つこともできます。...
お洒落で手軽なストッケのベビーチェア「クリック」の魅力を徹底解説
ノルウェー発のストッケは、お洒落ママたちから絶大な支持を得る人気のベビー用品ブランド。数あるベビーチェアの中で不動の地位に君臨するトリップトラップは、ベビーチェア選びの選択肢のひとつとして候補に挙げる方も多いのではないでしょうか。 ストッケといえばトリップトラップの印象が強く残りますが、他にも「ステップス」や「クリック」といった別ラインのハイチェアもあります。トリップトラップの情報は既に耳にしている方も多いと思いますので、今回はこの中の「クリック」に注目していきたいと思います。 トリップトラップとステップは対象月齢や価格など、ほぼ同じラインのアイテムですが、「クリック」においては全くの別ラインで登場しています。ストッケのハイチェアの中では言わば異色のラインです。 何が異色なのか、一言でいえば、全てにおいて「お手軽」ということ。 世界中のママたちのベビーチェアに対する声から生まれたのが「クリック」というだけあって、その手軽さは使い勝手や価格、全ての面において実現されているのです。 お手軽であってもストッケ品質が約束されているなんて、魅力的すぎませんか?! そんなクリックの魅力を隅から隅までしっかりと解説していきます。組み立て方法や便利なオプション品の紹介、実際に使った先輩ママの口コミも公開していきますので、是非最後までお付き合いください。 読み終えた時には、思わずクリックの購入ボタンをクリックしたくなるかもしれませんよ(笑) 1. ココがすごい!ストッケ「クリック」 7つの魅力 では、ここからクリックの魅力について解説していきます。 ストッケだけに、そのデザイン性は見ての通りお洒落さに関しての話はするまでもありません。ここでは、機能性を中心に7つのポイントにわけて、その魅力を一つずつお伝えしていきますね。 それでは早速みていきましょう! 1-1. 世界中のママの声から生まれた究極のハイチェア 「先輩ママたちは、ベビーの離乳食用ハイチェアについて色々なことに悩んできました。部屋の雰囲気を損ないたくない、あれこれ揃えるのが面倒、汚れるから掃除が大変・・・。「ストッケ クリック」は、子ども用ハイチェアに関する世界中の消費者の声から生まれました。」 離乳食が始まる頃にベビーチェアの購入を検討する方が多いと思います。デザイン性、機能性、利便性、収納の問題などなど、選び始めると決定打がみつからず迷走しがちだったりします。やっと決めて購入したものの、いざ使ってみたら、ここが使いにくい、あれが足りない、手づかみ食べでチェアもクッションも汚れるしお手入れも大変、と悩みは尽きないものです。 そんな先輩ママたちの苦い経験から、クリックはその悩みをクリアする構造を実現しています。 ベビーチェア選びに悩んだ時はクリックを選べば間違いなし!と言えるほど、ママたちの思いが詰まったパーフェクトなチェアなのです。 1-2. 予算も手間も追加不要のオールインワンパッケージ クリックの大きな特徴のひとつが「オールインワンパッケージ」。 チェア本体のみではなくトレイとハーネスもセットになり、全て一箱にまとめてお届けします。 トリップトラップやステップスはチェア本体は単体商品、トレイやベビーセットなどはオプション品として必要に応じて購入します。離乳食期での使用の場合、まだ体の小さな赤ちゃんにはチェア単体ではサイズが合わず座ることは難しいため、ベビーセットとクッションの購入は必須となるでしょう。手づかみ食べが始まればテーブルの必要性にも迫られます。チェア本体のみ購入してその後のあれこれ必要になり何度も買い足した結果、大きく予算オーバーしてしまうのが現実です。 「だったらオプション品は買わなくていいんじゃない?」と思う方もいるかもしれません。 それは大間違い!絶対に必要です。ないと座れません。 筆者の私もトリップトラップ愛用者の一人なので、そこにおいては経験済み。 お譲りでいただいたトリップトラップとベビーセットに、離乳食期の頃に座らせたところ、大きすぎてとても使える状態ではありませんでした。当時はまだベビー用のクッションもなかったので、これを使えるのはまだまだ先との判断で、安価でコンパクトなトレイ付きチェアを購入しましたが、それでもまだ大きくてクッションを追加購入することになった経験があります。 その点、クリックはオールインワンパッケージなので、買い足しの必要がほぼありません。チェア本体がコンパクトな構造のため、離乳食期のお子さまでも座ることができますが、大きいと感じた時は専用クッションを買い足すのみ。トレイとハーネスもセットなので、活発に動くようになってからも安心して使うことができます。 ベビーチェア購入の課題「買い足し」問題をクリアした、予算も手間もかからない安心のパッケージなのです。...
危険!ベビーカー転倒事故増加の理由とは?荷物かけフックの落とし穴
子どもと外出する時に便利な育児グッズとして代表的なのが「ベビーカー」ですよね。 最近このベビーカーによる転倒事故が増えていることをご存じでしょうか。 実はこのベビーカーの転倒事故の一番の原因は『ベビーカーのハンドルに荷物をかける』という行為によって起きているのです! 外出時にベビーカーをよく使う人にとっては他人ごとではないはずです。 子どもとのお出かけには紙おむつにおしり拭き、ミルクなど何かと荷物が必要です。 買い物帰りにはさらに荷物が増えてしまいますよね。 ついつい予定外の買い物をして手に持ちきれなくなってしまったとき、みなさんはどうしていますか? ベビーカー座席下に付いている収納かごは、おむつや着替え、抱っこ紐など子供の荷物でパンパン。他の物を入れる隙間なんてありません。 そうなると、「ベビーカーのハンドルにちょっとかけるくらいだったら大丈夫。」なんて思ってしまいますよね。 外出先で、ベビーカーのハンドルにフックをつけて荷物をかけている人…結構見かけます。 実は、筆者もベビーカー用フック愛用者の一人でした。 2019年12月に国民生活センターより『ベビーカーの転倒による乳幼児の事故に注意』という注意喚起が発表されました。 その調査によると約3割の赤ちゃんがベビーカーに乗っているときに転倒・転落を経験していたことが判明したのです。しかも、頭や顔をケガした赤ちゃんが9割もいるという結果に! ベビーカーによる転倒事故が増えているという衝撃的な事実を知りハッとしました。 私も何度か、ベビーカーでの移動中にヒヤッとしたことがありますが、大した事故にもならずにいたので「大丈夫だろう。」と過信していました。 国民生活センターの報告内容を見て、一歩間違えれば大きな事故になっていたかと思うとゾッとしました。 「このままではダメだな、危ないな、ちゃんと見直さなければいけないな。」と改めて感じました。 ベビーカーは使い方さえしっかり守っていれば安全な乗り物です。 しかし、使い方を間違えれば大きな事故につながる危険な乗り物にもなります。 この記事では、2019年12月に国民生活センターが発表した研究データを元に、 ベビーカー転倒事故が増えている理由 どんな事故に繋がってしまうのか? どんなことに気を付けなければいけないのか? 万が一転倒してしまったら? ベビーカーで快適に外出するためのポイント をまとめています。 これを機に一緒に、ベビーカーの使い方を見直してみませんか? 1. ベビーカーが転倒する最大の原因はハンドルにかけた荷物だった! 医療機関ネットワーク事業(消費者等と国民生活センターとの共同事業)には、2014年4月以降ベビーカーごとの転倒あるいは乳児が転倒して怪我をした事例が288件も寄せられています。 ※2014年4月~2019年10月末日までの伝送分...
初心者でも安心!エルゴ抱っこ紐の付け方を種類別に徹底解説【画像付】
ママたちからの絶大な支持を集め、今や抱っこ紐採用率No.1とも言える、不動の地位に君臨するエルゴベビー。一度は使用してみたいママ憧れのベビー用品のひとつです。 オシャレママたちの心をくすぐる豊富なカラーバリエーションや、パパにもぴったりフィットする汎用性の高い設計、そして、エルゴがここまで支持される大きな理由として「機能性が高い、肩や腰が疲れにくい」ことが挙げられます。 赤ちゃんが成長するにつれ、その機能性は発揮され、重たくなった赤ちゃんを長時間抱っこしても疲れにくく、肩や腰への負担を軽減してくれます。また、抱き方のバリエーションも豊富で、生活シーンに合わせた使用方法を選ぶことができます。 エルゴ抱っこ紐の高性能を十二分に生かすために重要なのが、正しく装着すること。一歩付け方を間違えると逆にカラダに負担がかかってしまい、腰痛が悪化した、なんてことにもなり得ます。せっかくの機能が生かされず、ただただ使いにくい抱っこ紐になってしまうということだけは避けたいものです。 実際、ナイスベビーにも「肩や腰が痛くなる」といったお問合せをいただくこともあります。装着方法を確認すると間違った装着をしている場合が多く、まずは、正しい装着方法を実践していただけるようご案内しています。正しく装着したところ使用感がグーンとアップした、腰痛が改善されたという声を聞くほど、正しく装着するということは安全に快適に抱っこ紐を使用する上で重要なポイントとなります。 大前提として大切なのは「専用の説明書をしっかりと読むこと」。感覚で装着するのはご法度です! とはいえ、説明書を読んでも合っているか不安に感じたり、説明書の解読が苦手だったり、お譲りで説明書が付属していなかった方もいるかと思います。 そんなみなさんに向けて今回は、誰でも安全に装着できるよう、エルゴの付け方を細かく解説していきたいと思います。装着時に間違えやすいポイント、ちょっとしたコツ、知っておくと役立つ情報なども紹介していきます。解説と合わせてエルゴベビー公式装着方法の動画も掲載しますので、是非参考にしてください。 では早速、付け方を見ていきましょう!と言いたいところではありますが、まず最初に「本体に破損がないか」を確認してください。 これは新品で購入した方も、お譲りしてもらった方も必ず行ってください。少しでも破損を発見した場合は、直ちに使用を中止して販売店やエルゴベビーに問い合わせましょう。 確認ができことを前提に、ここから一緒に抱っこ紐の付け方をマスターしていきましょう! こちらの記事をお読み頂ければ、正しい抱っこ紐の付け方を知ることができて、安心してお子様とのお出かけを楽しむことができます。最後までお付き合いくださいね! 1. アダプト・オムニ360の付け方 最初に、エルゴ抱っこ紐のスタンダードタイプ「アダプトとオムニ360」の付け方を解説していきます。どちらも付け方は同じ。まずは、装着前にすべき基本準備を整えてから実際に装着していきます。コツや注意点もともに紹介していますので、しっかりと確認していきましょう。 1-1. 抱っこ紐装着前に必ず行う基本準備 アダプトとオムニ360を装着する前に必ず準備しなければならないのが、抱っこ紐の大きさを赤ちゃんの「体型に合わせる」こと。 この工程を行わないと、どんなに装着の手順が合ってようとフィットせず、安全に使用することができません。しっかりと事前準備からはじめていきましょう! 1-1-1. 身長に合わせてシートアジャスタータブを調節する 自然なすわり姿勢とは赤ちゃんの足が「M字型」姿勢になるのが理想的。赤ちゃんの成長に合わせてアジャスターを調節することで、どの月齢でもM字型姿勢を保つことができます。 では、ウエストベルトの内側についている「シートアジャスタータブ」を赤ちゃんの身長に合わせて調節しましょう! 従来のエルゴ抱っこ紐は、新生児に使用する際にインサート(新生児クッション)で赤ちゃんを包み込んでから装着する必要がありました。しかし、シートアジャスタータブ機能の採用により、赤ちゃんの身長に合わせてアジャスター位置を変更することで、お尻の沈み込みが調整できるので、インサートがなくても新生児期の小さなカラダを守ることができるようになりました。また、股幅が調整できることで、自然なすわり姿勢のM字型姿勢を保つこともできます。 快適な使い心地を実現するために、成長に合わせてアジャスターをこまめに調整するよう心がけましょう。 左右のシートアジャスタータブは必ず同じカラーガイドに留める 画像のように左右のシートアジャスタータブを別カラーガイドに留めるのはNG!股関節脱臼や歪みの原因になりかねません。必ず左右同じカラーガイドに留めましょう。 1-1-2. フロントストラップ・シートアジャスターボタン(スライダー)の調整 シートアジャスターを調整した後は、本体シート前面にあるアジャスターでもシート幅を調整します。シート幅を調整することで、さらに赤ちゃんの体格にあったすわり姿勢を実現することができます。 本体シート前面についているボタン(スライダー)はアダプトとオムニ360によって表記や調節方法が異なります。どちらも前述のシートアジャスタータブと同じタイミングで変更すると良いでしょう。 抱っこ紐で赤ちゃんの「太もも~お尻」を支えられているかがポイントとなります。膝裏まで支えられる位置までシートを調整します。ヒザの位置が少し上に上がった「M字」の状態が理想の姿勢です。 アダプト(フロントストラップ) 左右3つのボタンで3段階のサイズ調整が可能。赤ちゃんの太ももから膝裏までを支えるサイズになるよう、ボタン位置を調整します。サイズ調整をしたら、フロントストラップをループに通してから固定します。...