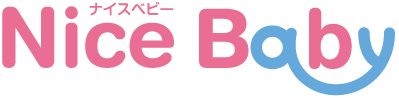出産準備・子育て
出産準備リスト|必須の品を3日でそろえるための決定版
「出産で準備するもの、たくさんあって大変!」 「多すぎて、どれから選べばいいのかわからない……」 「本当に全部必要?」 初めての出産、期待と同時に不安も感じますよね。 特に、出産準備品については、情報がたくさんありすぎて「何から準備すればいいの?」と迷ってしまうのではないでしょうか。 実は、一般的に紹介されている出産準備品を、全て用意する必要はありません。 まずは最低限のものをそろえて、その上で、状況に応じて必要なものを追加していきましょう。 以下の【最低限そろえておくべきリスト】をそろえておけば大丈夫です。 参考:出産準備品は最低限で!子育てミニマリストが提案する出産準備リスト これだけでもそろえるのが大変そうに思われるかもしれませんが、ベビー用品店でまとめて購入したり、セット品を活用すれば3日程度で準備可能です。 なぜ必須のものから準備するかというと、闇雲にいろいろなものをそろえても、「ほとんど使わず後悔するアイテム」もあるからです。 【必須→あったら便利→あとから買える】と優先順位をつけて準備することで、無駄な出費や、あれこれと準備をする時間が減らせますよ。 本記事では、無駄なく効率的に出産準備を進められるよう、優先順位別に紹介しています。 1. 【必須!】最低限そろえておくべき出産準備リスト 2. 必要に応じて追加すると良い出産準備リスト 安心して赤ちゃんを迎えられるように、ぜひ準備をする際の参考にしてくださいね。 1. 【必須!】最低限そろえておくべき出産準備リスト この章では、最低限そろえておくべき出産準備リストをご紹介します。 まずは、表の「準備する時期」を目安に、ここでお伝えしている商品をそろえておけば大丈夫です。 【最低限そろえておくべき出産準備リスト】 準備する時期 アイテム 個数目安 費用目安(1つあたり) どこで買える? 母子手帳を貰ってから 母子手帳ケース 1個 2,000円~...
「産後パパ育休」「育休」改正内容をどこよりもわかりやすく徹底解説
ここ数年で育休を取得するパパも増えてきましたね。 育休を取得するパパのための制度「産後パパ育休」 一体どのような制度なのか、詳しく知っていますか? 育児介護休業法には、育児休業の他に、パパの育児休業取得を促進するため、夫婦が協力して育児休業を取得できるように「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」といった特例が設けられています。 パパが当たり前のように育休を取れる環境づくり、さらに育休の充実をはかるため、2022年4月から育児介護休業法の改正が行われています。 2022年10月の「産後パパ育休」の制定と「育児休業」の改正により、育児休業がより柔軟に取得できるようになりました。 今回は、2022年10月から適用の「産後パパ育休」と、改正された「育児休業」と「育児休業延長」について詳しく解説していきます。 後半には、継続される「パパ・ママ育休プラス」についても触れていきます。 取得には細かなルールがあり、複雑で覚えるのが面倒と思うかもしれませんが、せっかく持っている大切な権利です。しっかりと理解してどのように活用していくか、夫婦でしっかりと話しあっていきましょう。 1.「産後パパ育休」の内容をわかりやすく解説 2022年4月の育児介護休業法の改正で、事業主に対して労働者への育休取得の意向確認が義務付けられました。 「育休を取得するのかしないのか」は確認されますが、育休取得に絡む要件について、こと細かに説明してくれる会社は少ないかもしれません。 基本的に、育休や産休に絡む情報は、自らが進んで情報収集をしないと得られないと考えた方がいいと思います。 2022年10月からは「パパ休暇」は廃止され、新たに「産後パパ育休」が適用となります。 まずは「産後パパ育休」とは、一体どんな制度なのかを解説していきますので、一緒に確認していきましょう。 \2022年9月までの「パパ休暇」について詳しくはこちらの記事で!/ 便利そうで便利じゃない?!パパ休暇・パパママ育休プラスを徹底解説 「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」一体どのような制度なのか、詳しく知っていますか?女性の育児休業取得が定着してまだ10年ちょっと、といったところでしょうか。育休は女性のためだけではなく、子育てをす... ナイスベビーラボ 2024.06.09 1-1. 「産後パパ育休」と「育児休業」は別の休業制度 「産後パパ育休」は、正式には『出生時育児休業』といいます。通称が「産後パパ育休」です。 名前が違っても同じ休業のことを指しています。 基本的な考え方として、出生時育児休業という名の通り、子どもが生まれたときに取得する育児休業です。 子供が1歳になるまでに取得できる、いわゆる従来の「育児休業」とは別の休業です。 まずはこのことを理解した上で、以下の章を読み進めてください。 育児休業取得条件に満たなければ産後パパ育休もNG 基本的に産後パパ育休も育児休業なので、下記のような育休取得条件に該当しない場合は産後パパ育休の取得もできません。 入社1年未満の場合 育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明確である場合...
両親の愛情たっぷり「出産記念」を作ろう!厳選アイテム紹介と体験談
「出産記念」に何を残してあげようかお悩みでしょうか? 出産記念と言えば、へその緒を木箱に入れて残したり、胎毛を筆に仕立てて大切にすることなど昔から伝わる風習があります。 欧米では、ファーストシューズや銀のスプーン、ベビーリングなどが昔からの伝統として残っており、日本の家庭においても出産記念に残すアイテムとして認知されるようになってきています。 文化は違えども、成長祈願の意味をもつ言い伝えは同じ。「出産の記念になるものを残したい」というのは世界共通の思いのようですね。 筆者の私が、娘たちの出産記念に残したものの中で、一番思い入れがあったのは、手作りのフォトアルバムです。出産当時の想いが湧き上がってくるようで、見返すたびに涙腺崩壊する記念品となっています(笑) 出産記念品は、家族の愛情が伝わるエピソードを添えて残してあげましょう! ここでは、出産記念についてナイスベビーの社内アンケートを行い、どんなものが実際に記念になっているのか、どんなエピソードがあるかを調査しました。さらに、出産記念に人気のメモリアルアイテムについてご紹介します。赤ちゃん誕生の素敵な思い出になる記念品を見つけてくださいね! では、早速見ていきましょう! 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 誕生の奇跡を「出産記念」として残す!先輩ママパパ体験談 子育て経験のあるナイスベビースタッフに、「出産記念」について50人にアンケート調査を行いました。回答したスタッフは20代から50代と幅広い年齢層となっています。 1-1. 「出産記念」に残したものはありますか? 結果は、ご覧の通り、回答者の全員が「はい」と答えました。 出産は、ママにとってもパパにとっても、一生に何度かの貴重な経験と節目です。赤ちゃんが大きくなってから、自分の生まれたころのことを家族みんなで懐かしむことこそ、「出産記念」に残す意味があるのかもしれませんね。 1-2. 「出産記念」に残したものとエピソードを教えてください。 「名前や誕生日は入っていませんが、ロイヤルコペンハーゲンのイヤープレート。出産のその日に夫が後輩の結婚式の引き出物に貰ってきたので記念になっています。2人目のときは自分で買いました。」 「手形足形は紙粘土で型取りして石膏を流し込むタイプのもので作りました。子供が動くので苦戦しましたが、作る工程も思い出になって良かったです。」 「子供たちの写真やへその緒は自宅の片隅にしまってありますが、大掃除や部屋の片づけをしている中で写真を見たりへその緒の桐箱を目にすることがあります。へその緒を見ると「頑張って お母さんでしょ」って声が聞こえてくるような・・。妙な力があるような気がします。」 「アルバムへ刺繍で名入れとお誕生日をいれてもらえるサービスを利用して出産時の記念として残しました。最近は撮影した写真はデーター保存するのみですが、生まれてから幼稚園までの一番かわいい時期をアルバムに残すことができました。あまりマメな性格ではないので、ちゃんとしたアルバムはこれだけの為、唯一無二の大切な記念品となりました。」 「ファーストシューズを妊娠中に手作りしました。生まれてくる我が子を思いながら、裁縫する時間も思い出になっています。退院後自宅に帰ってきてから一緒に記念撮影しました!12年たった今も大切に保管してあります。」 「誕生記念に木製ソファーを購入しました。一生使えるソファーなので子供の成長と共についた傷が思い出になると思い、我が家の記念樹代わりになっています。」 出産記念品は、愛着と思い出が沢山詰まった家族の大切な宝物ですね。最近では、簡単にスマホで写真や動画が撮れるので、データで残すことが日常ですが、写真はプリントして残すことをおすすめしている方が多くいました! 写真は部屋に飾ったりアルバムにしたりして、お子様の成長を見て懐かしむこともできます。カタチに残すことで、見るたびにあの小さな頃を思い出すことで、家族の絆が深まることもあるようです。お子様が小学2年生くらいになると、学校の授業の中で「生まれたころの思い出」に小さい頃の写真やよく遊んだおもちゃなど、エピソードを添えて持っていくことがあるようです。そんな時、「出産記念」が役立ちますね! 2. 誕生のお祝いと記念に!メモリアルアイテム紹介! 我が子の誕生の記念、出産の思い出に!人気のあるメモリアルアイテムについてご紹介していきます! 出産記念品は、自分で選んで準備する他に出産祝いで頂くことも。また、産院によっては、誕生記念のボードやアルバム、手形足形を残せるキットをプレゼントしてくれることもあるようですね。さらに調べを進めていくと、自治体によって出産誕生の記念樹の苗木を住民にプレゼントしてもらえる嬉しいサービスもありました! では、早速チェックしていきましょう! 2-1. 写真で残す!フォトスタンド&アルバム フォトアルバムやフォトスタンドは、王道と言っていい出産記念品です。20年程前は、写真館でフィルムのネガから現像して写真にしていましたので、作業が大変だったアルバム作りでした。しかし最近では、自宅で印刷したり、ネットプリントも普及して手軽にプリントができるようになっています。 また、写真館できれいなアルバムに仕立ててもらったりすることも可能に。さらに、スマホで撮った大量の写真の中から、自動でいい写真だけを選んでくれてフォトアルバムにしてくれるサービスは、忙しいママパパに人気となっています。...
便利そうで便利じゃない?!パパ休暇・パパママ育休プラスを徹底解説
※本記事は2022年9月までの制度についてまとめた記事です。2022年10月以降の「産後パパ育休」「育児休業」制度についてはこちらの記事をご覧ください。 「産後パパ育休」「育休」改正内容をどこよりもわかりやすく徹底解説 ここ数年で育休を取得するパパも増えてきましたね。育休を取得するパパのための制度「産後パパ育休」一体どのような制度なのか、詳しく知っていますか?育児介護休業法には、育児休業の他に、パパの育児休業取得... ナイスベビーラボ 2024.06.09 「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」 一体どのような制度なのか、詳しく知っていますか? 女性の育児休業取得が定着してまだ10年ちょっと、といったところでしょうか。 育休は女性のためだけではなく、子育てをする夫婦それぞれが取得できる権利を持っています。 「育休=女性」というイメージが根付いていましたが、ここ数年で育休を取得するパパも増えてきました。 とはいえ、パパが当たり前のように育休を取れる環境がまだまだ整っていないというのが日本社会でしょう。 法が制定されていても、十分に生かされないのであれば意味を成しません。 その現実としてあげられるのは、出産前後で約60%の女性が離職している状況はこの20年間変わっていないという状況です。 子育てと家事、仕事を一手に引き受け続けることがどれだけ大きな負担であるかがわかります。ママの社会復帰には、パパのサポートが不可欠。子育ては夫婦でするものという認識を社会全体が共有認識として捉えていかなければなりません。 育児介護休業法には、パパの育児休業取得を促進するため、夫婦が協力して育児休業を取得できるように 「パパ休暇」 「パパ・ママ育休プラス」 といった特例が設けられています。 育児休業をもっと柔軟に効率よく活用できるよう、パパの育休を2回にわけて取得することができる制度が「パパ休暇」です。 「パパ・ママ育休プラス」は必要に応じて育休期間を2ヵ月延長できる制度です。 通常の育休も最長で子供が2歳になるまで延長ができるなど、ご家庭の状況に応じて育休のスタイルを選ぶことができます。 しかし! この2つの制度は、単純に2回にわけて取得できる!2ヵ月延長できる!というものではなく、利用するためには「定められた一定の条件」を満たす必要があるのです。 この「一定の条件」というのが非常に複雑で、さっと理解できる制度ではありません>< 特に「パパ・ママ育休プラス」においては、育休が2ヵ月延長できるという聞こえは良いですが、現実的には取得するのは難しいと言ってもよいでしょう。 ここでは「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」それぞれの内容を通常の育休との比較も交えながら、できるだけわかりやすく図解と共に解説していきます。 また、先に予定されている改正案についても触れていきますので、是非情報として持ってください。 初めて聞く時は複雑で覚えるのも面倒と思うかもしれませんが、せっかく持っている大切な権利です。 しっかりと理解してどのように活用していくか、夫婦で話しあっていきましょう。...
背中スイッチ攻略法!効果絶大な先輩ママの対策事例とグッズ活用術!
授乳や抱っこでスヤスヤ腕の中で眠る赤ちゃん。ようやく寝かしつけに成功して布団の上に寝かせた途端、起きて泣き出してしまう。まるで背中に起動ボタンが付いているかのように、布団に置くと起きてしまうこの現象を「背中スイッチ」と言います。 背中スイッチが作動してしまえば、寝かしつけはまた一からやり直し。この繰り返しに日々奮闘している方も多いことでしょう。 抱っこだとずっと寝るのに、布団に置くとすぐ起きちゃう赤ちゃん。 寝たかな?と思っても5分も経たずして泣き出す赤ちゃん。 一度寝かしつければお布団に置いてもずっと寝てくれる赤ちゃん。 一人で布団に寝かせておくと一人でスヤスヤ眠る赤ちゃん。 この違いは良い悪いではなくて、これはもう赤ちゃんの個性として受け止めるしかありません。 それは分かっていても、背中スイッチが敏感すぎて抱っこしっぱなしでは、何もできません。家事ができないどころか、食事もトイレに行く時間すらゆっくり取れない、というのが現実です。 そしてこの問題に直面している方が大勢いて、みなさんとっても苦労しています。 そこで今回は、背中スイッチ対策を模索中の方に向けて、背中スイッチの原因と対策を解説していきます。 背中スイッチ対策にはこれが一番効果的!という断言はできません。それでも、様々対策法や便利なグッズがありますので、それらを参考にご自身であれこれ試しながらBestwayを見つけていきましょう。 そのお手伝いのために、これが効果的だったよ!という先輩ママのテクニックを紹介しますので、是非参考にしてください。 1. おろすと起きる背中スイッチが作動する原因 背中スイッチ作動は、温度差や体勢の変化、モロー反射、寝るための力など、さまざまな要因が考えられます。一番安心できるママの腕から急に離されることへの不安はとても大きいということでしょう。できるだけ腕の中にいるような環境を上手く整えてあげることが大切。 まずここでは、背中スイッチが作動する主な要因について解説していきます。 1-1. 抱っこと布団の温度差 ママの抱っこで安心して眠りについたところで、布団の上に寝かせられた時、ママに腕の中の体温とひんやしした布団との「温度差」が目を覚まさせる要因とも言われてます。ママから離れた不安と同時に体感の冷たさも感じ驚いてしまうことがあるようです。 1-2. 抱っこ時のCカーブ姿勢からの体勢変化 赤ちゃんは背中は首からお尻まで滑らかに「Cカーブ」を描いています。赤ちゃんが一番安心できる姿勢です。ママの腕で抱っこされている時はCカーブの姿勢になっていますが、布団に仰向けで寝かせた時に背中がピンと伸びてしまいます。この急な体勢の変化が刺激となり起きてしまう原因になると言われています。 1-3. 周囲の刺激により起こるモロー反射 生後間もない赤ちゃんが、寝ている時に、ピクッとして両手を万歳するような動きをしますよね。これを「モロー反射」と言います。周囲の刺激によって起こる反応で、体勢の変化や音や光など、様々な外的要因が引き金になります。ピクっとしてまたスヤスヤ眠ることもあれば、自分でびっくりして泣き出してしまうこともあります。 1-4. 抱っこから離すのは深い眠りに入ってから 寝かしつけに時間がかかる時は、ママパパもかなり心身ともに消耗してしまいますよね。 「もう下しても大丈夫かな?」と早めの見切りでお布団に下ろしてしまって大失敗することがよくあります。ツライですが、ここはもうひと頑張り!この5分が大きな差を生みます。あと一歩眠りが深くなってからゆっくりと次の寝かしつけ動作に移行しましょう。 1-5. 自分で寝る力がまだついていない 授乳やおしゃぶり、抱っこなど、入眠のサポートツールが必要な赤ちゃんは、まだ自力で寝る力が足りていないため、背中スイッチが敏感とも言われています。やっと眠ったところで布団に寝かせられた時に背中スイッチが作動して、さらに入眠ツールがないことの不安も重なり泣いてしまうことが多々あります。 2. 今すぐできる!先輩ママが実践した背中スイッチ攻略法 背中スイッチに苦戦した先輩ママたちが実践した攻略法を紹介します。ここではグッズを使用しない「寝かせ技」です。どれもすぐに実践できる手法ですので、今日から試してみてくださいね! 2-1. 寝かせる前に布団をあたためる...
『子育て本音トークvol.11』ベビー用品体験アイテム70種類総まとめ編
半年間に渡りお送りしてきましたナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』が全10回を持ちまして最終回を迎えました。体験者だから言えるレンタルでよかった!これは購入すべき!のリアルな話をたっぷり聞いてまいりました。 育休中に体験してもらったアイテムはなんと全70種類!何となく使ってみたら期待以上の活躍をしてくれた、使ってみたくてレンタルしたのにイマイチ使えなかったなど、使ってみないとわからないのがベビー用品。短い期間しか使わないからこそ、上手にアイテム選びをしたいですよね。 今回の第11弾はこれまでのトークの総集編として、全10回の中から選りすぐりのシーンを抜粋してお届けします。ベビー用品選びの参考になる話がたくさん盛り込まれてますので、是非参考にしてくださいね。 それでは、一緒に振り返りしていきましょう! 1. 使ってみた!ベビーベッド・布団・クーハン編 ミニサイズのベビーベッドをリビングの常設ベッドとして、ベビー布団やマットと共に使用。簡易型ベビーベッドは赤ちゃんの居場所として家中のあちこちで、持ち運びができるクーハンは沐浴の後のお着替えスペースや里帰り先での赤ちゃんの居場所として活躍しました。 1-1. ベビーベッドのおすすめはハイタイプ。お布団は必要性を感じたら検討 「ベビーベッドは絶対に必要。そして絶対にレンタル!必須期間は6ヵ月かな。あとは赤ちゃんの様子をみながら使用期間を検討する。あとは、お世話しやすくて体が楽なのでハイタイプはおすすめですね!」 「マットは必須、シーツ類なら断然エアスルー防水シーツがおすすめ!お布団はマットがあればいらないと思う。」 「もし布団を使うのであれば、ベッドをレンタルする時に、ベッドのサイズと合う布団を一緒にレンタルするのが絶対におすすめ。」 1-2. クーハンは借りて大正解!里帰りにも最適! 「クーハンは期待以上の大活躍!沐浴のあとの着替え場所として使ってました。クーハンに着替えセットとおむつを用意して、タオルでくるんだ赤ちゃんをクーハンにのせて、そのままお着替え♪」 「ピクニックやお出かけシーンでも出番はたくさんありますよね。」 「使う期間短いから買うほどじゃないんだけど、レンタルならすごくいい商品だと思う。里帰り先の赤ちゃんの居場所としても最適だし、私はクーハンと共に実家に行くかな(笑)」 『子育て本音トーク vol. 1』使ってみた!ベビーベッド・布団・クーハン編 2. 使ってみた!バウンサー・ハイローチェア編 日中の赤ちゃんの居場所として、ママの代わりにあやしてくれるバウンサー&ハイローチェア。赤ちゃんにフィットすればママの強いサポーターになること間違いなしのアイテムです。バウンサーは手動タイプと電動タイプ、ハイローチェアは電動タイプを体験しました。 2-1. リビングにベビーベッドがあるならバウンサー。なければハイローチェアで! 「日中の寝かしつけで使いました。一度、夕方泣きでいくらあやしても泣き止まないことがあって。ハイローチェアに寝かせてスイングさせて音楽も大きめにして、私の抱っこの代わりに寝かしつけをしました。」 「我が家はリビングにベビーベッドがあるので手動バウンサーが役に立ったけど、ベッドを置かない方なら断然ハイローチェアが便利だと思います。」 「初めてのお子さんなら電動バウンサーはとってもいいと思います。ちょっと金額が張るのでレンタルで(笑)」 「使える時期や赤ちゃんによって合う合わないってありますね~。」 「そういった意味では、購入は高いので興味があればレンタルで試すのがベストな商品だと思いますよ。」 2-2. 赤ちゃんのためというよりママのためのアイテム 「今回使った商品については、赤ちゃんのためというより自分のために使いました。これを使うことで、体が楽、疲れから多少なりとも解放される。そして、心にも余裕ができたし、育児を楽しくするにはいいアイテムだと実感しました。どれも子育てに必須のアイテムではないけど、ベビーベッド以外の赤ちゃんの居場所として、ママのサポーターとして是非使ってもらいたいです。」 『子育て本音トーク vol. 2』使ってみた!バウンサー・ハイローチェア編...
【完全ガイド】里帰り出産しない人必見!産後の生活に役立つ出産準備
妊娠をすると頭の中をよぎる「出産をどこでするか」の問題。特に初産であれば悩むところですね。 一般的に「出産=里帰り」と捉えることが多いと思いますが、家庭によりその事情はさまざま。里帰りしたくてもできなかったり、あえて里帰りしない選択もあります。 ここでは「里帰り出産をしない」という選択にフォーカスし、産後の生活を安心して過ごすためにはどうすべきか、考えていきたいと思います。 産後を自宅で過ごすことは、赤ちゃんのこと、家庭のこと、日常全てのことを自分たちでこなさなければなりません。産後すぐのママが産前と同じように動くことは不可能。スムーズな日常生活を送るために必要不可欠なのは、できる限りのサポートを利用すること。パパのサポートは言うなかれ、家族やご近所、行政のサポートや便利なサービスを使ってできる限り負担を減らすことを目指しましょう。 まずは、産後の生活をイメージしながら、赤ちゃんとの生活がスムーズに迎えることができるよう、産前に整えておくべき準備について考えていきましょう。 最後まで読んだ時、里帰り出産をしないと決めたママたちの見えない不安が少しでもクリアになっていれば…と願いながらこの記事を書いています。どうぞ最後までお付き合いください。 1. 里帰り出産は必須じゃない!里帰りしなくても大丈夫! 産後の床上げは21日と言われているように、産後の体はしっかりと休んで体調を戻していくことが何より大切。里帰りをすれば、産後は家族のサポートを受けてママは赤ちゃんのお世話に専念することができます。家事全般をやってもらえる他に、赤ちゃんのお世話について実母を頼れることも大きな理由でもありますね。 日本では昔から里帰りをする文化が根付いていますが、実は海外ではあまりなく、産後のママのサポートは母親ではなく、パートナーがメインで担うというがスタイル。むしろ、パートナーと離れて出産することに疑問を持たれるようです。 そう!里帰りしない場合は「パパの活躍」キーになるということです。 産後の日常生活における母体への一番の負担は「家事」。まずはそこを全面的にパパに担ってもらうことが何より重要です。とはいえ、仕事の都合などによっては、パパだけを頼りにできないということもあります。そんな時は他の手を、使えるものは全て使いましょう。 里帰り出産の実母の変わりとなるサポートやサービスを、産前からしっかりと確保しておく。そして何より大切なのはパパに可能な限りのことをしてもらう約束をしておくことです。ここを押さえておけば、里帰りしなくても大丈夫!里帰り出産は必須ではないですよ! 1-1. 意外?!「里帰りしなかった」が半数近く! 前述の通り、日本では里帰りという文化から「出産=里帰り」のイメージがありますが、実際のところどうなのでしょう? という事で「里帰りした or しなかった」について先輩ママパパ200人にアンケート調査実施してみました。結果はこの通り、ほぼ半々という結果になりました。里帰りが多いというイメージはありますが、実は、しない選択をする人も多いことがわかります。 1-2. 里帰りした理由を聞かせて 「赤ちゃんのお世話に専念できるように、育児以外の家事を協力してもらうため。子育てのアドバイスも受けたかったから」 「実家が近くだったので」 「自宅だと昼間は1人になってしまうため里帰りをしました」 「初めての出産で不安があり、実家も快く迎え入れて頂けたので協力をお願いした」 「初孫のため、両親が里帰りを希望していたため」 「母の勧めにより、体力回復までは実家にいるように言われたため」 「夫の帰りが遅く、一人の時に陣痛がきたら不安だったのと、産後のサポートを期待して里帰りした」 「夫の助けは期待できなかった。産後体力が戻ってない中で自分一人で初めての育児、家事をこなすのに不安があったから」 1-3. 里帰りしなかった理由を聞かせて 「最初からその考えはなかった」 「実家が遠方なので移動が大変。新生児を連れての長い移動をしたくなかった」...
『子育て本音トーク vol.5』使ってみた!お宮参り・お食い初め編【後編】
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』シリーズ第5弾! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第5弾は「お宮参り・お食い初め」についてを、前編、後編に分けてお届けしています! 前編「お宮参りの一日」では当日の様子をたっぷりと聞ききました。後編では「お宮参り衣装の和装と洋装、お食い初めの漆器」について、実際に着用した着物やドレスの体験談も含め、レンタル衣装やお食い初めのことなど、たっぷりと聞いていきたいと思います。 1. レンタルしたお宮参りの着物について 牡丹の花の本刺繍がとても魅力でした。 たばち「今回はお宮参り・お食い初め編の後編として「お宮参り衣装の和装と洋装、お食い初めの漆器」のアイテムについてお届けします!」 ととママ「レンタルしたのは着物とドレス、あとお食い初め漆器も使ってみました。」 たばち「まずはお宮参り衣装から。この着物を選んだ理由を聞かせてください。」 ととママ「上が男の子2人だからかな。可愛いピンクを赤ちゃんの時にどうしても着せたかったのが一番の理由です。」 たばち「デザインも色々あるから目移りしませんでしたか?」 ととママ「しましたよー(笑)この着物を選んだのは、華やかで可愛いお花がいっぱいのデザインと、真ん中にある牡丹の花の本刺繍がとても魅力でした。」 たばち「この豪華な刺繍は手作業ならではですよね!」 ととママ「せっかく出張撮影なので、実は贅沢にもう1枚、赤の着物でも撮影してもらいました(笑)」 2. レンタル着物をいろいろ見てみよう! 手にすることのできない逸品がレンタルなら出会える たばち「その他にもたくさん衣装を用意したので、いろいろと見ていきましょう。」 ととママ「これだけ衣装を並べると華やかですね!」 たばち「この絞りの着物、本当にキレイ。絞り風の柄と本絞りを比べるとこんなに質感が違うものなんですね。本物はやっぱりすごい!」 ととママ「絶対に購入できないこれだけのクオリティのものを着ることができるのは、レンタル最大の醍醐味なのかも。」 たばち「一般的には知られていないけど、今ではなかなか手にすることのできない逸品が、レンタルだと出会えるってことがありますよね。」 ととママ「多少レンタル代が高めでも一生に一度の記念だし、良いもの、納得いくものを選んでほしい!」 夏用の絽(ろ)の着物 たばち「こちらが夏用の絽(ろ)の着物です。この透け感と軽さ、夏ならではの雰囲気が素敵ですよね。」 ととママ「お宮参りは5月の後半でとっても天気のいい日だったんです。途中で赤ちゃんの顔が赤くなってきて、慌てて着物を外したんですね。あの日は絽の着物でもよかったと思う。」 たばち「夏は着物を着ないで、洋装だけの方も多いですよね。」 ととママ「絽の着物なら夏でも負担にならないし、絽の存在を知って是非着てもらいたい!」 ポップなデザインが魅力の映える化繊着物 たばち「こちらは昨年からレンタルを始めた化繊の着物です。」 ととママ「華やかでとってもかわいい。ポップで写真映えしそう。」...
『子育て本音トーク vol.5』使ってみた!お宮参り・お食い初め編【前編】
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』シリーズ第5弾! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第5弾は「お宮参り・お食い初め」についてを、前編、後編に分けてお届けします! 前編は、お宮参りの一日の流れや、着用した着物やベビードレスについて、また出張撮影の様子など当日の様子をたっぷりと聞いていきたいと思います。 たばち「今回はお宮参り・お食い初め編です!アイテム以外にお宮参りの一日についても話を聞きたいので、前編では「お宮参りの一日」、後編では「お宮参り衣装の和装と洋装、お食い初めの漆器」のアイテムについて、初の前編後編でお届けしたいと思います!」 ととママ「まずはお宮参りの一日ですね。実はお兄ちゃん2人はやらなかったので、今回3人目にして初体験!(笑)撮影は出張撮影をお願いしました。」 たばち「お宮参り、やってみてどうでしたか?」 ととママ「すごい良かった!本当にやってよかった!お宮参りは絶対にやるべき!と強く主張させてください!」 1. お宮参り当日のタイムスケジュールを見てみよう! 日程決めは赤ちゃんとママの体調を最優先に考えて! たばち「お宮参りをしたのは生後何日目だったのですか?」 ととママ「少し遅めだったのですが、1ヵ月検診終わった後で生後55日でした。」 たばち「日程はどうやって決めたのですか?」 ととママ「産前は一般的な生後一ヵ月頃にやろうかな、と思っていたのですが、実は生後間もなく入院してしまったこともあり、1ヵ月検診の結果を待って決めることにしました。特に問題もなかったので、少し落ち着いた頃に日程決めを始めました。」 たばち「何もなければ一般的に言われている生後1ヵ月がいいと思いますか?」 ととママ「私個人的な考えは、あまり風習にとらわれる必要はないと思ってます。赤ちゃんとママの体調を最優先に考えてご家庭のスタイルで決めていいと思いますよ。」 たばち「では、お宮参り当日のスケジュールを教えてください。」 お宮参り一日の流れ 6:00 起床・食事の準備 7:00 [兄2人・パパ]起床・朝食・支度 授乳、おむつ替えなど赤ちゃんの準備 8:00 自分の支度・出発の準備 9:00 出発 10:00 到着 到着と同時に出張撮影がスタート...
いつから始める出産準備まるわかり解説!妊娠月別準備スケジュール付
妊娠中期(5~7ヵ月)は心も体も安定し体も動かしやすくなる時期。お腹も徐々に大きくなるのと共に妊婦さんである実感もとても大きくなってくるころですね。 妊娠後期(8~10ヵ月)に入ると日に日にお腹も重たくなり、体の自由が効かないことも多くなります。産休に入り赤ちゃんを迎えるための色々な準備も忙しくなる時期です。 では、出産準備はいつ頃から始めるのがベストなのでしょう。 初めての出産であれば、準備をするとしても一体いつから何に手を付けていいのか、よくわからないですよね。 出産準備の開始時期に決まりはありませんが、まずは母体に無理のない範囲で進めることが大前提。産休に入ってからゆっくりと...と考える方も多いと思いますが、実はそれではちょっと遅いこともあります。 出産予定日はあくまでも予定の日。特に妊娠後期は急なトラブルも起こりやすい時期ですので、ギリギリで慌ててしまうことのないよう、余裕を持って準備することが大切です。 そこで今回は、出産準備の進め方を妊娠月に合わせて解説していきます。 準備品以外の生活で進めるべきことや、産後のために知っておきたい情報なども紹介します。便利な妊娠月別の準備スケジュール帳もダウンロードできますので、是非参考にしてくださいね。 1. 妊娠6~8ヵ月頃から徐々に始めたい出産準備 出産準備の開始時期として、ナイスベビーラボがおすすめしたい時期は妊娠6~8ヵ月頃。その理由としては、体調が安定し、現実的に動きやすい時期であることがあげられます。赤ちゃんの性別もわかるのでベビー用品選びのイメージもしやすいですね。 では、一般的にはいつ頃からスタートするのが多いのでしょうか?ナイスベビーラボで先輩ママにアンケート調査をしてみましたので、まずはその結果から見ていきましょう。 1-1. 出産準備はいつから?アンケート調査してみた! 1-2. 動きやすい時期にできることをスタートしよう アンケートでも一目瞭然。出産準備は妊娠7~8ヵ月でスタートした方が約半数を占めました。妊娠9ヵ月以降で準備を始める方が次に多い結果となり、産休に入ってから落ち着いて準備を進める方も多いようです。 妊娠7~8ヵ月は、妊婦生活にも慣れ体調も安定し、動きやすい時期。この頃が一番現実的に動ける時期ということなのでしょう。ナイスベビーラボが推奨する時期ともほぼ合致します。 9ヵ月以降になるとかなりお腹も大きくなり体の自由も効かなくなってきます。妊娠後期はママの体調にも変化が起こりやすいナーバスな時期。出産間近で買い物などで長時間外出するのはとてもリスキー、何が起こるかわかりません。 できればその前の動ける時期にやっておきたい準備がいくつかあります。出産準備は、少し早めの時期にやっておくべきこと、後期でもできることに分けて進めていくのがよいでしょう。具体的な準備の進め方についてこの後の章から順を追って解説していきますね。 2. 始める前に絶対に知ってほしい「出産準備の心得」 可愛いベビー用品を見ていると、あれもこれもほしくなったり、あったら便利かな?と使うのかわからないものまで買ってしまったり、これ、やりがちです。結局使わなかった、とか、肝心なことを準備していなかった、などの無駄や不足がないようにしたいものです。 ここでは出産準備を始めるにあたり知ってほしいことをまずは伝えたいと思います。 2-1. アイテムごとに異なる準備時期を知ろう 赤ちゃんを迎えるためには色々な準備品が必要となりますが、思いつくままに準備を進めてしまうのは絶対にNG!早すぎて邪魔になったり、後からもっといい物が見つかったり、遅すぎてほしいものが手に入らなかったりすることも考えられます。 例えば、外出時に使う抱っこ紐やベビーカーなど、育児には必須アイテムではありますが、実際、生まれて1ヵ月は外出を控えるために出番はありません。産前にはリサーチのみ、揃えるのは産後でも十分間に合います。 出産準備は急がずに、まずは、アイテムごとに準備すべき時期を知って、必要なものを徐々に揃えていきましょう。 2-2. 使わなかった...とならないために「必要最低限」が鉄則 ついつい買いすぎてしまいがちなベビー用品。可愛い赤ちゃんグッズはほしくなってしまうんですよね。わかります。ただ、揃えたわりには全然使わなかったという物も多くなってしまうので要注意。 産前に揃えるべきアイテムとしては、産後すぐに必要となるもの「必要最低限」を鉄則として準備していきましょう。 赤ちゃんによって使うものが異なってくることと、ママの状態によっても異なってきますので、産後の赤ちゃんとママの状態に合わせて揃えていくことをおすすめします。 出産準備リストについて、詳しくはこちらの記事で! >...
『ナイスベビー塾 Vol.3』洗えてたためるポータブルベビーサークルを学ぼう!
生後6ヶ月頃になると、そろそろハイハイをし始める赤ちゃんも出てきます。 ハイハイをし始めると一気に行動範囲が広がり、ちょっと目を離したすきにとんでもないところまで移動していた!なんてこともあります。家の中には階段や暖房器具、コンセントなど赤ちゃんにとって危険なものがたくさんありますし、間違って何かを口に入れてしまうことも…。 そうなると、もう気が気じゃなくて赤ちゃんから目が離せなくなってしまいますよね。 そんな時あると安心なのがベビーサークル。 ベビーサークルがあれば、赤ちゃん専用の安全に過ごせるスペースを作ることができます。 でも、ベビーサークルと聞くと、木製のガッチリとしたサークルや、プラスチック製の大きなパネルを連結させるサークルなど、けっこう大掛かりなものを想像しませんか? ベビーサークルは使ってみたいけど、そんな大きくて場所を取るものをお部屋にずっと置いておくことなんてできるかな?と言ったお悩みから作られた便利アイテムが今回ご紹介する「洗えてたためるポータブルベビーサークル」。 「洗えてたためるポータブルベビーサークル」は、必要なときにパッと開いて、使い終わったらサッと閉じることができる画期的なベビーサークルなんです。 社内勉強会の様子と併せてベビー用品を徹底的にご紹介する『ナイスベビー塾』の第三弾として、詳しく見ていきましょう! 1. パッと広げるだけ!すぐに使えるベビーサークル なんと言っても一番の特徴はコンパクトにたたんだ状態から「超簡単」に組み立てできることです。 安定プレートを付けてパッと広げるだけで、あっという間にベビーサークルが完成します。 初めて触るスタッフも1分かからずに組み立てることができました。 ワンタッチテントのような感覚でサッと展開できるので、ちょっとしたときでも億劫にならずすぐに使うことができます。 2. 使わないときはコンパクトに収納できる 使わないときは、ロックボタンを解錠してフレームを縮めるだけでこんなにコンパクトにたためます。 安定プレートで自立するからお部屋の隅に収納することができます。 これなら限られたスペースでも気兼ねなくベビーサークルを導入することができますね。 付属のショルダー付き収納バッグに入れれば、持ち運び時に便利です。 帰省や旅行、アウトドアにも持っていくことができて、様々なシチュエーションでベビーサークルを使うことができます。 本体重量は3.8kgと軽量。楽に持ち運びできることはポイントですね。 3. たためるタイプなのに中は広々快適&しっかり安定感! たためるタイプのベビーサークルなのに、内寸幅は131cmと中はけっこう広々としています。 コンパクトなベビーサークルだと中が狭くて、なんだか閉じ込められているような感じがしてかわいそうになってしまいますよね。 「洗えてたためるポータブルベビーサークル」 なら充分な広さが確保されていて、のびのび快適に遊ぶことができます。 ...
ウイルス感染や菌から赤ちゃんを守る!マスクさせずに家族ができる事
「外出したいけど、菌やウイルスが心配…」 感染症の流行している時期、不特定多数の人が大勢集まる場所では、どうしてもウイルスや菌をもらってしまう可能性があります。そんな中でも、赤ちゃんと一緒に外出をしなければならない時も多々ありますよね。どうやって赤ちゃんを守ったらいいか、ママはお悩みだと思います。 赤ちゃんにマスクはさせるべき? 嫌がる子にはどうしたらいいの? 赤ちゃん用のマスクってあるの? マスクをしないでウイルスから守る方法って? 赤ちゃんにマスクをさせることについては、それぞれのご家庭やママパパによってもかなり意見が分かれるようです。感染を予防するために用いられているマスクですが、口と鼻を覆うものなので呼吸の妨げになり、赤ちゃんが使用する場合、思わぬ事故につながる可能性も考えられます。 リスクを考えマスク以外の方法でウイルスや菌から赤ちゃんを守れたらいいですよね! ここでは、マスクを使用せずに行うウイルス対策について考えていきたいと思います。ご家庭でできること、日常の心構え次第で回避できることもたくさんあります。まずはできることをしっかりと。ご自身でできる感染予防を心がけて行きましょう。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 赤ちゃんのマスクは危険!事故の可能性も! まだ自分で意思表示ができない乳児期の赤ちゃんにとって、顔半分の鼻と口を覆うマスクは、安全なものとは言えません。授乳期の赤ちゃんにマスクをつけた場合、ミルクの吐き戻しによる窒息や呼吸困難などの事故や命の危険が考えられます。赤ちゃんを守るためと思っても、かえって危険です。乳児期の赤ちゃんにマスクをさせないでください。 2歳未満の子どもにマスクは不要、むしろ危険! 乳児の呼吸器の空気の通り道は狭いので、マスクは呼吸をしにくくさせ呼吸や心臓への負担になる マスクそのものやおう吐物による窒息のリスクが高まる マスクによって熱がこもり熱中症のリスクが高まる 顔色や口唇色、表情の変化など、体調異変への気づきが遅れるなど乳児に対する影響が心配。 引用:公益社団法人 日本小児科医会(2020/5/25時点) 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 2. 自分で付けはずしできるようになる2~3歳からマスクOK 自分でマスクを扱えるようになるのは2~3歳頃からでしょう。「好き嫌い」など、自我が芽生えてくるころは「イヤイヤ期」なんて呼び方をすることもありますよね。マスクをできるかどうかは、お子様の性格やその時の状態によっても異なります。 病院や電車などマスクをしてほしい場所では、家族みんなでマスクをして、「一緒だね」「可愛いマスクしようね」と声かけをしてあげると、喜んでマスクをつけてくれることもあるようです。自分でマスクを付けたりはずしたり練習しておくことも良いかと思います。マスクをさせる時は、必ず大人が見守ってあげましょう。 インフルエンザなどの感染症流行の時期に、予防接種をしなければならない時や健診などの外出予定もあると思います。ベビー用品メーカーから販売されている2歳以降から使えるマスクは、素材やドーム型の形状にして赤ちゃんの小さい顔にフィットする工夫がされています。 ただし、お子様が使用方法を誤ったり、吐き戻しを詰まらせるなどの危険はありますので、必ず大人がお子様から目を離さないよう注意が必要です。 ピジョン はじめてのマスク 7枚入 R...