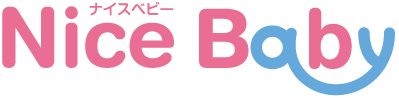出産準備・子育て
手づかみ食べに使いたい!離乳食から使えるひっくり返らないベビー食器
生後5~6ヵ月頃からスタートする離乳食。ママに大人しく食べさせてもらう時期はあっという間に過ぎ、すぐに遊び食べがはじまります。 手でぐちゃぐちゃぐちゃ、スプーンはポイっと投げる、手に届くものはぜ~んぶ触る倒す、せっかく用意した小さく可愛いベビー食器もポイポイされて台なし。 食事のたびに「はぁ~~~」とママのため息が聞こえてきそうな、そんな様子が目に浮かびます。 手づかみ食べ期の「遊び食べ」は赤ちゃんの成長の証であり、それはママも重々承知のこと。だけど、食事のたびにひっくり返ったお皿を片付けて、目も離せない状況はとってもツライですよね。 そんなママにおすすめしたいのが、イージーピージーのひっくり返らないベビー食器! テーブルにピタッとくっついて動かないんです! 赤ちゃんがポイポイしたくても、お皿が動かないから、赤ちゃんんも食事に集中できて、ママの負担も大幅に削減できます。 それだけじゃない! 高品質のシリコンを使用した、耐久性の高い安心安全な食器。電子レンジや食洗器ももちろん使えます。トレーとお皿の一体型だから後片付けもお皿洗いも簡単なのも嬉しいポイント。 そして機能性のみならず、なんと言ってもおすすめなのは、この見た目の可愛さ!おしゃれなデザインに豊富なカラーバリエーション、サイズや形も色々あるのでお気に入りが必ず見つかるはず。 また、お皿の形やトレーも上手に利用してフードアートにもチャレンジ!抜群に映えるプレートはSNSでも注目されること間違いなし! 贈り物にも絶対喜ばれる、イージーピージーの魅力をたっぷりとお伝えします。 1. これはすごい!離乳食から使える革命的ベビー食器「イージーピージー」 小さな赤ちゃんがいたら、絶対に買ってます、私。次に出産祝いを贈る時には、イージーピージーを贈ると決めています。これをもらったら絶対に喜んでもらえる自信があります! 革命的ベビー食器という言葉が正にぴったり。周りにオススメするだけでは事足らず、とうとうブログにまでつづってます(笑) そんなイージーピージーの特長をポイントごとにまとめて紹介していきますね。 1-1. ママのストレスがゼロになる!ひっくり返らないお皿 まず一番の特長である「ひっくり返らないお皿」。テーブルに置くとピタッとくっついて動かなくなります。赤ちゃんがお皿をポイっとしようとしてもできません。マット部分のフチをめくれば簡単にはがれますが、上に引っ張っても動きません。プラスチックなどの軽いお皿でよく起こる、簡単に持ち上げたり、ずれ落ちたりすることが起こりません。 また、お皿とマットが一体化しているため、食べこぼしもマットでキャッチできるし、マットの上に食べ物を置くことだっててきます。こぼすたびに駆け寄ってお片付けすることもなくなるので、ママのストレスもぐぐっと削減できるはずですよ。 1-2. 電子レンジも食洗器もOK!安心安全の高品質シリコン素材 赤ちゃんの食事で使うグッズのため、高品質で安全性が高い素材を使用しています。人体に有害な可能性があるとされているフタル酸・BPA・PVCは不使用。FDA承認の高品質シリコンを使用した、衛生的で耐久性の高いベビー食器です。 耐熱温度は-25度~220度と、耐熱性・耐寒性共に優れ、電子レンジや食洗器にも使えてとっても便利。耐久性も高く長い期間使っていただけます。汚れを寄せにくい性質なので衛生的、トレーとお皿が一体型なのでお皿洗いが一度にできるのも助かりますね。 1-3. カラーやデザインも豊富!インテリアにマッチするおしゃれなベビー食器 機能性バツグンのイージーピージーは、見た目の可愛さも大きな特長のひとつ。豊富なカラーバリエーションからキッチンやリビングのイメージに合うカラーがきっと見つかります。食器棚やキッチンに重ねて置いてもインテリアを邪魔しないおしゃれなベビー食器です。色違い、デザイン(形)違いで色々ほしくなって目移りしそうですが、楽しく選んでくださいね! 1-4. 可愛くて楽しいフードアート!映えるベビー食器でママも遊んじゃおう! 見てください!このキュートなフードアート!見てるだけでもワクワクしちゃいますね! イージーピージーは機能性だけではなく、食事の楽しさも教えてれる食器。こんな楽しいプレートだったら、お子さんのテンションもぐぐっとアップ!楽しいフードアートにはまるママたちも続出するかも?!ハッピーなお食事タイムになること間違いなしですね♪ フードアートはSNSにアップして幸せのシェアをしましょう!映えるプレートは周囲をざわつかせる投稿になりますよ! 2. くっついて動かないベビー食器を動画でみてみよう!...
赤ちゃんとの温泉は1歳から!危険を避けるためにすべき5つの事前準備
そろそろ赤ちゃん連れで温泉に行きたいなと思っているママやパパが多いのではないでしょうか。 そこで不安になるのが赤ちゃんはいつから温泉に入っても大丈夫なのかということ。 なんとなく小さな赤ちゃんは入れない方がいいのだろうけど、実際のところ本当にダメなの? 何歳からは入ってもいいの? なぜダメなの? そんな疑問に全てお答えします! 1歳頃までは温泉(大浴場の利用)はやめておくのがベター。 不特定多数の人が同じ温泉に浸かるため赤ちゃんが温泉に入るタイミングによっては衛生面に不安があります。 細菌と赤ちゃんが好む温泉は実は同じ。ぬるめで刺激の少ない温泉を細菌も好みます。つまり赤ちゃんが入れる温泉は細菌が発生している可能性があります。 大人にとっては多少汚れていても問題がない場合でも、まだ免疫の少ない赤ちゃんにとっては思わぬ健康トラブルに繋がることも。そのため、1歳頃までは温泉に浸かるのはやめておいた方が安心です。 しかし、日々休みなくこなしている育児。そんな日頃の疲れを癒すためにもたまには温泉へ行きたいと思っているママパパも多いはず! そんなママパパのためにぜひ知っておいて欲しい1歳未満の赤ちゃんとも安全で楽しく一緒に温泉を過ごすコツをご紹介します。 最後まで読んで頂ければ、赤ちゃんとの温泉が不安なイベント事ではなく、HAPPYなイベントになりそうだと自信を持つことができます。 赤ちゃんとの初めての温泉をぜひ楽しかった一生の思い出として残して下さいね。 1. 赤ちゃんの温泉(大浴場利用)は1歳頃まではやめておくのがベター 不特定多数の人が同じ湯舟につかる大浴場の利用は衛生面からまだ免疫力の弱い赤ちゃんには危険です。 また、濡れて滑りやすい浴場を赤ちゃんを両手で抱っこしながら移動するのも考えただけでも大変そうですよね。 そのため赤ちゃんの負担やママパパの負担、さらに周りの方への配慮も考えると1歳頃までは温泉は避けておいた方が無難です。 しかし、温泉の大浴場でなくても温泉を楽しむ方法もあります。2章ではその方法もご紹介していきます。 1-1. 小さな赤ちゃんの体への負担が大きい 温泉は不特定多数の人が同じ湯舟に浸かるため衛生面に不安があります。そのため免疫力が戻る1歳頃まではなるべく避けましょう。 もちろん、温泉施設によっては1日1回の清掃ではなく複数回掃除をすることで衛生に気をつけている場所もありますが、実際のところはどのタイミングで掃除をしているかわからないため、入浴するタイミングによってはお湯が汚れてしまっている場合があります。お湯が汚れてしまっていると細菌が温泉の中で繁殖している可能性があります。 特に日本の中で最も多い中性~弱アルカリ性の温泉は、肌への刺激が少ないため肌が弱い人でも安心して入浴することができますが、衛生面でみると酸性やアルカリ性の温泉の方が検出される菌数が少ない調査結果がでています。 赤ちゃんが温泉に入ることでの健康被害についてはっきりとした医学的なデータはありません。しかし、赤ちゃんは1歳頃になるまでは免疫力が低いため細菌などの外敵にとても弱いことは事実です。そのため、湯船に細菌などがいる可能性やうっかり温泉を誤飲してしまう可能性も考えると赤ちゃんの温泉は大事をとって1歳頃までは避けておいた方が無難です。 源泉掛け流し温泉なら大丈夫? 高温の源泉掛け流し温泉や硫黄泉、酸性泉ではレジオネラ菌が検出されない場合が多かったという調査結果が医学会雑誌に掲載されています(参照1)。 厚生労働省では特にレジオネラ菌(症状:肺炎や熱など)の感染リスクが高い人として高齢者や新生児を挙げています(参照2)。 しかし、源泉掛け流し温泉は高温である場合がほとんどのため赤ちゃんには熱すぎてのぼせてしまいます。 また、臭いがきつい硫黄泉やピリピリする酸性泉はまだ肌の弱い赤ちゃんには向いていません。菌が発生しにくくとも赤ちゃんに合わない温泉のため源泉掛け流し温泉等は避けてあげましょう。 参照1:衛生面からみた温泉【(財)中央温泉研究所】...
出産準備品は最低限で!子育てミニマリストが提案する出産準備リスト
「出産準備」妊娠をするとよく耳にする言葉ですね。なんとなくイメージできるけど、実際にはどんなものが必要なの?と疑問を持つママはとても多いと思います。 ネットで検索してみると、出産準備に必要なものを細かくリスト化してくれているサイトがたくさんあります。とてもみやすく丁寧に書かれていますよね。 でも、そろえるものが多すぎて、正直びっくりしませんか? ネットでみる出産準備リストにあるものを全て揃えれば準備万端かもしれませんが、その半分も使わなかった、なんてこともありえます。 出産準備とは産後に使用するものを、産前にそろえておく準備のこと。産後に何が必要か、それは、正直産後になってみないとわかりません。一言で言ってしまえば「必要なものは人によって異なる」からです。 筆者の私は、産休に入ってすぐの頃、出産経験者の姉に付き合ってもらい出産準備の買い物にいきました。経験者のアドバイスで必要なものや便利だったものをそろえましたが、実際に私には必要なかったものや、後から買い足したものもありました。 子育てグッズは必要最低限、できるだけお金はかけない、が私のモットー。ありがたいことに家族や知人からのお譲りも多く、大きなものはほとんど買う必要がありませんでした。私ほどミニマムに抑えた人はいないんじゃないか、と自分で思うほどです(笑)。 そんな私がおススメするのは、まずはミニマムで準備して、産後のママと赤ちゃんの様子を見ながら、少しずつ必要になったものを揃えていくスタイル。 「出産準備リスト=産後すぐに必要なもの」という定義を前提に、 今回は自称"子育てミニマリスト"の私から、最低限これを揃えておけば大丈夫!という厳選アイテムをまとめた「出産準備ミニマムリスト」を提案します。出産準備に迷っているプレママの参考になればうれしいです。 本記事の内容は、あくまでも筆者の経験に基づく個人的意見をまとめた記事であるということをご理解いただけますと幸いです。 1. 出産準備リストからみる、いる?いらない?の考え方 アイテムを揃える際の考え方として「生まれる季節ごと」「カテゴリごと」に分けられていることが多いです。ここでは、詳細なアイテムを見る前に、季節ごと、カテゴリごとでジャッジできる考え方について述べていきたいと思います。 1-1. 生まれる季節によってアイテムは変わるのか?! 生まれる季節ごとの出産準備リストをあちこちで入手することができます。暑い、寒いで、着る服も使うものも異なります。季節によって変えましょう。といった提案が一般的な出産準備リストですが、実際のところ、夏でも冬でも大きくはかわりません。 夏も冬も家の中では快適な温度が保たれています。ましてや、新生児のいるお家です。我慢してエアコンやヒーターをつけないなんてご家庭はないと思いますし、生まれてすぐは外出も控える方がほとんどです。季節を意識したアイテムはもう少し経ってから、必要性を感じてからの準備でも問題ありません。 生まれる季節ごとのリストを見比べても、実際にはアイテムに大きくかわる点は少なく、すぐに必要と思われるものありませんので、季節を意識した出産準備をする必要はないでしょう。 1-2. カテゴリから考える出産準備アイテムのいる・いらない 出産準備品のカテゴリとして、上記のようにまとめらることが多いようです。 このカテゴリの下に、細かい準備品がぶら下がってくるとイメージしてください。 これを見ただけでは、初めての出産の場合、何が必要か不要かの判断がつきにくいと思いますが、実は、この段階でほぼ不要なものも見受けれられます。 ここで注目すべきカテゴリ3つについて解説します。 お出かけ関連グッズ 今回は「出産準備リスト=産後すぐに必要な物」と定義しています。 一般的に産後すぐは、ママや赤ちゃんの体調を考慮して外出を控えることが多いため「お出かけグッズ」は必然的に不要。産前に準備しておくマストアイテムではないことがわかりますね。 ここで唯一必要となるのは、退院時に車で自宅に戻るケース。この場合は赤ちゃんを車に乗せるためのチャイルドシートの使用が必要となります。 授乳関連グッズ 完全母乳で育てる場合、哺乳瓶は必要ありません。ただ、完全母乳で育てたいと思っても、最初は分泌量が足りずミルクを足さなければならないこともあります。哺乳瓶は一つ持っておくと安心ですが、乳首のサイズや形状なども異なるので、どれを用意するかも難しいところ。 入院中に母乳の出方と赤ちゃんの様子を見ながら助産師さんに相談してみるといいと思います。...
今しか使わないのに今こそ必要なベビー用品…レンタルしたらこんなに楽だった!
「あると便利かも?」そう思ってついつい買いすぎてしまうベビーグッズや育児グッズ。 しかし、意外と高い…、購入したけど全然使わなかった…、なんていうのもよくある話ですよね!そんなときにおすすめなのが、必要なものを必要なときに「レンタル」するという選択。 最近のレンタルサービスは品ぞろえはもちろんのこと、メンテナンスやサービスなども充実!かしこく利用するママも増えてきています。 今回は、そんなママが大集合!レンタルグッズの魅力をたっぷりとご紹介します。 ベビーグッズのレンタル…ママたちはどう考える? ベビーグッズや育児グッズは、必ず購入しなければいけない?いいえ、そんなことはありません。 使用する場所、使用する期間などに応じ、実は気軽にレンタルすることもできるんです! ただ、ベビーグッズのレンタルに関して、ママが迷うことも多いようで… 買うのとレンタル、どっちがお得? 出産された方はベビー体重計買いましたか?レンタルしましたか? 買う方が良いのか、レンタルする方が良いのか迷い中です。。 返却時、つけてしまった「キズ」や「汚れ」が心配… A型ベビーカーのレンタルを検討しています。…… 返却の際にキズとか汚れの賠償とかうるさいのかなとか、いろいろと心配もあります😥 レンタル会社ってたくさんあって分からない! チャイルドシートやベビーカー等レンタルしようと思ったのですが、どこが良いのでしょう💦 レンタルする物のメーカーはあまり気にしないのですが…検索すると色々出てきてどこからレンタルしたら良いやら😵 大切な赤ちゃんのために使うもの。せっかくレンタルするのなら、納得いくものを選びたいですよね! 「実際はどうなの?」レンタルグッズで育児中のママたちが大集合 今回は、レンタルグッズ未経験のママ必見! 実際にレンタルグッズを使用したことのあるママも含めた先輩ママたちに、気になるあれこれを聞いてみました。 Q レンタルの印象は? 商品の状態や衛生面が気になる!が正直なところ… レンタル経験者のママも、最初はレンタルに対して不安を抱いていたそう。 ゆかさん:「赤ちゃんに使うものなので、商品の状態や衛生面などが気になりました。 どんな状態で来るのかが心配で…」 壊れたり汚れたりしたときはどうなる? なおこさん:「私は、実際にレンタルをしたときに、汚れてしまったり、壊れてしまったりした場合に、どうなるんだろう…という心配もありました」 Q レンタルグッズを使用しようと思ったきっかけは? とりあえず試してみようかな?...
パパママ必見!妊娠・出産でもらえるお金が200万円超!?知って得するマネーガイド【手続きチェッ...
妊娠おめでとうございます! 産まれてくる赤ちゃんの顔を見る日が今からとても楽しみな時期かと思います。赤ちゃんを迎える新しい生活の始まりを心待ちに、幸せ一杯で嬉しい反面、妊娠すると妊婦検診や検査などで出産にかかるお金のことを考えると不安もありますよね。 出産費用と言っても、特に初めての出産の場合、一体何にいくらかかるのかなど想像もつかないことだと思います。 妊娠・出産は基本的に病気ではないため健康保険が適用されません。その場合、一般的に妊婦検診や検査でかかる医療費は約10万円、正常分娩で30万~70万円、平均約50万円程かかると言われています。 さらに医療費に加え出産に向けて必要となるマタニティ用品やベビー用品を合わせると出産前後1年間でかかる費用は総額で約50万円~100万円程もかかると言われています。 金額を聞いてびっくりされると思いますが、実はきちんと公的制度を知り手続きをすれば「もらえるお金・戻るお金」は沢山あります。 全ての制度を利用すると最低でも専業主婦のママは約52万円、職場復帰予定のママ(平均月収が20万円)なら、なんと!約216万円分も支援を受けることができます。 これらの制度を上手に賢く使って頂いたうえでさらに、各地方自治体や企業が独自に行っている支援についてもご紹介させて頂きます。自治体によってはかなりお得な支援もありますので、知っていると得をする!そんな情報をあわせてご紹介させて頂きます。 そして、一番大切なことは、お金が「もらえる・戻る」ためにはどれも必ず自ら申請する必要があります。ただ待っているだけではお金をもらうことはできません。必ず申請方法まで確認してもらえるものはもらいましょう。 妊娠したママだけではなく、将来ママ・パパになる予定の方にも必ず知って頂きたいマネー知識です。ぜひ最後までお付き合い下さい。 1. ママの働き方によって違う『もらえるお金・戻るお金』 妊娠・出産時に受けられる支援は沢山ありますが、実は全てのママが全ての支援を受けることができるわけではありません。 ママの働き方によって受けられる支援が異なるため、今回「職場復帰」「出産退職」「専業主婦」の3パターンにママをわけて、受けられる支援をそれぞれママ別に紹介していきます。 まず、妊娠・出産時にもらえるお金として「妊婦検診費の助成」「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」の4つの支援があります。 妊娠・出産時には約50万~100万円ほどかかると言われていますが、もらえる支援をしっかりと受けると実際ご自身で持ち出す金額をぐっと減らすことができます。 ご自身が受けられる支援の内容や手続き方法を把握して頂き、漏らすことなく「もらえるお金・戻るお金」を増やしましょう。 職場復帰ママ 雇用保険・健康保険に加入し、現在働いていて出産を気に一時的に仕事を休み産後に現在の職場で仕事を継続予定ママ 【勤務先の健康保険に産前産後変わらず加入】 出産退職ママ 雇用保険・健康保険に加入し、出産のタイミングで退職しようとしているママ 【退職後はパパの健康保険の被扶養者又は国民健康保険に加入】 専業主婦ママ 専業主婦や自営業、フリーランス、パート(保険加入なし)で勤務しているが、雇用保険・社会保険にもはいっていないママ 【パパが加入している健康保険の被扶養者か国民健康保険に加入】 【ママ別】妊娠・出産で「もらえるお金」一覧 職場復帰 出産退職 専業主婦 妊婦検診費の助成...
出産祝いで喜ばれるもの第1位は「現金」!?子育てママに聞く真実
先日、高校時代の友人から出産の報告を受け、出産祝いを贈ることにしました。何を贈ろうかネットで最近のおすすめプレゼントリストなど様々なサイトを調べましたが、これだと思う商品が見つからず調べれば調べるほど深みにはまり分からなくなっていきました。自分が出産祝いをもらった時の記憶をさかのぼると、ふと親戚から写真立てをもらったことを思い出しました。何年も前のことですし、どんな写真立てだったかもうろ覚えで、当然どの部屋にも飾ってはいませんでした。大体の頂きものをしまっておく場所は見当がついていたのでその物置を調べると、当時もらったそのままの状態のきれいに箱詰めされた新品の写真立てを見つけ出しました。何年もの間この物置で眠っていた写真立ては、この日思い出さなければこのまま一生眠り続けていたことでしょう。もちろんお祝いの気持ちこそが大切ですが、一生眠り続けてしまうようなものでは贈る意味がありません。友人には本当にもらって良かったと思われるものを贈ろう!と決意を固めました。そこで、本当に心から喜んでもらえる出産祝いは何なのかを解明すべく、まさに出産祝いをもらったばかりのママたちが集まる当社(ナイスベビー)のネットワークを使い、聞き込み調査を実施しリアルな声を集計しました。この記事はアンケート結果をそのままランキングへ反映した、今子育てママが思う「出産祝いでもらって本当に良かったものベスト5」になります。私のようにこれから出産祝いに何を贈ろうか迷っている人は多いと思いますが、とりあえず無難なものを贈ればいいかなと当たり障りのないものを選んでしまう前に、まずはこの記事を読んでみてください。読み終えて頂ければ本当に心から喜ばれる出産祝いのヒントが見つかることでしょう。また、それぞれのランキングごとに、注意点やアンケート結果によるリアルな人気商品を合わせてまとめましたので、大いに役に立つはずです。 1. 子育てママに聞いた出産祝いでもらって本当に良かったものベスト5 1-1. 本当に良かった第1位「現金」 今回のアンケートで最も回答数が多かったのが意外にも「現金」です!予想していなかった結果に驚きました。出産祝いは一般的に赤ちゃんが使うもの、可愛らしいものなどを連想しますが、子育てママのリアルな声を聞くと、本当にもらって良かったものは「現金」という意見が一番多かったのです。 出産祝いをもらったことがある子育てママ187名にナイスベビーラボがアンケート調査(2019年6月実施) 贈る側からすると「なんだか冷たい印象を与えてしまわないかな?」とか「考えるのがめんどくさかったと思われないかな?」とか心配になってしまうかもしれませんが、今回のアンケート結果では否定的な意見は無く、「本当に必要なものを自分で選んで買えること」が他の贈りものには無い最も嬉しいポイントになるようです。 1-1-1. 出産祝いに現金は失礼にあたらない ご祝儀やお香典と同様に、一般的に出産祝いで現金を贈ることは失礼にはなりませんし、マナー違反でもありません。赤ちゃんが生まれるとミルク代や紙オムツ代など他にもいろいろなことにお金がかかるので、貰って一番役立つのがお金と言えるようです。特に2人目や3人目の赤ちゃんの場合は、ベビー用品が既に揃っているケースも多いので、本当に必要なものを自分で買える現金が一番喜ばれる可能性が高いです。 ただし、上司や先輩など目上の方に出産祝いを贈る場合に現金はマナー違反になってしまうので注意が必要です。出産祝いだけに限らず、お祝い事において目上の方へ現金を包むことはマナー違反にあたってしまいます。その為、ご出産祝いで現金を贈る場合は友達や同僚、後輩の人だけにするようにしましょう。 1-1-2. 相場は3,000円~10,000円ほど 出産祝いで贈る現金の相場は、贈る相手との親しさや年代によっても変わりますが、一般的に友達へ贈るのであれば3,000円~10,000円になるようです。あまりにも高額だと相手が恐縮してしまったり、お返しのことを悩ませてしまうので注意しましょう。 友達 3,000~10,000円ほど 親戚 5,000~10,000円ほど 同僚・後輩 3,000~5,000円ほど 1-1-3. 現金の代わりに商品券でもOK 一般的に問題はありませんが、「やっぱり現金を贈るのはちょっと生々しい・・・」と感じる場合は代わりに商品券を贈るのもOKです。商品券であればお祝い用のかわいいラッピングも出来ますし、現金を贈るよりも抵抗は少ないかもしれません。商品券を贈る場合は全国どこでも使えるJCBギフトカードやVJAギフトカードがおすすめです。また、最近ではAmazonギフトカードや楽天ポイントギフトカードを贈るなど商品券にもバリエーションが増えていますね。 1-2. 本当に良かった第2位「紙おむつ(たくさん)」 出産祝いでもらって本当に良かったもの第2位は「紙おむつ」です。オシャレでインスタ映えする人気のおむつケーキではありません。紙おむつをパックや箱でドンっと贈るのです!新生児の赤ちゃんは紙おむつを1日に約10~15枚も使います。実用性重視で絶対に必要な消耗品の紙おむつを出産祝いに贈ればきっと喜ばれます。ただし、やはり実用性重視の為、親しい友達へのプレゼントとして選択することをおすすめします。 1-2-1. 出産祝いにはSサイズ以上の紙おむつがおすすめ...