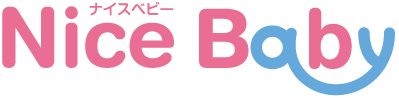出産準備・子育て
出産準備リスト|必須の品を3日でそろえるための決定版
「出産で準備するもの、たくさんあって大変!」 「多すぎて、どれから選べばいいのかわからない……」 「本当に全部必要?」 初めての出産、期待と同時に不安も感じますよね。 特に、出産準備品については、情報がたくさんありすぎて「何から準備すればいいの?」と迷ってしまうのではないでしょうか。 実は、一般的に紹介されている出産準備品を、全て用意する必要はありません。 まずは最低限のものをそろえて、その上で、状況に応じて必要なものを追加していきましょう。 以下の【最低限そろえておくべきリスト】をそろえておけば大丈夫です。 参考:出産準備品は最低限で!子育てミニマリストが提案する出産準備リスト これだけでもそろえるのが大変そうに思われるかもしれませんが、ベビー用品店でまとめて購入したり、セット品を活用すれば3日程度で準備可能です。 なぜ必須のものから準備するかというと、闇雲にいろいろなものをそろえても、「ほとんど使わず後悔するアイテム」もあるからです。 【必須→あったら便利→あとから買える】と優先順位をつけて準備することで、無駄な出費や、あれこれと準備をする時間が減らせますよ。 本記事では、無駄なく効率的に出産準備を進められるよう、優先順位別に紹介しています。 1. 【必須!】最低限そろえておくべき出産準備リスト 2. 必要に応じて追加すると良い出産準備リスト 安心して赤ちゃんを迎えられるように、ぜひ準備をする際の参考にしてくださいね。 1. 【必須!】最低限そろえておくべき出産準備リスト この章では、最低限そろえておくべき出産準備リストをご紹介します。 まずは、表の「準備する時期」を目安に、ここでお伝えしている商品をそろえておけば大丈夫です。 【最低限そろえておくべき出産準備リスト】 準備する時期 アイテム 個数目安 費用目安(1つあたり) どこで買える? 母子手帳を貰ってから 母子手帳ケース 1個 2,000円~...
「産後パパ育休」「育休」改正内容をどこよりもわかりやすく徹底解説
ここ数年で育休を取得するパパも増えてきましたね。 育休を取得するパパのための制度「産後パパ育休」 一体どのような制度なのか、詳しく知っていますか? 育児介護休業法には、育児休業の他に、パパの育児休業取得を促進するため、夫婦が協力して育児休業を取得できるように「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」といった特例が設けられています。 パパが当たり前のように育休を取れる環境づくり、さらに育休の充実をはかるため、2022年4月から育児介護休業法の改正が行われています。 2022年10月の「産後パパ育休」の制定と「育児休業」の改正により、育児休業がより柔軟に取得できるようになりました。 今回は、2022年10月から適用の「産後パパ育休」と、改正された「育児休業」と「育児休業延長」について詳しく解説していきます。 後半には、継続される「パパ・ママ育休プラス」についても触れていきます。 取得には細かなルールがあり、複雑で覚えるのが面倒と思うかもしれませんが、せっかく持っている大切な権利です。しっかりと理解してどのように活用していくか、夫婦でしっかりと話しあっていきましょう。 1.「産後パパ育休」の内容をわかりやすく解説 2022年4月の育児介護休業法の改正で、事業主に対して労働者への育休取得の意向確認が義務付けられました。 「育休を取得するのかしないのか」は確認されますが、育休取得に絡む要件について、こと細かに説明してくれる会社は少ないかもしれません。 基本的に、育休や産休に絡む情報は、自らが進んで情報収集をしないと得られないと考えた方がいいと思います。 2022年10月からは「パパ休暇」は廃止され、新たに「産後パパ育休」が適用となります。 まずは「産後パパ育休」とは、一体どんな制度なのかを解説していきますので、一緒に確認していきましょう。 \2022年9月までの「パパ休暇」について詳しくはこちらの記事で!/ 便利そうで便利じゃない?!パパ休暇・パパママ育休プラスを徹底解説 「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」一体どのような制度なのか、詳しく知っていますか?女性の育児休業取得が定着してまだ10年ちょっと、といったところでしょうか。育休は女性のためだけではなく、子育てをす... ナイスベビーラボ 2024.06.09 1-1. 「産後パパ育休」と「育児休業」は別の休業制度 「産後パパ育休」は、正式には『出生時育児休業』といいます。通称が「産後パパ育休」です。 名前が違っても同じ休業のことを指しています。 基本的な考え方として、出生時育児休業という名の通り、子どもが生まれたときに取得する育児休業です。 子供が1歳になるまでに取得できる、いわゆる従来の「育児休業」とは別の休業です。 まずはこのことを理解した上で、以下の章を読み進めてください。 育児休業取得条件に満たなければ産後パパ育休もNG 基本的に産後パパ育休も育児休業なので、下記のような育休取得条件に該当しない場合は産後パパ育休の取得もできません。 入社1年未満の場合 育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明確である場合...
便利そうで便利じゃない?!パパ休暇・パパママ育休プラスを徹底解説
※本記事は2022年9月までの制度についてまとめた記事です。2022年10月以降の「産後パパ育休」「育児休業」制度についてはこちらの記事をご覧ください。 「産後パパ育休」「育休」改正内容をどこよりもわかりやすく徹底解説 ここ数年で育休を取得するパパも増えてきましたね。育休を取得するパパのための制度「産後パパ育休」一体どのような制度なのか、詳しく知っていますか?育児介護休業法には、育児休業の他に、パパの育児休業取得... ナイスベビーラボ 2024.06.09 「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」 一体どのような制度なのか、詳しく知っていますか? 女性の育児休業取得が定着してまだ10年ちょっと、といったところでしょうか。 育休は女性のためだけではなく、子育てをする夫婦それぞれが取得できる権利を持っています。 「育休=女性」というイメージが根付いていましたが、ここ数年で育休を取得するパパも増えてきました。 とはいえ、パパが当たり前のように育休を取れる環境がまだまだ整っていないというのが日本社会でしょう。 法が制定されていても、十分に生かされないのであれば意味を成しません。 その現実としてあげられるのは、出産前後で約60%の女性が離職している状況はこの20年間変わっていないという状況です。 子育てと家事、仕事を一手に引き受け続けることがどれだけ大きな負担であるかがわかります。ママの社会復帰には、パパのサポートが不可欠。子育ては夫婦でするものという認識を社会全体が共有認識として捉えていかなければなりません。 育児介護休業法には、パパの育児休業取得を促進するため、夫婦が協力して育児休業を取得できるように 「パパ休暇」 「パパ・ママ育休プラス」 といった特例が設けられています。 育児休業をもっと柔軟に効率よく活用できるよう、パパの育休を2回にわけて取得することができる制度が「パパ休暇」です。 「パパ・ママ育休プラス」は必要に応じて育休期間を2ヵ月延長できる制度です。 通常の育休も最長で子供が2歳になるまで延長ができるなど、ご家庭の状況に応じて育休のスタイルを選ぶことができます。 しかし! この2つの制度は、単純に2回にわけて取得できる!2ヵ月延長できる!というものではなく、利用するためには「定められた一定の条件」を満たす必要があるのです。 この「一定の条件」というのが非常に複雑で、さっと理解できる制度ではありません>< 特に「パパ・ママ育休プラス」においては、育休が2ヵ月延長できるという聞こえは良いですが、現実的には取得するのは難しいと言ってもよいでしょう。 ここでは「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」それぞれの内容を通常の育休との比較も交えながら、できるだけわかりやすく図解と共に解説していきます。 また、先に予定されている改正案についても触れていきますので、是非情報として持ってください。 初めて聞く時は複雑で覚えるのも面倒と思うかもしれませんが、せっかく持っている大切な権利です。 しっかりと理解してどのように活用していくか、夫婦で話しあっていきましょう。...
『ナイスベビー塾 Vol.3』洗えてたためるポータブルベビーサークルを学ぼう!
生後6ヶ月頃になると、そろそろハイハイをし始める赤ちゃんも出てきます。 ハイハイをし始めると一気に行動範囲が広がり、ちょっと目を離したすきにとんでもないところまで移動していた!なんてこともあります。家の中には階段や暖房器具、コンセントなど赤ちゃんにとって危険なものがたくさんありますし、間違って何かを口に入れてしまうことも…。 そうなると、もう気が気じゃなくて赤ちゃんから目が離せなくなってしまいますよね。 そんな時あると安心なのがベビーサークル。 ベビーサークルがあれば、赤ちゃん専用の安全に過ごせるスペースを作ることができます。 でも、ベビーサークルと聞くと、木製のガッチリとしたサークルや、プラスチック製の大きなパネルを連結させるサークルなど、けっこう大掛かりなものを想像しませんか? ベビーサークルは使ってみたいけど、そんな大きくて場所を取るものをお部屋にずっと置いておくことなんてできるかな?と言ったお悩みから作られた便利アイテムが今回ご紹介する「洗えてたためるポータブルベビーサークル」。 「洗えてたためるポータブルベビーサークル」は、必要なときにパッと開いて、使い終わったらサッと閉じることができる画期的なベビーサークルなんです。 社内勉強会の様子と併せてベビー用品を徹底的にご紹介する『ナイスベビー塾』の第三弾として、詳しく見ていきましょう! 1. パッと広げるだけ!すぐに使えるベビーサークル なんと言っても一番の特徴はコンパクトにたたんだ状態から「超簡単」に組み立てできることです。 安定プレートを付けてパッと広げるだけで、あっという間にベビーサークルが完成します。 初めて触るスタッフも1分かからずに組み立てることができました。 ワンタッチテントのような感覚でサッと展開できるので、ちょっとしたときでも億劫にならずすぐに使うことができます。 2. 使わないときはコンパクトに収納できる 使わないときは、ロックボタンを解錠してフレームを縮めるだけでこんなにコンパクトにたためます。 安定プレートで自立するからお部屋の隅に収納することができます。 これなら限られたスペースでも気兼ねなくベビーサークルを導入することができますね。 付属のショルダー付き収納バッグに入れれば、持ち運び時に便利です。 帰省や旅行、アウトドアにも持っていくことができて、様々なシチュエーションでベビーサークルを使うことができます。 本体重量は3.8kgと軽量。楽に持ち運びできることはポイントですね。 3. たためるタイプなのに中は広々快適&しっかり安定感! たためるタイプのベビーサークルなのに、内寸幅は131cmと中はけっこう広々としています。 コンパクトなベビーサークルだと中が狭くて、なんだか閉じ込められているような感じがしてかわいそうになってしまいますよね。 「洗えてたためるポータブルベビーサークル」 なら充分な広さが確保されていて、のびのび快適に遊ぶことができます。 ...
パパママ必見!妊娠・出産でもらえるお金が200万円超!?知って得するマネーガイド【手続きチェッ...
妊娠おめでとうございます! 産まれてくる赤ちゃんの顔を見る日が今からとても楽しみな時期かと思います。赤ちゃんを迎える新しい生活の始まりを心待ちに、幸せ一杯で嬉しい反面、妊娠すると妊婦検診や検査などで出産にかかるお金のことを考えると不安もありますよね。 出産費用と言っても、特に初めての出産の場合、一体何にいくらかかるのかなど想像もつかないことだと思います。 妊娠・出産は基本的に病気ではないため健康保険が適用されません。その場合、一般的に妊婦検診や検査でかかる医療費は約10万円、正常分娩で30万~70万円、平均約50万円程かかると言われています。 さらに医療費に加え出産に向けて必要となるマタニティ用品やベビー用品を合わせると出産前後1年間でかかる費用は総額で約50万円~100万円程もかかると言われています。 金額を聞いてびっくりされると思いますが、実はきちんと公的制度を知り手続きをすれば「もらえるお金・戻るお金」は沢山あります。 全ての制度を利用すると最低でも専業主婦のママは約52万円、職場復帰予定のママ(平均月収が20万円)なら、なんと!約216万円分も支援を受けることができます。 これらの制度を上手に賢く使って頂いたうえでさらに、各地方自治体や企業が独自に行っている支援についてもご紹介させて頂きます。自治体によってはかなりお得な支援もありますので、知っていると得をする!そんな情報をあわせてご紹介させて頂きます。 そして、一番大切なことは、お金が「もらえる・戻る」ためにはどれも必ず自ら申請する必要があります。ただ待っているだけではお金をもらうことはできません。必ず申請方法まで確認してもらえるものはもらいましょう。 妊娠したママだけではなく、将来ママ・パパになる予定の方にも必ず知って頂きたいマネー知識です。ぜひ最後までお付き合い下さい。 1. ママの働き方によって違う『もらえるお金・戻るお金』 妊娠・出産時に受けられる支援は沢山ありますが、実は全てのママが全ての支援を受けることができるわけではありません。 ママの働き方によって受けられる支援が異なるため、今回「職場復帰」「出産退職」「専業主婦」の3パターンにママをわけて、受けられる支援をそれぞれママ別に紹介していきます。 まず、妊娠・出産時にもらえるお金として「妊婦検診費の助成」「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」の4つの支援があります。 妊娠・出産時には約50万~100万円ほどかかると言われていますが、もらえる支援をしっかりと受けると実際ご自身で持ち出す金額をぐっと減らすことができます。 ご自身が受けられる支援の内容や手続き方法を把握して頂き、漏らすことなく「もらえるお金・戻るお金」を増やしましょう。 職場復帰ママ 雇用保険・健康保険に加入し、現在働いていて出産を気に一時的に仕事を休み産後に現在の職場で仕事を継続予定ママ 【勤務先の健康保険に産前産後変わらず加入】 出産退職ママ 雇用保険・健康保険に加入し、出産のタイミングで退職しようとしているママ 【退職後はパパの健康保険の被扶養者又は国民健康保険に加入】 専業主婦ママ 専業主婦や自営業、フリーランス、パート(保険加入なし)で勤務しているが、雇用保険・社会保険にもはいっていないママ 【パパが加入している健康保険の被扶養者か国民健康保険に加入】 【ママ別】妊娠・出産で「もらえるお金」一覧 職場復帰 出産退職 専業主婦 妊婦検診費の助成...