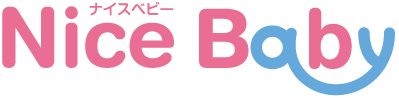お祝い・行事
おすすめはワンピース!お宮参りのママの服装選びで重視すべきポイント
お宮参りの赤ちゃんの服装が決まり、次は自分のを!と考えているママの中で着物?ワンピース?スーツ?となにを着たらよいのか悩むママもいるのではないでしょうか。 産後間もない時期でママの身体は万全ではありません。着物やスーツだとお腹周りなどが締め付けられ、体調を崩してしまう⋯ということも。そういった点から授乳しやすく、ゆったりとした身体に負担の少ないワンピースが1番おすすめです。 そこで今回は、ワンピースがなぜおすすめなのか理由と服装を選ぶときのポイントを詳しくご紹介します。 安心安全でおしゃれに!自分にあったワンピースを見つけましょう。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1.お宮参りにはワンピースがおすすめな理由 お宮参りでのママの服装の種類は主に「着物」「ワンピース」「スーツ」の3つです。 先輩ママ80人にお宮参りで着た服装はなにかアンケートを取りました。結果はワンピースが「72.1%」と過半数のママがワンピースを選んでいます。では、なぜワンピースが人気でおすすめなのか理由をご紹介します。 1-1.授乳しやすく、動きやすい 新生児~1ヵ月の赤ちゃんの授乳頻度は基本、3時間おきです。お宮参りのときやお食事会のときなど、授乳やおむつ替えをするタイミングが何度も訪れることでしょう。授乳口付きのワンピースだと授乳の度に服を脱がなくても、さっと授乳ができるので安心です。現代では、お宮参りや結婚式などでも利用できる授乳服とは分からないデザインのものが多く販売されています。授乳や動きやすさを考えるとワンピースが1番安心です! 1-2.産後の体に負担がかからない 出産は体に大きな負担がかかります。産後間もない時期に行うお宮参りは、ママにとって心身ともに万全な状態とはいえません。せっかくの機会だから着物を着たいと思うママもいるかと思いますが、無理は禁物です。お腹周りなど締め付けが少ないゆったりとしたワンピースをおすすめします。少しでも産後の体に負担をかけないことが大切です。 1-3.体型カバーに最適> 「産後で体型がまだ戻っていない⋯」「産後で骨盤や体の歪みが気になる⋯」と頭を悩ませているママも多い様子。そんな悩みを解決するのが体のラインが出すぎないワンピースです。種類も豊富で自分の気になるところをカバーできる、ぴったりの1着が見つかるはず!体型カバーにはワンピースが最適です。 1-4.他の行事でも利用できる ワンピースは、お宮参り後の色々な行事でも着まわせるデザインのものが多くあります。落ち着いたデザインのものであれば、結婚式、入園式などさまざまな行事で使用できて、小物を変えればまた違った雰囲気で着こなすこともできます。着物ほど汚れを気にすることもなく、お手入れも簡単で保管もしやすいのがよいですね。 2.服装を決めるときの3つのポイント! お宮参りの服装で悩んだときは、以下の3つのポイントを参考にしてみてくださいね。 2-1.主役である赤ちゃんより目立たない ママの服装の色やデザインは特に決まりや制限はありませんが、忘れてはいけないのが主役は「赤ちゃん」ということです。ママとパパだけが豪華で派手な服装になるのはNGです。主役である赤ちゃんが引き立つように、ママとパパは派手すぎない少し控え目なデザインを選びましょう。 先輩ママ80人に実際にお宮参りで着た服の色のアンケートを取りました。人気の色は【黒】と【ネイビー】という結果に! 2-2.一緒に行く人の雰囲気を合わせる ママとパパは着物で祖父母は普段着などだと全体のバランスが悪く、記念撮影の写真映えもイマイチに⋯ まずは、赤ちゃんが着る服装を決めてから大人の服装を決めるとバランスが取りやすいです。 お宮参りに行く家族と事前に話し合って服装の雰囲気を合わせましょう。 赤ちゃんが和装の場合 ・ワンピース ・着物 ・スーツ 赤ちゃんが洋装の場合...
【厳選】ママたちの満足度が高いお宮参り用着物レンタルショップ3選
お宮参りの際に着せてあげる着物(祝い着、産着)。もう決められていますか?一生に一度のお祝い事ですので、納得のいく着物を赤ちゃんに着せてあげたいですよね。 そうはいってもお宮参りの着物はその用途から他の着物と違い、何度も着るものではないため、購入するのはためらってしまう方も多いはず。そんな時の心強い味方が着物レンタルです!! お手軽に着ることができるため最近人気の着物レンタルですが、お宮参り着物をレンタルする方法は大きく分けて3つ「着物レンタルサービス」「フォトスタジオ」「神社」です。 その中でも特に、柄や色を沢山の着物の中から選べる「楽しさ」、レンタル期間が長いため余裕をもったお宮参りができる「安心さ」から人気が高い「着物レンタルサービス」についてご説明させて頂きます。 この記事では一生に一度のお宮参りが楽しく過ごせ、家族の幸せな思い出として残るようなお手伝いができるように「着物レンタルサービス」の中でも「楽しさ」や「安心」で特にママたちの満足度の高い着物レンタルショップ3選とその理由をご紹介させて頂きます。 衣裳 レンタル一覧ページ 1. お宮参り着物をレンタルする方法 お宮参り着物をレンタルする方法は大きくわけて「着物レンタルサービス」「フォトスタジオ」「神社」の3つがあります。選ぶ方法によって受けられるサービスやレンタル料金が変わってきますので違いを知ったうえでご家族にあったレンタルを選びましょう。 1-1 着物レンタルサービス 一番多くのママに利用されているのがこの着物レンタルサービスです。 成人式や結婚式で1度は利用されたことがある方が多いのではないでしょうか。ネットや電話で手軽に注文をすることができ、選べる着物の色・柄が多いため、赤ちゃんのお名前にあった柄や色、生まれた季節によって着物を選ぶなんてこともでき、着せてあげたいぴったりの1着を見つけることができます。 また、他のレンタルサービスと比べレンタル期間が長いため余裕をもってお宮参りの日を迎えることができます。「楽しく」着物選びをしたいママや「安心」して余裕をもったお宮参りをしたいママにおすすめです。レンタル料金は3,520円~28,000円と幅広いためご家族の予算にあった着物を選ぶことができます。 メリット ・誰でも申込ができる ・日程が自由に決められる ・選べる着物の種類が多い ・レンタル期間は平均3泊4日と比較的長い ・料金の幅が広く、自分の予算に応じて選ぶことができる ・自宅に届き、自宅から返却で便利(来店受取OKなお店も) ・クリーニングなどアフターケアが不要で、返却するだけでOK! ・保管しておく必要がないので、収納場所もメンテナンスも不要 ・生地は化繊(アクリルやポリエステルの化学繊維)や正絹から選べる ・男の子用着物は家紋を入れることができるお店もあり デメリット ・希望した柄が被っている場合利用できない ・赤ちゃんの体調不良などの場合でも日程がずらせない場合もあり ・着付けは自分で行う 1-2 フォトスタジオ...
お宮参りは午前中がおすすめ!パターン別のスケジュールを時間で比較
はじめてお宮参りに行こうと計画を立てているママパパ。 「どのくらい時間がかかるの?」「午前中に行くべき?午後に行くべき?」と、時間についてたくさんの疑問が出てくるかと思います。 実際、お宮参り自体の所要時間は、参拝のみなら30分、ご祈祷する場合は1時間、とそれほど時間はかかりません。 しかし、お宮参りと言えば参拝だけでは終わらないことは多いので、その後記念撮影やお食事会などを含めると、一日がかりになることも珍しくありません。参拝の後に何をするかにより、所要時間が大きく変わってきます。 こちらでは、おすすめの時間帯やスケジュールを立てる際の注意点など先輩ママが実際に行ったタイムスケジュールと一緒にご紹介します。 ご家族にあった一日の計画づくりに、この記事がお役立ていただけたら嬉しく思います。どうぞ最後までお付き合いください。 1. お宮参りの所要時間 お宮参りのスケジュールを立てるにあたり、まずは神社での参拝時間について解説していきます。 お宮参りの所要時間は、ご祈祷するかしないかによって大きく異なります。ご祈祷の予約の要不要も、神社によって異なりますので、参拝先が決まったら必ず問い合わせをしましょう。 1-1. 参拝のみなら30分 祈祷してもらうのが習わしではありますが、必ずしもご祈祷をしなければいけないということはありません。赤ちゃんの誕生を祝い、これからの健やかな成長を祈願することがお宮参りですので、赤ちゃんの体調や家庭事情によっては、家族で参拝のみでも問題はありません。 1-2. ご祈祷するなら1時間 ご祈祷の所要時間は、15分~20分が一般的です。受付やお土産をもらう時間も合わせ1時間ほど見ておくとよいでしょう。 受付時間は神社によって異なりますが、午前9時~午後4時までの場所が多いようです。ご祈祷する15分前までには受付を済ませておくようにしましょう。 予約不要や当日予約OKの神社もありますが、週末や連休などは待ち時間が長くなることも想定しましょう。神社のHPや電話で確認し、事前に予約をしておくとスムーズです。 2. お宮参りの時間帯は午前中がおすすめ お宮参りは午前中に行く?午後に行く?と悩んでいる方もいるかと思います。 お宮参り後のお食事会・写真撮影など他のスケジュールも立てやすい点などから午前中がおすすめです。午前中にお宮参りに行くメリットが、他にもたくさんありますので解説します。 2-1. 清々しい気持ちでお参りできる 午前中はお宮参りや参拝で神社に訪れる方が多く、混みやすいというのは事実です。しかし、午前中に行うと朝の清々しい空気とあたたかい太陽の光を強く感じることができます。基本、赤ちゃんは早起きです。さわやかに目覚め、ぐずらないうちにお宮参りを行うことをおすすめします。赤ちゃんがご機嫌だと家族みんなもHAPPYです。 2-2. 午後はゆっくり休めるので、赤ちゃんもママも安心 小さな赤ちゃんを連れての外出は、できるだけ早く帰宅するのが安心です。 午前中にお宮参りを行えば、時間に余裕ができ、午後の時間帯は有効的使えますね。お宮参り後の食事会や家でゆっくり家族団らんなど、赤ちゃんとママの体に負担なく一日を過ごすことができます。 2-3. トラブルがあった場合も対応しやすい 1日の時間に余裕があるとトラブルがあった場合でも対応しやすくなります。 赤ちゃんの様子や神社の混み具合によって、なかなか予定通りに進まない⋯なんてこともあります。当日にトラブルがあった場合でも午前中にお宮参りを予定しておくことによって、午後に変更するなど臨機応変に対応できるため、気持ちにも余裕ができます。 3. 赤ちゃんの負担を減らす4つの方法 赤ちゃんにとってはじめての長時間のお出かけが「お宮参り」になるご家庭も多いことと思います。まだ産まれて間もない時期に長時間外出させるのは、赤ちゃんにとって負担では?と不安に思っている方は多いのではないでしょうか。 そこで今回は、赤ちゃんとママ、そして家族の負担を減らす4つの方法をご紹介します! 3-1. 神社が最も混む、大安の土日祝日は避けましょう...
簡単・綺麗に着られるお宮参り着物の着せ方と畳み方を解説【動画付】
日本の伝統行事であるお宮参り。習わしにしたがって赤ちゃんに着物を着せてあげたい!と思っているママが多いかと思いますが、着物の着せ方に悩んでいませんか? 一般的な着物と違ってお宮参りの着物(祝い着、産着)は簡単に着付けができます。ポイントさえ押さえれば誰でも簡単に着付けできますので安心してください。 自分一人で「簡単に」「綺麗に」着付けができるようになるために、こちらの記事では、綺麗に着れる4つのポイントを紹介するとともに、着た後の保管方法やたたみ方についても解説していきます。 ご家族で赤ちゃんに着せてあげるとより一層お祝いの気持ちが込められると思いますので、チャレンジしてください。 一生に一度のセレモニーイベントが楽しく過ごせ、家族の素敵な思い出として残るように丁寧に説明していきますので、是非最後まで読んでくださいね。 衣裳 レンタル一覧ページ 1 お宮参り着物の着せ方 1-1. 着物の着せ方をイラストと動画でわかりやすく解説 1-2. お宮参り前日に準備しておくと安心!綺麗に着せる4つのポイント お宮参り当日はママや赤ちゃんのお出かけ準備で何かと忙しい一日になります。そのため当日慌ててお宮参り着物の準備をすると忘れ物をしたり大切な着物にシワができたりといったトラブルが発生する可能性が高くなります。 ここでは前日に済ませて置きたいポイントを紹介します。前日にしっかりと準備を整えることで、当日は慌てることなくスムーズに着付けが行えます。 1-2-1. 着物を半日ほどハンガーにかけましょう お宮参りをする前日に暗い室内で着物を半日ほど着物ハンガーにかけておくとシワが取れ当日綺麗に着ることができます。 お宮参り着物の代表的な生地である正絹(しょうけん)は直射日光だけ でなく蛍光灯の明かりでも生地を傷め、色あせや変色する場合がありますので必ずカーテンを閉め、電気を消した暗い室内で行います。 また、長時間干しっぱなしにしてしまうと形が崩れてしまったり、ホコリがついたりするので必ず長くとも半日を目安にかけましょう。 1-2-2. 着物紐と襦袢紐の袖通しは事前にしておきましょう 綺麗な床や机の上で行った方が紐を通しやすいため「着せ方5の手順」は、 上記1-2-1の作業(着物をハンガー にかけシワを伸ばす)後に行い、当日は神社に着いてすぐに赤ちゃんに着せてあげられるようにしましょう。 1-2-3. 事前に練習をしましょう お宮参り当日は外で赤ちゃんに着せることになりますので事前に自宅で練習をしておくと安心です。 着せ方はそんなに難しくないため、1~2回程全身が映る鏡の前で練習をしておけば大丈夫です。慌てることがないように必ず練習を行い当日は楽しいお宮参りの日を迎えましょう。 1-2-4. 持ち運びできるように綺麗に畳んでおきましょう 神社まで持ち運びやすいように前日にシワにならないように綺麗に畳んでおき明日に備えましょう。*畳み方は4−3をご確認下さい。 2. 赤ちゃんに着物を着せるタイミングはご祈祷直前がおすすめ 赤ちゃんに着物を着せるタイミングに正式な決まりはありませんが、羽織るだけとはいえ意外と暑く赤ちゃんにとって着心地のいいものではありません。 赤ちゃんのよだれ・吐き戻しで着物を汚してしまうことや、赤ちゃんの体重+着物の重さで抱っこする人は想像以上に疲れ両手の動きが制限されるため、特に車の乗り降りの際に着物を踏んでしまい転倒する危険性もあるためなるべく着用時間を短くしましょう。 ベビードレスや普段着等でご自宅を出発し、神社に到着後、手水舎(てみずしゃ)で軽くお清めをしてからご祈祷前に着せてあげると着用時間が短くできます。...
お宮参り 女の子の着物選びのポイントを知って選りすぐりの一枚を!
お宮参りの着物選び、普段着ることのない着物を選ぶのは、とても難しいですよね。数あるデザインから一枚を選ぶとなると、何から決めたらいいのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。お宮参りの衣装は、デザインだけでなく素材や装飾の違い、絵柄に意味もあり、実はとても奥がとても深いものなんです。 そこで今回はお宮参りの着物選びで知っておきたい3つのポイントとともに、着物の準備方法、七五三の祝い着への仕立て直しについても合わせてご紹介します。お宮参り衣装の基本を知って、着物選びをもっともっと楽しみましょう! 衣装(和装・女児) レンタルページ 1. お宮参り衣装 女の子の着物の選び方 知っておきたい3つのポイント 色鮮やかで美しい女の子のお宮参り衣装。ハレの日にふさわしい華やかなデザインを楽しめるのは女の子ならではの醍醐味ですね。ここでは女の子の衣装の代表的なデザイン、着物に施されている絵柄の意味、着物の生地や加工についてを着物選びの3つのポイントとしてご紹介します。 1-1. 選び方のポイント1:素材で選ぶ?デザインで選ぶ?ナイスベビーラボおすすめの女の子の着物 女の子の着物で多く人気も高いのが赤の着物。ピンクやオレンジ、白や黒など様々なカラーがありますが、やはり一番の人気は赤です。男の子の着物は真ん中に主役の絵柄がデザインされているのに対して、女の子は細やかな絵柄が全体的に散りばめられているデザインが多く見られます。 これまでは伝統的な絵柄が多いのは正絹の着物が主流でしたが、近年ではポップで現代的なデザインの化繊の着物も人気があります。ここでは、正絹、化繊それぞれのおすすめデザインを紹介します。 1-1-1. 伝統的なデザインが魅力!女の子におすすめの正絹の着物12選 正絹(しょうけん)とは絹100%の着物で、特別な日には是非選んで頂きたい着物です。鞠や御所車、熨斗などの昔からお祝いごとに用いられた古典的な絵柄が描かれる伝統的なデザインが魅力です。ここでは、ナイスベビーラボがおすすめする正絹の着物12選を紹介します。デザインや雰囲気の違いなど参考にしてくださいね。 本絞り加工が美しい、しっかりとした重厚感のある生地が特徴。本物志向の方におすすめの着物です。 背中の真ん中に本刺繍で描かれた、大きく美しい牡丹の花が存在感を放ちます。 桜の花びらが舞い散る中にたくさんの花々が咲き誇る、春にぴったりの着物。地紋の花柄がさらに可愛らしさを引き立てます。 童の遊ぶ絵柄が印象的な着物。近年の着物では見つからない貴重なデザインです。 初着にはめずらしい黒の着物。美しい絵柄が際立つ豪華で大人っぽいデザインが魅力です。 贅沢なまでにほどこされた金彩の絵柄が美しい着物。ピンクと赤、両方のカラーを叶えます。 たくさんの蝶が舞う優美な着物。シックで大人っぽいデザインが魅力的です。個性的な着物をお探しの方におすすめです。 優しいピンク色の地に可愛い手毬と四季折々の花々が美しい着物。初着ならではのキュートすぎるデザインです。 背中に咲く大輪の花々は、絵付け師の手描きによるもの。細やかな絵は他に類を見ない美しさです。 細やかに金彩で描かれた花々が、まるで花火のような美しさ。その中を舞う熨斗が輝きを放つ幻想的なデザインが印象的な着物です。 鮮やかなオレンジ色が目を引く着物です。大きく羽ばたく鶴が何羽も描かれる艶やかで個性的なデザインです。(夏用着物) 赤に近い濃いピンク色の地に所々に使われる紫色がとても美しい着物。女の子には珍しい花の飾り紋も目を引きます。(夏用着物) 女の子用 正絹の着物をもっとみる 1-1-2. ポップでキュートな着物!女の子におすすめの化繊の着物6選 鮮やかな色彩とポップなデザインで人気なのが化繊の着物。正絹では表現できな化繊ならでは発色も特長で、古典的な絵柄は継承しつつ現代的なデザインへと進化しています。お手入れのしやすさとお手軽な価格も魅力のひとつです。ここでは、ナイスベビーラボがおすすめする化繊の着物6選を紹介します。...
【お宮参り男の子】着物選びで知っておきたい柄の種類や家紋の入れ方
お宮参りの着物(産着)選び、普段着ることのない着物を選ぶのは、とても難しいですよね。数あるデザインから一枚を選ぶとなると、何から決めたらいいのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。お宮参りの衣装は、デザインだけでなく素材や装飾の違い、絵柄に意味もあり、実はとても奥がとても深いものなんです。 そこで今回はお宮参りの着物選びで知っておきたい3つのポイントとともに、男の子の着物で重要となる家紋についてのアレコレ、着物の準備方法を合わせてご紹介します。お宮参り衣装の基本を知って、着物選びをもっともっと楽しみましょう! 衣装(和装・男児) レンタルページ 1. お宮参り衣装 男の子の着物の選び方 知っておきたい3つポイント 力強いデザインが印象的な男の子のお宮参り衣装。背中には、鷹や兜などの絵柄が大きく描かれています。カラーは黒や紺色をベースに、華やかでおめでたい金色なども多く使われ見ごたえのあるデザインばかりです。ここでは男の子の衣装の代表的なデザイン、着物に施されている絵柄の意味、着物の生地や加工についてを着物選びの3つのポイントとしてご紹介します。 1-1. 選び方のポイント1:伝統的なデザインが人気!男の子におすすめの着物12選 男の子の着物に多く施されているのが「鷹」と「兜」。どちらも勇ましく迫力のある男らしい絵柄です。地色に用いられるのは黒、濃紺がもっとも多く、他にも緑やグレー、青や白など明るいカラーもありますが、やはり一番の人気は黒、続いて濃紺、ベーシックで伝統的なデザインを好まれる方が多いようです。同じ地色でも絵柄や施されるカラーによっても雰囲気が大きく変わってきますので、色々と見てみましょう。まずは、ナイスベビーラボおすすめの着物12選を紹介しますので、デザインや雰囲気の違いなど参考にしてくださいね。 深く濃く美しい黒の地が特徴の着物。本刺繍で描かれた鷹がひときわ際立つ品格漂うデザインです。 兜に乗る龍は贅沢な刺繍で描かれています。松の木にはとまる珍しい白の鷹が目を引きます。 男の子の着物にはあまり見ない花の絵柄の着物。男らしさと華やかさを兼ね備えたデザインが人気です。 絞り加工が施された着物。緑をベースとした絶妙なカラーと個性的なデザインが印象的です。 縁起のよい大きな宝船。堂々とした太い幹の松木が雄大さを感じさせます。地紋の生地と渋い色使いの重厚感あるデザインです。 中央に大きく描かれた富士山に金雲がかかる美しい自然の描写が特徴の着物です。 深く美しい濃紺の地に舞う金色の 絵巻が華やかさを演出。ダイナミックで男の子らしいデザインの着物です。 滅多にない宝船と鷹の組み合わせの貴重なデザイン。色数を抑え贅沢に金彩を施した絵柄と個性的な地色が、絶妙なバランスを生み出しています。 富士山、梅の花、松など自然の絵柄がメインの兜を大きく引き立てています。雅な美しさが目を引くデザインです。 石持部分が白丸ではなく松竹梅で縁取られた縁起のよいデザイン。家紋にこだわる方には是非おすすめした着物です。鷹と松だけのシンプルで迫力ある絵柄が印象的です。 細やかに描かれた松の葉にはひとつひとつ金彩が施され、その美しさが目を引きます。花の地紋の生地との相性も絶妙な、繊細で趣のある着物です。 重厚感のある総疋田織りの生地を用いた着物。独特な風合いに華やかなデザインが加わり、優しく美しい印象を与えます。 男の用 お宮参りの着物をもっとみる 1-2. 選び方のポイント2:絵柄の意味を知ると着物選びはもっと楽しくなる 男の子の着物は主役の絵柄として鷹と兜が描かれているものが多く見られます。メインの柄の周りにも複数の絵柄や模様がデザインされており、見比べてみると同じような絵柄が使われていることに気がつきます。なぜこれらの絵柄が多く使われいるのか、その意味や由来について少し掘り下げていきたいと思います。絵柄の意味を知って、デザインだけではない違った角度からの着物を選びをしてみてはいかがでしょうか。 [鷹]鷹は男の子の着物絵柄として兜と並び一番多い絵柄。その鋭い眼光は、遠くはるか先まで見渡すことから「物の本質を見抜く力・先を見通す目」として、また鋭い爪は「運や幸運をしっかりと掴む」という意味で、出世や大成の願いが込められています。...
お宮参りの食事会を無理なく開催するためのケース別ポイント解説!
お宮参りの後の食事会は、必ず行わなければならないの?と不安に思っているママも多いのではないでしょうか。体調の優れないことが多い時期ではありますので、必ずしも食事会を開かなければならないということではありません。しかし、離れて暮らしている両親と会う機会はあまり多くはないと思います。 ここでは、ママと赤ちゃんに負担にならないような食事プランと、どんな食事が好まれるのか、お支払いはだれがするのかなどの疑問にお答えします。素敵な記念日になるよう、参考にしていただければ幸いです。 1. お宮参りでお食事会をすべき理由 お宮参りでお食事会をすべき理由は、ご家族の集まる機会に、赤ちゃんの顔を見ながら楽しく食事ができるとご家族にとって良い思い出になるからです。お宮参り後のご家族の休憩もかねて、お食事会を催しましょう。但し、ママと赤ちゃんの体調が良いという事が前提となります。初めての外出には気を遣うことも多く不安がたくさんですよね。ずっと室内で育児をしていたママと赤ちゃんの負担にならないよう、事前に準備して計画することが必要です。食事会は必ずしなければならないという決まりはないため、赤ちゃんやママの体調を第一に考慮しましょう。 食事会は昼食がおすすめ! 午前中にお宮参りを済ませた後に食事会を昼食にするのをおすすめします。まだ小さい赤ちゃんは寝ている時間が長いですが、授乳やオムツ替えなどのお世話、帰宅後のお風呂に入れる事を考えて、ママの負担にならないように時間調整をしましょう。 しかし、御祈祷の予約時間やご家族の都合によっては午後に食事会をする場合があります。出来るだけ時間をかけず、早めにお開きにできるよう周りのご家族にフォローしてもらいましょう。 2. 場所別お食事会の二つのパターン お宮参りを行う神社へご祈祷後、できれば神社近くの自宅や実家、個室のレストランでゆっくりと食事会をするご家庭が多いようです。食事会を行う場所によって、準備するものや段取りが変わります。それぞれのパターンとメリットやデメリットをご紹介しますので参考にしていただければ幸いです。 自宅や実家で食事 メリット 赤ちゃんとママの体調を優先しやすいこと。 自分達のペースで時間を気にしなくて良い。 周囲の目を気にせず、リラックスできる。 時間の融通が利くこと。 授乳、着替え、オムツ替えなどがしやすい。 外食よりも料金をやや抑えられる事。 料理好きのママは、パーティの用意も気分転換になる。 デメリット 部屋の掃除や席のセッティングが必要。 宅配の注文・食器の片づけなどある。 来客用のスリッパやコップ、食器などの用意が必要。 外食の場合 メリット 準備、配膳、片づけなどの手間がかからない。 育児に忙しいママの気分転換にもなる。 記念日ならではの特別感を味わえる。 スケジュールが組みやすい。 デメリット 可能な限り個室を予約。できれば座敷席を。...
平均総額5万~8万円!お宮参りに必要なお金4つとマナーを徹底解説
赤ちゃんが生まれてはじめての大きなイベント「お宮参り」。そんな大切なイベントに向けて準備を進めていく中で、「初穂料はいくら払うの?」「誰が払うの?」「そもそも何にお金がかかるの?」とお金について不安や疑問を持った方も多いのではないでしょうか。お宮参りには様々なマナーがありますが、お金のことになると、なかなか家族や友人に聞けないこともあるかと思います。そこで今回は、お宮参りに関わるお金事情を詳しくご紹介します。家庭の負担にならない方法を見つけることによって、赤ちゃんとママ、そして家族みんなが笑顔で素敵なお宮参りになること間違いなし! 1.お宮参りに必要なお金の相場 お宮参りに必要なお金は、参列者の人数や地域によって様々ですが下記の金額を目安にしてみてください。 平均総額 5万円~8万円 初穂料 5,000円 お祝い着 1万円~ 記念写真撮影 2万円~3万円 食事会費 3,000円 (1人あたり) では、それぞれを詳しく見ていきましょう。 1-1. 初穂料・玉串料:5,000円 神社で祈祷したときには、お礼として神様へ初穂料(玉串料)を納めます。一般的な相場は「5,000円」となり、次に多いのが「1万円」です。この金額の違いは、料金に応じてお守りやお札、お菓子などお土産の量や質の違いがあります。神社によっては指定している場合もありますので、予約時に確認することが大切です。中には「お気持ちで納めください」と個人にお任せするところもありますが、硬貨は使用せずお札を包むのがマナーです。わからない場合は、5,000円を目安にするとよいでしょう。 1-2. お祝い着:1万円~ お宮参りの赤ちゃんの衣装は、大きく分けて「和装」と「洋装」があり、それによって費用も異なります。一般的な着物(和装)であれば、3万円~5万円ほどで購入することができますが、グレードによっては10万円以上するものもあります。洋装の場合は、1万円~3万円ほど。どちらも購入するとなれば、それなりの費用がかかります。誕生してから1年の間はお祝い行事がたくさんあるため、この出費は大きいですよね。現代ではレンタルする方も多く、負担にならない範囲で賢く利用するのもよいでしょう。 1-3. 記念写真撮影:2万円~3万円 A.写真館やスタジオ撮影:2万円~3万円 記念撮影と言ったらまず、この撮影方法を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?多くの人が利用している方法になりますが、料金はどのオプションをつけるかによって大きく異なります。大手スタジオでの撮影料は3,000円となりますが、そこにアルバムや小物などオプションを追加すると3万円前後になるケースが多いです。商品という形で写真を残したいと考えている方におすすめです。 B.出張撮影:2万円~3万円 最近人気を集めており、撮影方法の中で1番おすすめなのが出張撮影!カメラマンにお宮参りに同行してもらい、赤ちゃんの晴れ姿、家族写真の撮影をしてもらえます。料金は、カメラマンによって8,000円~3万円と幅広く、土日と平日で変わる場合もあります。料金なども検討の上、納得できる人を見つけましょう。自然光の中で、お宮参りの様子も綺麗に写真に残すことができ、赤ちゃんが大人になったときに思い出話で盛り上がることでしょう。 C.自分たちで撮影:0円~1万円 プロのカメラマンに撮ってもらうと、仕上がりも綺麗でプロならではの写真ができることでしょう。しかし、料金は決して安くはありません。その点、自分たちでの撮影は自分でセッティングできるため、予算を抑えることができます。赤ちゃんの機嫌を見ながらでき、赤ちゃんやママの負担も少なくすることができるでしょう。予算を抑えたい方やオリジナリティーあふれる写真を撮りたい方におすすめです。 1-4. お食事代:3,000円(1人あたり) お宮参りでは、参拝後に食事会を開く方は多いと思います。食事会はレストランでも自宅でも構いません。ただし、主役である赤ちゃんが、まだ食事ができる時期ではないので、一人あたり5,000円以内に抑えるのが一般的です。 A.外食する場合:【昼食】2,000円~3,000円/人 【夕食】3,000円~5,000円/人 料亭や懐石などのコース料理の場合は5,000円ほどになります。子育てをしながら、家の片付けやご飯を作るのは本当に大変ですよね。外食ではそのような準備の必要がないため、安心ですね。 B.自宅でする場合:2,000円~3,000円/人 赤ちゃんが泣いてしまったらどうしよう⋯授乳のタイミングは?など周りの方に気を使わず、リラックスして食事を楽しむことができます。外食よりも料金を抑えられる傾向にあり、人数が多い場合などにおすすめです。...
お宮参りと100日祝い一緒に行うのはOK?それぞれの違いについて解説
家族が誕生しこれから赤ちゃんと過ごす素敵なイベントが沢山あります。その中でも誕生後、初めの伝統的なセレモニーイベントであるお宮参り。日本人としてきちんとした伝統行事も行なってあげたいと思っているママとパパが多いと思います。しかし、やりたいけどどうしたらいいの?お宮参りと近いお日にちのお祝い事として百日祝いもあるけどどう違うの?と悩んでいませんか。 この記事を読んで頂ければ5分で違いがわかり、違いを知った上でお宮参りや百日祝いをどのように行っていくかイメージが湧きます。お宮参りと百日祝いの違いや込められた意味、一緒に行う場合のポイントをお伝えします。 一生に一度のセレモニーイベントが楽しく過ごせ、家族の幸せな思い出として残るようなお手伝いができるようにご説明させて頂きます。 1 「お宮参り」と「百日祝い」の違い お宮参りは「誕生報告と健やかな成長」、百日祝いでは「一生食べ物に困らないように」と込められた意味が違います。どちらも生まれてきた赤ちゃんの成長を願う日本の伝統行事ですが、それぞれの違いを深く知ることで、より心の込もった素敵なイベントになります。ぜひ参考になさって下さい。 お宮参り 百日祝い(お食い初め) 味込められた意味 誕生報告、健やかな成長 一生食べ物に困らないように 時期 生後30日前後 生後100日前後 内容 赤ちゃんを父方の祖母が抱き、その上に祝い着を被せて神社に参拝します。 祝い膳を用意し、親族の年長者が赤ちゃんにごちそうを食べさせるふりをさせます。 場所 神社 自宅・レストラン 写真撮影 神社・自宅・フォトスタジオ 自宅・レストラン・フォトスタジオ 服装(赤ちゃん) 祝い着(着物) 特に決まりはないです 1-1 お宮参りとは「神様に赤ちゃんの誕生を報告し健やかな成長」を願うための行事 生後一カ月頃に赤ちゃんの誕生を住む土地の氏神様に報告するために神社へ参拝します。参拝時、正式には父方の祖母が赤ちゃんを抱いて参拝します。その理由は昔、出産は穢れたものと考えられ産後1ヶ月のママは穢れを祓う忌明けが終わっていないため、ママの代わりに乳母や親族の女性が抱っこしていました。しかし現代では穢れについて厳しく言われていないため、ママが抱いて参拝しても問題ありません。特に夫婦だけでの参拝の場合はママが赤ちゃんを抱く方が自然です。 1-1-1 赤ちゃんには特別な祝い着(着物)を ママは負担の少ない服装で無理をせず お宮参りは赤ちゃんにとって一生に一度の行事ですので、伝統的な形をのぞみ祝い着(着物)を選ばれる方が多いようです。参拝や記念撮影の直前に祝い着(着物)を着せてあげると赤ちゃんにとって負担が少なくスムーズにお参りをすることができます。...
時期をずらすのはOK!「お宮参りはいつ行くべき?」に対する私の回答
お宮参りはいつ行うものでしょう? お宮参りは、その土地の守り神である産土神(うぶすながみ)に赤ちゃんの誕生を報告し健やかな成長を願い、生後1カ月で行う伝統行事です。地域によって3日程度前後していますが、男の子は生後31日目、女の子は生後32日目に神社やお寺に参拝するのが一般的です。ここでは、具体的にいつお宮参りに行ったらいいか、どのように日程を決めるのがベストかがわかります。赤ちゃんを囲んで家族皆さんで素敵な記念日を過ごせるといいですね。 1. お宮参り時期とは、赤ちゃんとママの体調を最優先してください! 現代では、小さい赤ちゃんと産後間もないママの体調を気遣って正式な時期より後にずらしたり、天候によって日程を変更したり、柔軟な対応をしているご家庭が多くなっています。しきたり通りに行うことより、みんなが赤ちゃんと一緒にお祝いできることをメインにお宮参りの日程を立てましょう。あまり神経質にならずにみんなが気持ちよく参加できる時期を選ぶようにしましょう。また、ご両親の仕事の都合や遠方で集まるのが難しい、介護があって遠出できないなどの理由で、赤ちゃんとママとパパだけでお参りするケースも少なくありません。 1-1. お宮参りは時期をずらしてOK ! お宮参りの時期については、しきたりを厳守すべきものというわけではありません。真夏・真冬に生まれた赤ちゃんは、なおのこと気候の穏やかな日にお参りしましょう。お正月の初詣の時期などの混雑はさけ、赤ちゃんとママの体調や家族の都合で生後半年ごろまでを目安に、時期をずらしても構いません。 1-1-1. お宮参りは、赤ちゃんとの外出に慣れたころに行ってOK! ママも赤ちゃんとはじめての外出はドキドキですよね?赤ちゃんの持ち物はどうしたら良いかや授乳間隔が短いなどの不安もあります。ママも久しぶりの外出でしょうし、和服を着たりおしゃれする時間があるのかなど、いろいろと不安もあると思います。無理をせず、外出にも少し慣れて来たころに参拝に出かけるということでまったく問題ありません。 1-1-2. お宮参りの記念写真のタイミングも別でもOK! お宮参り写真というと、神社にお宮参りをした後、スタジオへ行って記念撮影される場合が一般的のようです。しかし、お宮参りの神社に出向かず、スタジオ撮影などで生後1カ月の記念に写真だけでも残したいと記念写真だけを撮られる方もおられます。生後間もない赤ちゃんと一緒の初めてのお出かけを不安に思い、神社やお寺への参拝を撮影とは別日にセッティングするというご家庭もあるようです。 1-1-3. 筆者の体験談 筆者の長女・次女のお宮参りは、スタジオでの記念撮影と別日に行いました。里帰り出産で両親や実姉に甘えた生活をしていたため、出産後1カ月は経っても産後の体重が妊娠前のプラス15キロと減らず、だいぶ別人と思われる写真が記念に残っています。(笑)子供のお宮参り写真は、産院でもらったスタジオ撮影チケット無料のサービスがあり、お得に撮影できました! 最近では、出張撮影や一軒家スタジオ、おなじみの大手チェーンスタジオなど多種多様です。すぐに大きくなってしまう赤ちゃん期をたくさんの写真で記念に残してあげられたら、お子様が大きくなった時とても喜ばれることに違いありませんね。 1-2. 百日祝いと一緒にお宮参りするのもOK! 時期を検討して、百日祝い(お食い初め)のタイミングと合わせてお宮参りをされるご家庭もあります。生後3カ月が過ぎると、赤ちゃんの首もすわり表情も豊かに笑顔を振りまいてくれるようになり、なお一層可愛さが増してくるころです。 遠方にご家族がいらっしゃってなかなか会いに行けない場合、予定を合わせてお披露目を兼ね、お宮参り&百日祝い(お食い初め)の食事会を開くのもいいですね。ママも赤ちゃんとのお出かけにも慣れてきていますし、いい写真もたくさん残せてとても良いお祝いになることでしょう。お宮参りの生後1カ月の出先で撮った写真はほとんど、小さく頭だけ又は顔半分写った赤ちゃんとご家族の写真ですから。(笑) 1-3. 「六曜」の大安の日、仏滅の日は気にしなくて大丈夫! 六曜は、諸説ありますが、中国から来たかけ事などの占いから始まったという説もあります。六曜とお宮参りは異なる成り立ちでできていますし、六曜の吉凶と神社へのお参りや厄払いと言ったお祓い・御祈祷に関しては、全く関係ありません。お宮参りが仏滅になってしまった場合でも、基本的には気にしなくて大丈夫です。 また、人気のある有名な神社では、婚礼などの行事予定が入っている場合もありますし、大安などは、かえって混雑が予想されます。赤ちゃん連れですし、おむつ替えや授乳間隔も短いころですので、空いている日にゆっくりお参りをするというのもありかもしれません。ご家族の中に六曜にこだわる方がいらっしゃる場合は、お宮参りの日程を決める際の参考程度に考えましょう。 そもそもの「六曜」の話 六曜(ろくよう)とは、暦のひとつ。1週間を先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類で表したものです。足利時代に中国から日本に伝えられましたが、広く行われるようになったのは幕末以降のことです。参考までに、六曜の吉凶についてご紹介します。 基準日 意味...
お宮参り・記念撮影・食事会までの基本的な流れと段取りのポイント
赤ちゃんが生まれて数週間、そろそろお宮参りについて決めないと!と考え出すころですね。とはいっても、何から準備をしたらいいのか、特に初めての場合はわからないことだらけ。そんな時はまずはお宮参り全体の流れを確認してみましょう。 ここでは、神社での参拝方法、その後の記念撮影、食事会までをお宮参りの一日として、それぞれの内容と流れについて具体的なタイムスケジュール例と共に紹介します。一日の流れを確認して、ご自身に合うパターンを選びスケジュールを立てれば、必要なものや段取りも見えてきます。赤ちゃんが生まれて最初の伝統行事、無理なく楽しく、素敵な思い出をつくりましょう。 1. お宮参り当日の基本的な3つの流れはこれ! 一般的なお宮参りの一日に組み込まれる大きな要素としては、下記の3つがあげられます。 神社へご祈祷に行きましょう 記念写真を撮りましょう 食事会を開きましょう この3つを一日でこなす場合、お宮参りと撮影まで午前中に済ませて、昼食を兼ねた食事会にするパターンと、お宮参りを済ませた後、午後から撮影、食事会を夜に開く2パターンが考えられます。どちらのパターンを選ぶかは、この後の解説を読んでご家族の状況に合うスタイルを選んでくださいね。それでは、(1)お宮参り(2)記念撮影(3)食事会 それぞれについて、その内容と流れをみていきましょう。 1-1. 神社へご祈祷に行きましょう お宮参りは、その土地を守る氏神さまに赤ちゃんの誕生を報告、健やかな成長を願い参拝をする伝統行事です。神社で神主さまにお祓いをしていただき、初穂料を納めます。一般的に神社への午前中がよいとされています。お祓いをしていただく場合は、日取りと場所が決まったらまずは神社へ問い合わせをしましょう。ご祈祷の予約の要不要は神社によって異なります。結婚式などすでに他の予定が入っていて希望の時間帯にご祈祷ができないこともありますので、必ず事前に確認をとるようにしましょう。 1-1-1. 自宅での出発準備:前日までにできるだけ準備を整えましょう 赤ちゃんの衣装の準備やママパパの着替え、ご両親が来たりなど当日の朝は忙しないもの。生後間もない赤ちゃんの外出には、何かと荷物も多くなりますので、可能なものは全て前日までに準備しておきましょう。 お宮参りの衣装が和装の場合、お参りの際に掛け方がわからない!とあたふたしてしまう事がよくあります。着物のかけ方は必ずご自宅で事前に練習しておきましょう。また、どのタイミングで誰が赤ちゃんを抱っこするのか、なども決めておくのも当日の流れをスムーズにするポイントです。 赤ちゃんにベビードレスを着せる場合、神社まで距離があるようなら到着してから着替えさせるのもOK!ミルクの吐き戻しなどでせっかくの衣装が汚れてしまっては台無しです。お着替えのタイミングも事前に考えておくことも大切です。 当日の朝は身支度を整えるだけ。前日までにできるだけの準備をしてスムーズに一日をスタートさせましょう! 1-1-2. 神社に到着したら:受付から参拝終了までの一般的な流れ (1)神社到着 <一礼してから鳥居をくぐりましょう。参道は真ん中を避けて端を歩きます。手水舎で手と口を清めます。 ▼ (2)ご祈祷受付 受付時に初穂料を渡し支払いを済ませます。予約時間の10分前には受付をしましょう。赤ちゃんの着替えやおむつ替え、授乳などがある場合は30分前など余裕を持って行くことをおすすめします。 ▼ (3)待合室へ 受付が終わると、待合室に通されるのでそちらでご祈祷の順番を待ちます。赤ちゃんの着替えやおむつ替え、授乳などはこの間に済ませましょう。 ▼ (4)本殿にてご祈祷 順番がきたら本殿へ向かい、ご祈祷の儀式を受けます。ご祈祷の時間は20~30分程度が一般的。混雑している場合は待ち時間を含めそれなりの時間を要す場合がありますので、だいたいの目安を事前に確認しておくとよいと思います。 ▼ (5)授与物の受け取り ご祈祷の後は、神社からお札やお守り、お食い初め漆器などの入った授与物が渡されます。ここに記載したものは一例で内容は神社により異なります。受け取りのタイミングも受付の際に支払いと引き換えで受け取る場合もあります。...