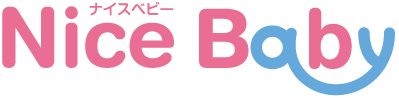ベビーベッド・寝具
育児が断然楽になった!移動式ベビーベッドは短期間でも使う価値あり
「ベビーベッドを使いたいけれど、置く場所どうしよう?置いたら邪魔になりそう…。」 「用意してもあまり使わなかったらコスパ悪いよね。」 ベビーベッドをこれから準備しようとしている方はこんな悩みに直面しているのではないでしょうか? 正直にお話をすると、筆者の私も1人目出産の時は同じことを考えていました。 「ベビーベッドって部屋に置いたら邪魔だし、短期間だったら我慢すれば何とかなる!」と思っていたのが事実です。 「あると便利だろうけど、なくてもなんとかなりそう。」そう考えたことが一番の決め手となり、ベビーベッドは使わずに育児を行うことにしました。 案の定、床でお世話は当たり前。 初めての育児で毎日必死な上、無理な体勢でのお世話を繰り返し、体への負担が知らず知らずたまっていたようです。 気付いた時にはすでに遅く、産後6ヵ月に人生初の『ぎっくり腰』を発症。散々な目にあいました。 あの時のことは、もうこりごり。とても後悔しています。 2人目からは考えを改めベビーベッドを使うことにし、大正解!! 身体への負担が軽減され、こんなにも違うのかと驚きました。 子供が増えることで、ますます体に負担がかかるのかと思いきやベビーベッドのおかげもあり、楽に育児をすることができました。もちろんぎっくり腰もなしです。 しかし『ベビーベッドを使うことで部屋が狭くなる』というのも事実。 そんな悩みを解消してくれるのが今回ご紹介する「移動式ベビーベッド」です! 私は、この「移動式ベビーベッド」を使って2人目、3人目と快適な育児を行うことができました。 赤ちゃんを安全な場所で寝かせてあげたい。 安心して育児をしたい。 ベビーベッドは使いたいけれど設置スペースが限られている。 自分の体に負担なく楽しく育児がしたい。 そんな方におすすめのベビーベッドです。 この記事を読み終わった後は、あなたにとって理想的なベビーベッドを選ぶことができるようになります。 これから始まる赤ちゃんとの生活がHAPPYになること間違いなしです! ぜひ参考にしていただければと思います。 1. 産後の育児が断然楽になる!コンパクトな移動式ベビーベッドをおすすめする3つの理由 ベビーベッドに寝るのは赤ちゃんだけれど、お世話をするのはママやパパ。 特にママは、出産という大きな仕事を終えて、体はヘトヘト。でも休む暇はありません。 少しでも育児が楽になれば、ママの体への負担は軽減します。 だからこそ、さまざまな種類がある中でコンパクトでなおかつ移動ができるタイプのベビーベッドをおすすめします。 第一章では、おすすめポイントを3つご紹介します。...
マットレスは必須!年間500台のベビーベッドを届けてわかったこと
これから生まれてくる赤ちゃんの為にベストな環境で寝かせてあげたい。 そのためには何を準備しなければならないのだろう? まずはじめに、頭に思い浮かぶものは寝具のベビーベッドとベビー布団ですよね。 ベビーベッドとベビー布団だけ用意すれば十分と考える方がほとんどだと思います。 でも、普段ママパパがベッドで寝る時は、快適に寝るためにマットレスを利用していますよね。 そう考えると快適な睡眠環境作るには「赤ちゃんにもマットレスは必要なのだろうか?」と疑問に感じませんか? お答えします。 ベビーベッドを使う際、マットレスは赤ちゃんにとって欠かせないアイテムです。 実は筆者の私は、以前までナイスベビーの配送スタッフとしてお客様宅にベビーベッドをお届けしていました。そのなかで実際に現場で見たものをお伝えします。 稀なケースではありますがレンタル品のベビーベッドや布団セットを引き取る際、ベビーベッドの床板の裏側や敷布団などにカビが付いて返却されることがありました。 おそらくその原因は、敷布団を長い間ベビーベッドに敷きっぱなしで使用されていたか、もしくは加湿器等で過度な湿度によりお部屋の環境が悪くなってカビが発生したものと思われます。そういうケースの方は、たいがいベビーベッドだけの利用でマットレスを利用しないお客様でした。 知らずにそうした悪い環境のもとで赤ちゃんを寝かせていた思うと少し怖いですよね。 そうならないためにも今回私は配送経験をもとに、赤ちゃんにとってベストな睡眠環境をつくる為に、マットレスの必要性を解説します。 この記事を読んでいただけた後、実際にマットレスの特性がよくわかり「赤ちゃんを寝かせる為にはやっぱり必要だね!」とママパパが判断していただければ幸いです。 1. ベビーベッドにマットレスが必要な理由 ベビーベッドを利用して赤ちゃんの睡眠環境作ろうと思う方の大半はベビー布団セットも準備します。ベビー布団セットがあれば敷布団も入っているしマットレスまでは必要ないでしょう…と思うママパパもいると思います。 実は、ベビー布団セットに入っている敷布団は薄くて使っているうちにヘタってしまい耐久性がなく、かつ通気性の悪いものがほとんどです。ここでは敷布団とは違うマットレスの特性を解説し、ベビーベッドにマットレスが必要だということをお伝えします。 1-1. 敷布団だけだと通気性が悪くカビ・ダニが発生する原因になってしまう! なぜ敷布団にカビやダニが発生してしまうの?と思いますよね。 その原因は、敷布団の通気性にあります。 主にベビー布団セットに入っている敷布団は、赤ちゃんの沈み込みを防ぐために硬めに作られています。 その敷布団の中の素材の多く固綿でできています。固綿の敷布団は通気性が悪いのです。 通気性が悪い敷布団だとカビ・ダニが発生してしまう! 一日の大半を寝て過ごす赤ちゃんは、寝ている間に大量の汗をかきます。一日の寝てる間におよそコップ2杯分(約400㎖)もの汗をかきます。その量は大人の約2倍にもなります。赤ちゃんがかいた汗は布団や敷布団にしみ込み、通気性の悪い敷布団だとなかなか乾きません。その状態で使い続けているとカビやダニが発生する条件を満たしてしまうのです。 “カビ・ダニの発生の条件は4つ” ① 湿気がある 赤ちゃんの汗等による湿気がこもる環境や加湿器による過度な湿度環境 ② 養分がある...
『子育て本音トーク vol. 1』使ってみた!ベビーベッド・布団・クーハン編
ナイスベビースタッフによる『子育て本音トーク』がスタート! 育児休業から復帰したスタッフを囲み、育休中に使ってもらった沢山のベビー用品について、根掘り葉掘り探ってしまおうという企画です。 第1弾は「ベビーベッド・ベビー布団・クーハン」について。こんな感じで使った、これは便利だった、いらないかも...など、いいも悪いも含めた本音トークをたっぷりと聞いていきたいと思います。 あゆなママ「ととママが育休から復帰しましたー!」 たばち「おかえりなさーい♪」 あゆなママ「ととママにはお休み中に相当の数のベビー用品を使ってもらいましたよね。これから数回に渡って体験談を聞かせてもらいたと思います!その前に、ととママの自己紹介をお願いできますか?」 ととママ「8歳、6歳の男の子、1歳の女の子の三児の母です。あと、犬と猫もいます。二階建て一軒家4LDKに家族5人とペットと暮らしてます。よろしくお願いしまーす!」 たばち「早速ですが、今回第1弾は、ベビーベッド・ベビー布団・クーハンについて、いろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。」 1. ミニサイズベビーベッド・簡易型ベビーベッドを使ってみた! リビングにベッドを置かないという選択肢はなかった たばち「使ってもらったのは、ミニサイズのベビーベッドと簡易型ベビーベッドでしたね。」 ととママ「上の子の時に使っていた標準サイズのベビーベッドがあるので、ミニサイズのベビーベッドを選びました。標準サイズは寝室に置くので、ミニサイズはリビング用として使いたくて。」 あゆなママ「リビングにもベッドを置こうと思ったのはなぜ?」 ととママ「上のお兄ちゃん2人の動きがすごいのと、ペットも飼ってるので、逆に置かない選択肢はなかったんですよね。実際、退院した日は、犬と猫が赤ちゃんに興味津々ですごい近づいてきたので、ベッドあってよかったーって思った。もし布団に寝かせてたら大変だったと思う。」 たばち「持ってる標準型をリビングに置こうとは思わなかったんですか?」 ととママ「ロータイプだし大きいしリビングには無理だなーと。さすがに大きすぎ(笑)」 赤ちゃんがベッドから落ちる事件が! たばち「どのくらいの期間使いましたか?」 ととママ「実は6ヵ月頃に赤ちゃんがベッドから落ちるという事件がおきて。私が目を離した時なので何で落ちたのかはわからないのだけど>< それで慌てて床板の高さを下げたのだけど、そしたらお世話しにくくなっちゃって。」 あゆなママ「ベビーベッドは6ヵ月で卒業?」 ととママ「そうなりましたね~。あまり寝ない子だってこともあって。よく寝る子だったら1歳とかサイズが大丈夫な限り使えるのだけど。」 ハイタイプはとにかくお世話しやすい! たばち「使い勝手はどうでした?」 ととママ「すごく良かった!ハイタイプだからとにかくお世話がラク!扉が2ヶ所開くのもすごく便利!ミニサイズでも荷物置きは十分なスペースがあるから、赤ちゃんの荷物は全部置いてました。」 あゆなママ「産後ママで腰痛の悩みを持つ人って多いから、おむつ替えの多い新生児期はやっぱりハイタイプがいいよね。」 2. 簡易型ベビーベッド「ソイネ」を使ってみた! 軽くて1階から2階へも簡単に移動できる! あゆなママ「簡易型ベビーベッドはソイネはどうでした?」 ととママ「本当は寝室の添い寝で使うつもりで借りたんだけど、結局ベッドの横に置いて使うことはあまりなかったな~」 たばち「どんな時に使ってました?具体的なシチュエーションを教えてください。」...
これで全て分かる!先輩ママも絶賛するクーハンの魅力とおすすめ5選
育児アイテムを揃えていく中で、よく目にするけど...、友達が使ってたけど...、あった方がいいのかな?と必要なのか不必要なのか悩むアイテムってありますよね。赤ちゃんを寝かせて運べるかごのようなもの、クーハン(クーファン)もその中の一つではないでしょうか。よく見るアイテムだけど、実際はどの程度便利なんだろう?使う機会って多いのかな?とちょっと想像しにくいかもしれませんね。 実際、クーハンは絶対に用意すべきアイテムではありません。そして、ちょっと控え目なアイテムであることは確かです。しかし、クーハンには使った人のみぞ知る、手放せない魅力がたっぷりと詰まっていて、コアなファンの多いアイテムなんです! ナイスベビーのお客さまからも「便利だった!」「あって助かったー!」とたくさんの声をいただき、ライフスタイルや使用する場所によってとても便利にお使いいただいています。 クーハンに興味を持ちこの記事を読んでいただいている方には、まず、クーハンがどんなシチュエーションで使えるのか、その魅力をしっかりと知っていただきたいと思います。商品の機能を知ればあらゆるシーンで活躍し、クーハンのある生活は育児をもっと便利にしてくれること間違いなしです。 こちらの記事を読んで、クーハンに魅力を感じた方は絶対に使うことをおすすめします。先輩ママのあってよかったと思ったシチュエーションも紹介していますので、是非参考にしてください。 1. クーハンとは、赤ちゃんを寝かせて持ち運べる簡易ベビーベッド クーハンとは、赤ちゃんを寝かせて持ち運びができる簡易ベビーベッドです。 今回、調査を進めて行く中で見たことはあるけど「クーハン」という言葉を知らない方が多いことが分かりました。呼び名も「赤ちゃん用のかご」や「ベビーバスケット」「ベビーキャリー」「クーファン」など人によって様々ということに驚きです。 クーハンは元々、フランスのかごやバスケットを意味する「couffin」が語源と言われています。中世フランスの農民らが農作業中に赤ちゃんを目の届く場所に寝かせておくために利用していたのが始まりです。 現在では、赤ちゃんの移動手段や簡易ベッドとして便利に使用できるだけではなく、かごの中に小さな赤ちゃんが寝ている姿はとても可愛いとSNSでも評判の高いアイテムです。赤ちゃんの移動を便利に、お洒落に、使用できるママのお助けベビーグッズこそが「クーハン」なのです。 1-1. 一度使ったら手放せないクーハンの魅力 クーハンは他のベビーグッズにはない、ならではの魅力があります。 実際に使ったことのあるママの中でも「クーハンがあって本当に助かった」「外出の時は必ず持ち歩く便利アイテム!」と絶賛する声がたくさん上がっています。ここでは、そんな一度使ったら手放せないクーハンの魅力を詳しく紹介します! 1-1-1. ママの居場所にいつでも赤ちゃんを楽に移動できる クーハンの最大の魅力は、なんと言ってもママの居場所にいつでも赤ちゃんを楽に移動できる点です。 日中は、赤ちゃんとママのふたりきりのご家庭も多く、育児の他に家事もこなすママは部屋間の移動が頻繁。その度に赤ちゃんを起こすことも出来ず、家事中は別室にいる赤ちゃんの様子が確認しにくいとお悩みのママは多いようです。 クーハンはベビーベッドと違い、コンパクトで持ち手が付いています。 持ち手を持って移動させれば、赤ちゃんの体勢を変える必要がないため、起してしまうといったリスクを軽減させることができます。 家事に合わせて赤ちゃんも移動できれば、いつでもママの側に居られて安心。そしてママも、家事をしながら赤ちゃんの様子を見ることができるので安心して家事に取り組めますね。 1-1-2. 外出先でも赤ちゃんの寝床、おむつ替えスペースを確保できる クーハンは自宅内の移動だけではなく、帰省先など外出先での寝床やおむつ替えスペースとしても活躍します。 赤ちゃんを連れてお出かけする場合はどこであっても赤ちゃんの寝床スペースが必要です。クーハンの重さは約2.5kg~3kg程ととても軽く、誰でも簡単に持ち運ぶことができるので外出先にサッと持っていき、サッと赤ちゃんの寝床が確保できます。 さらに外出先で困ることの一つと言えば、おむつ替えスペースの問題。例えば、知人宅にお邪魔した際、おむつ替えでカーペットなどを汚してしまえばトラブルの原因になることも考えられます。 もしクーハンがあれば、クーハンの中でおむつ替えができるので、汚してしまう心配はありません。「気にしなくて良いよ。」と言って頂けることも多いですが、親しい人であっても周囲への配慮は大切ですね。 簡単に持ち運べて、どこでも赤ちゃんの寝床やおむつ替えスペースを確保できるクーハンは、外出先でも大活躍です! 1-2. バッグ型orかご型、使用場所で決めるクーハンの選び方 クーハンには、バッグ型とかご型の2タイプがあります。それぞれ違った魅力があり、どちらにしようかお悩みのママパパは多いようです。 選ぶポイントはたくさんありますが、その中でも筆者がオススメする選び方は一番多く使用する場所を考えて決める、ということです。なぜなら、ライフスタイルによって必要な機能とそうではない機能があるからです。 事前に使用場所を考えることによって、最も必要とする機能を存分に発揮することができます。 それでは、それぞれの特徴を見ていきましょう!...
全貌を大公開!ナイスベビーで実際にベビーベッドをレンタルしてみた
ベビーベッドのレンタルと聞くと、まず心配になるのが衛生面のことですよね。基本的にレンタルは中古品なので「どんな状態のものが届くのか?」「赤ちゃんが使うものなのに中古で大丈夫?」といった心配があります。また、「借りたものを壊してしまったらどうしよう?」や「汚してしまうことが心配で躊躇してしまう」など様々な不安要素があると思います。 ナイスベビーなら心配ナシ! ナイスベビーでは1台1台徹底した丁寧なクリーニングと独自の大型洗浄機での滅菌処理など、品質には自信を持っています。直接赤ちゃんの肌に触れるものだからこそ、しっかりとしたケアを第一に心がけています。また、レンタルベビーベッドはナイスベビーの無料保証サービス「あんしんサポート」で、汚れ・キズ・破損しても弁償は一切ありませんので、自分の物のように心置きなく使って頂けます。 ベビーベッドのレンタルはまだまだ認知度も低く、WEB上にもあまり情報が出ていない為、他にも不透明な部分が多いことが実態です。 そこで、そんなベビーベッドのレンタルに対する不安を解消すべく、実際にレンタルをしてみた体験レポートをご紹介します!取材にご協力頂いたのは、今回はじめてベビー用品のレンタルを利用する育児ママ。 「ナイスベビー」のレンタルサービスで、注文から返却まで実際に体験してみたリアルな様子と絶対に知っておきたいポイントを合わせて詳しくご説明します。 全ての流れを細かく知ることで、ベビーベッドのレンタルに対する不安は解消されるはずです。その全貌をしっかりと理解して、安心してお得で便利なナイスベビーのベビーベッドレンタルを賢く利用しましょう! 1. ベビーベッドのレンタルを申し込む 今回はじめてベビーベッドのレンタルをするのは千葉県にお住まいのひかりさん。 かかりつけの病院で手にしたナイスベビーのカタログを見て、ベビーベッドがレンタルできることを初めて知りました。ベビーベッドは使う期間が限られているので、使い終わった後すぐに返却できるレンタルはとても魅力的に感じました。 ただ、やっぱりレンタルの最初の印象としては衛生面での不安。「生まれたばかりの赤ちゃんに中古のベビーベッドを使うのはどうなんだろう…?」という心配が真っ先に頭に浮かびました。 しかし、カタログを読み進めていくと、ナイスベビー独自の大型洗浄消毒機、高温スチーム、電解水生成装置での殺菌処理や、1台1台手作業による丁寧なメンテナンスによって安心安全な状態であることが分かり、「これなら大丈夫かもしれない!」とベビーベッドをレンタルすることに決めました。 ナイスベビーの無料カタログを請求しよう! ナイスベビーのカタログは東京、千葉、神奈川、埼玉の主な産婦人科に置いてあるので、ぜひチェックしてみてください。 もちろんWEBサイトから無料請求することもできます。 カタログの無料請求はこちら 1-1. はじめにレンタルの計画を立てよう 初めてベビーベッドのレンタルをするにあたって、どこでどのくらいの期間を借りるのかを申し込み前に計画しておきましょう。レンタル開始後に利用期間を短縮することは出来ないので、無駄な期間を契約してしまわないように事前に利用期間を考えておくことがポイントです。 ひかりさんは現在帰省中なので、帰省先の実家で1台、自宅へ戻ってきてからもう1台、合計2台のベビーベッドをレンタルしたいと考えています。 今回ひかりさんの計画はこちら。 時期 場所 レンタル内容 出産~1ヶ月 実家 帰省中の1ヶ月間だけベビーベッドを使いたい。1ヵ月間だから小さいベッドでいいかもしれない。その他にもすぐに揃えなければいけないレンタル商品を調査中。...
サークル兼用ベビーベッド厳選3選!購入前に知っておくべき3つのこと
赤ちゃんを迎える準備として、まず最初に思い浮かぶベビーベッドの準備。サイズ、機能、デザイン、それぞれ特徴があり、数あるベビーベッドの中から1つを選ぶのは一苦労ですね。 今回は、ベビーベッドの機能性に着目し、最も長い期間で使用することができる「サークル兼用ベビーベッド」を紹介していきます。ベビーベッドとしての機能はそのままに、床板・収納棚・キャスターを外せば、ベビーサークルにも変わる1台2役の多機能型ベビーベッドです。 ナイスベビーラボおすすめのサークル兼用ベビーベッドの紹介とともに、実際に使ったママたちのアンケート、そしてメリットデメリットも含め徹底的に解説していきます。ベビーベッド選びの参考に是非読んでください。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. サークル兼用ベビーベッドおすすめ3選 ここでは、ナイスベビーラボおすすめのサークル兼用のベビーベッドを紹介します。今回紹介するものは全てサークルにしたときにスペースの拡張が可能なものです。一般的にロータイプベッドはサークル兼用のものが多いですが、広さはベッドのサイズとあまり広くないため、ハイハイ時期を過ぎると狭く感じます。サークルとしても長く使う目的でサークル兼用のベッドを検討されている方は、今回紹介するお子様の成長と共にスペースを拡張することができるものがおすすめです。 1-1. ベビーサークルからキッズベンチになる3WAYベッド ファルスカ ミニジョイントベッド(グランドールインターナショナル) 対象月齢 新生児~24カ月(ベンチなら約6歳頃まで) 重さ 11.48kg サイズ [外寸]約W95×D65×H65㎝[内寸]約W90×D60×H65㎝※サークル時、連結可能なサイズは1辺240㎝ 安全規格 SG・PSG 「ベビーベッド」「ベビーサークル」「キッズベンチ」とお子様の成長に合わせて変形する多機能ベッドです。新生児~約6歳頃までと長く使用できるので、お値段以上の満足が得られるのではないでしょうか。別売りの「プレイペン/パネル」と連結させれば、さらにスペースを広くすることも可能です。さらにデザインや素材にもこだわっており、安全のため全ての角を丸く加工して、天然木・樹脂パーツ(PP)と上質な素材で作られています。赤ちゃんもママも安心・安全なベッドです。 ファルスカ つながる!ひろがる!木製ミニベッド ミニジョイントベッド ネオ 746051 ナチュラル 1個 (x 1) 22,000円(06/08 19:47時点) Amazon楽天市場Yahoo...
赤ちゃんの為に用意すべきベビーベッドに合う最適なベビー布団とは?
赤ちゃんとの新しい生活に期待をふくらませているママやパパ。いよいよ出産準備をしようと、赤ちゃんの睡眠環境を整える為にベビー布団は必要と考える方は多いと思います。では、赤ちゃんにとって、一体どんな布団がいいのでしょうか?ベッドで寝かせるのか、床に布団を敷いて寝かせるのか、悩んでいるご家庭が多いのは事実です。 ベビー布団にはサイズや素材、柄、洗える機能性があるかなど、購入の決め手は様々あります。ここでは、ベビー布団とベビーベッドのサイズの関係や購入時の注意点、おすすめの布団セットと一般的なお世話の方法についても紹介していきます。ご自身のライフスタイルに最適なお布団を選ぶためにも、ぜひ参考にしてください。 1. ベビー布団を購入する場合の3つの注意点 1日の大半を眠って過ごす赤ちゃんにとって、ベビー布団は最も重要なベビー用品。安全で安心できる睡眠環境を整えたいですよね。ここでは、ベビー布団を用意する際、事前に確認しておくべき3つの注意点について解説いたします。 1-1. ベビーベッドより先にベビー布団を購入してはダメ! 「ベビー布団は生後すぐから使うから、とりあえず購入しておこう!」と先だって考えているママやパパは多いと思います。まずは、お世話する場所のどこでどのようにベビー布団を使うか、シチュエーションをイメージすることが重要です。 例えば、居住スペースによっては、ママやパパがベッドで寝る場合、床にベビー布団を敷いて下に赤ちゃんを寝かせるというパターンは考えにくいでしょう。その場合、ベビーベッドを用意して夜中のおむつ替えや授乳をすることになります。布団を敷いて寝る場合も、寝室の大きさによっては、標準サイズ(内寸120×70㎝)のお布団を敷くスペースがなければ、ミニサイズ(内寸90×60㎝)のお布団を用意しなければならないパターンもあります。 また、いずれ大きくなっても使えるものをと大きいベビー布団を購入してしまっても、出番が先になってしまうと収納しておくスペースが必要になります。 ナイスベビーでは、お客様より『ベビーベッドよりも先にベビー布団を用意してしまい、ベッドのサイズに合わなかった』『設置したい場所が狭いので、小さいベッドが必要だけど、購入してしまったベビー布団は使えますか?』と、相談を受けることが多くあります。ベビーベッドとベビー布団のサイズは必ず合わせることが必須条件!ベビー布団を購入する前に、まず、ベビーベッドを使うかどうか、どのサイズのベビーベッドを使用するのか、を検討した上でお布団選びに入りましょう。 1-2. ベビー布団のサイズはしっかり確認! ベビー布団は主に2種類、標準サイズ(内寸120×70㎝)とミニサイズ(内寸90×60㎝)があり、それぞれベビーベッドのサイズと合うものになっています。ベビーベッドを使う予定の場合は、必ず布団(敷布団)とベッド(内寸)のサイズを確認してください。 メーカーによってはベビーベッドもベビー布団もサイズがさまざまあります。ベビーベッドをレンタルや購入することを考えているのであれば、先にベッドの選定からはじめましょう。ベビーベッドの内寸とベビー布団の敷きふとんのサイズが合わない場合、溝ができてしまったり、段差が出来てしまったり、窒息や転落などの危険が生じる可能性があります。赤ちゃんの安全を第一に考えて、ぴったりサイズのベビー布団を選んでください。 ★基本のサイズ(市販店で販売されているもの) 標準サイズ 120×70㎝ 標準サイズのベビー布団は、120×70cmが一般的。おおよそ2歳から2歳半頃まで使えます。 ミニサイズ 90×60㎝ ミニサイズのベビー布団は、90×60cmが一般的。1歳から1歳半頃まで使えます。 ★特殊サイズの例(メーカー独自のサイズ展開のあるもの) 小型サイズ 100×63㎝ 小型用のベビーベッド用のベビー布団は、メーカー独自で開発したサイズのベッドに合わせたお布団。標準型のベッドは思ったよりも大型のため、お客様のお声をもとに製作したもの。大き過ぎず小さすぎないので人気のサイズです。 特殊超小型サイズ 80×50㎝ 特殊サイズのベビー布団は、省スペースでお世話のできる特殊サイズのベビーベッド対応のベビー布団。このサイズのベビーベッドは生後8か月頃まで使えます。移動を簡単にできるサイズが魅力です。 タイニ―サイズ 70×60㎝ タイニ―サイズの新生児期から生後3か月ごろの赤ちゃん用のベビーベッドに合わせたベビー布団のサイズ。里帰り中の使用に最適です! ※特殊サイズのベビー布団は、一般店舗では市販されていません。また、海外ブランドのストッケやイケア等でもオリジナルサイズになっています。ベビーベッドを購入やレンタルされる店舗に確認が必要です。...
いつ折りたたむ?!折りたたみベビーベッドを選ぶ時に考えるべきこと
ベビーベッドを折りたたみたい!それにはいくつかの理由があると思います。第二子、第三子の出産までコンパクトにしまっておきたい、里帰り先と自宅で同じベッドを使いたい、部屋間を移動して使いたい、広げたり片付けたりの頻度が高い、など、その目的はいろいろですね。 まずは折りたたみベビーベッドにはどんな種類のベッドがあるのか、その特長をご紹介します。アイテムの紹介と合わせて、実際に折りたたんでみた検証の様子、その結果からみる折りたたみベビーベッドの利便性についてなど、徹底的に解説していきます。 ご家庭にぴったりの折りたたみベビーベッド選びの参考に、また、これを読んでいただければ、折りたたみにするか、通常のベッドにするかの悩みにもきっとお役立ていただけることと思います。是非参考にしてください。 本ページはアフィリエイトによる収益を得ています 1. 折りたたみベビーベッド タイプ別でみる2種のベッド 折りたたみベビーベッドのタイプは大きく分けて2タイプ。手軽でコンパクトな持ち運びもできる簡易タイプのベビーベッド。もう1つは本格的な木製タイプのベビーベッドでありながら、簡単に折りたためるタイプ。まずはこの2タイプの特長について解説していきます。 1-1. 手軽でコンパクト 簡易タイプのベビーベッド 簡易タイプのベビーベッドは、広げたり折りたたんだり、とにかくセッティングがラク!専用のバッグもついて持ち運びも簡単にできるのが特長です。これまではベビーベッドとしもプレイヤードとしても使えるものが主流でしたが、近年ではリビングや寝室を簡単に移動できる超小型の簡易ベビーベッドも多数ありとても人気です。添い寝ベッドとして、ゆりかごとしても使えるなど、多機能で個性的なアイテムが揃っています。 ◎こんな方にオススメ!◎ 自宅と実家、両方で使いたい! 寝室が狭くて大きなベッドは置けない リビングと寝室を移動させたい リビングでのお昼寝用で使いたい 短期間だけどベビーベッドを使いたい 1-2. 設置も収納も簡単 本格的木製タイプのベビーベッド 折りたたみベビーベッドのイメージは、どちらかというと簡易式ベッドで考える方が多いかもしれません。木製のベビーベッドでも簡単に折りたためるタイプがあり、且つ、かなりのハイスペック。本格的木製ベビーベッドと変わるところなく、高さ調整ができ、収納棚もキャスターもついてる優れものなのです。赤ちゃんに安心な睡眠環境もしっかり確保しながら、いざという時はさっさと簡単に収納。簡易式ベッドと比べるとコンパクト感には欠けますが、ベッドとしての機能や安心感はを重視する方にはおすすめします。 ◎こんな方にオススメ!◎ 第二子、第三子を予定していて、利用頻度も高くなりそう ベビーベッドはしっかりしたものを使いたいけど、設置や片付けがラクにできるベッドがほしい ママ一人でも扱える木製ベビーベッドがほしい 2. タイプ別折りたたみベビーベッド おすすめ5選 デザインも機能もそれぞれ異なる個性的なベッドから、スタンダードな木製折りたたみベッドまで、ナイスベビーラボがおすすめする折りたたみベビーベッド厳選5選を紹介します。販売は終了してしまっているけど、レンタルなら利用できるアイテムをあるので、一時的な利用であれば選択肢に入れてみてもいいですね。 2-1. 簡易式折りたたみベビーベッド おすすめ3選 ▶ ベッドサイドベッド Soine(ソイネ) 多機能な万能ベッド ソイネは、リビングに置いても場所をとらないコンパクトさが魅力。キャスターも付いているので、室内の移動もカンタン。ドーム型のかやを閉じれば、蚊やほこり、エアコンの風などから赤ちゃんをしっかり守ります。6段階で高さ調整が可能、ママのベッドの高さに合わせて夜は添い寝ベッドに。付属のセーフティベルトで大人用ベッドにしっかり固定できるので安心ですね。マットとドームを外し、足をたためば女性1人でも簡単に折りたたむことができます。専用の収納バッグに入れれば持ち運びも簡単です。...
ベビー業界歴30年の私がオススメする絶対に失敗しないベビーベッドの選び方
これから初めて赤ちゃんを迎えるにあたって、ベビーベッドの準備を考えている方は多いかと思います。 しかしベビーベッドにはサイズや高さ、機能面など驚くほど多くの種類があり、初めての方にとってはどうやって自分にぴったりなベッドを選べばいいのか判断がとても難しいですよね。 そこで、ベビー業界歴30年の筆者が自信を持っておすすめする「絶対に失敗しないベビーベッドの選び方」をご紹介します! 2章では、長年に渡ってベビー業界に携わってきた私の経験をもとにまとめたシュチュエーション別チャート表【決定版】を掲載していますので、誰でも簡単に自分にぴったりなベビーベッドを選ぶことができます。 ベビーベッドは赤ちゃんが一番長く過ごす場所ですから、全てのママ、パパに失敗のないベビーベッドの選び方を知ってほしいと強く願っています。ぜひベッド選びの参考にしてください! 1. ベビーベッド選びのステップ ベビーベッドには様々な種類がありますが、ご自身にぴったり合うものを選ぶことがとても重要です。ベビーベッドを使う状況や設置スペース、ライフスタイルによっても使い勝手も大きく異なってきます。 この章ではベビーベッド選びに必要なステップを順を追って説明していきます。 1-1. 設置場所を決めましょう 1-1-1. 寝室で使うなら添い寝タイプがおすすめ ママとパパがベッドで就寝している場合は、添い寝タイプがおすすめです。 添い寝専用のベビーベッドもありますが、ロータイプのベビーベッドであれば大人用ベッドに並べて添い寝することができます。 添い寝タイプのメリットは何と言っても夜中の赤ちゃんのお世話が楽なことです。新生児の赤ちゃんは一度眠りについてもすぐに起きてしまったり不規則なことが多いので、隣から赤ちゃんのお世話がすぐにできる添い寝タイプはとても助かります。 また、赤ちゃんに異変があってもすぐに気付くことができますし、ママが近くにいることで安心して眠りについてくれるというメリットもあります。 ただし、片側の扉が開いた状態になっているので、寝返りをはじめたら赤ちゃんが落下しないように十分注意が必要です。 1-1-2. リビングで使うならハイタイプがおすすめ ご自宅でベビーベッドをご利用の場合、リビングに設置するケースも多いかと思います。特に授乳やオムツ替えを頻繁におこなう新生児時期は、寝室よりもリビングにベビーベッドがあったほうが何かと便利な場合もあります。 また、ママが着替えやオムツ替えをする時に、上体をかがめてお世話をすると腰に負担がかかります。産後腰痛にお悩みのママには、少しでも緩和するためには立ったままお世話ができるハイタイプがおすすめです。 更に兄弟やペットが居る場合もハイタイプがおすすめです。手が届きにくいのでいたずら防止になります。 サイズは標準サイズがおすすめですが、場所が限られている場合は、ミニサイズでもOKです。 ハイタイプのデメリットもお伝えしておきます。 新生児期は赤ちゃんが殆ど動きませんが、寝返りをうつようになると動きも活発になってきます。成長に応じて床板(赤ちゃんが寝る板)の高さを下げて頂く必要があります。床板を下げることでハイタイプのメリットである立ったままの世話ができなくなってしまいます。ハイタイプとして使用できるのは、つかまり立ちの頃までとお考えください。 また、赤ちゃんが寝ている高さが高いので、パパやママがソファーなどに座っている時に様子が確認しづらいこともあります。リビングでも床に座るロースタイルのご家庭においては、リビングでもロータイプのベビーベッドの方が使いやすいと思います。 1-1-3. 里帰り時の短期利用であればハーフサイズがおすすめ 里帰り出産を予定している方や、出産後に里帰りを予定している場合は、使用期間が限られる事が多いと思います。一般的には一ヶ月検診が終了した頃にご自宅へ戻られるケースが多いと思いますが、ママの体調やお子様の状況などで3ヶ月ぐらいまでご実家で過ごされるケースもあります。長くても3ヶ月でご自宅へ戻られる場合が多いと思いますので、里帰りにはミニサイズのベッドがおすすめです。 また、1~2ヶ月程度であればハーフサイズのベッドがおすすめです。標準サイズの半分の広さのベッドで、1~2ヶ月程度の使用でしたら十分な大きさです。スペースも取りませんので、リビングでも寝室でも置く場所を問いません。当社のお客様も里帰りの利用でしたら圧倒的にハーフサイズのベッドが人気です。 1-2. 設置場所の広さに合わせてサイズを選びましょう 設置場所が決まったら、スペースに合わせてベビーベッド選びのサイズを決めます。ベビーベッドには大きく分けて3種類のサイズが存在します。それぞれの特徴とその選び方をご説明します。 内寸 外寸...
ベビーベッドレンタル最安値ランキング&お得にレンタルする3つのコツ
これから始まる赤ちゃんとの新しい生活。想像しただけで楽しみで胸が踊りますね!ベビー用品はどれも小さくて可愛くて、ついつい沢山揃えたくなり出費がかさみがち。でも、赤ちゃんが成長して、大人になり自立するまでの間には沢山のお金がかかります。これから長期的にお金がかかるからこそ、短い期間しか使わないベビー用品の費用は抑えたいと考えるママも多いかと思います。 そんな時に便利に利用したいのがレンタルサービス。特に「ベビーベッド」は購入よりレンタルを選ぶ方が多いベビー用品レンタルの代表アイテムです。 「安全・健康・お世話のしやすさ」からもぜひ利用したいベビーベッドですが、ベビー用品の中でも大きなもののひとつですので、ベビーベッドの置き場所や使用後の保管場所が心配と悩まれレンタルを選ばれるママが近年増えています。 今回はベビーベッドをレンタルしている主な15社を、様々な角度から徹底的に調査し、本当に安い1台を紹介させて頂きます。 ご自身にあったぴったりなベビーベッドを選ぶことでトータルで安くなること、さらになるべく安い価格でベビーベッドのレンタルが実現できる裏技もご一緒に紹介させて頂きます。レンタルを検討されているママ必見!是非、レンタルベビーベッド選びの参考にしてください! 1. ベビーベッドレンタルの最安値を徹底調査 ベビーベッドのレンタル価格、どれくらいのイメージをお持ちですか? 実は私も今回調査するまでは正確にはわかりませんでした。それはベビーベッドのサイズや機能、レンタル期間によってレンタル価格が全く変わってくるからです。 ベビーベッドはそれぞれのライフスタイルによって置き場所や使用期間が変わってきます。それにより大きさや機能に違いがあることでレンタル価格が変わってきます。 まずは、ベビーベッドのレンタル価格を、1日あたりのレンタル最安値と、サイズ別のレンタル最安値を紹介します。 ベビーベッドレンタルの全国配送を行っているレンタルショップ15社を徹底比較! DMMcom / 愛育社 / 愛育ベビー / ダーリング / ダスキンレントオール / ナイスベビー / ベビーアイランド / ベビーツーワン / ベビーファン / ベビーベッドレンタル専門店...
赤ちゃんの安全を守るためのおすすめベビーベッドガードと正しい使用方法
赤ちゃんを迎えるにあたって、ベビーベッドを用意する方は多いかと思います。 そのベビーベッドを使用するにあたり、布団・マットレス・ベッドメリーなど、実はベッドの他に必要なアイテムは数多くあります。すべてを用意すれば、より赤ちゃんも快適でママも安心して使用することができることでしょう。しかし、そうは言っても現実的にはアイテムが増えるほど費用がかかりますし、赤ちゃんによってはあまり使用しなかったアイテムもあったという声もあり、必要なものを無駄なく選んでいきたいですよね。 ベビーベッドと一緒に用意したいアイテムの1つ「ベビーベッドガード」。一般的にベビーベッドガードと呼ばれるものには2種類のアイテムがあります。1つ目が、ベビーベッドの内側に取り付ける「ベビーベッドガード」、そして2つ目が、大人用ベッドの側面に取り付けるフェンス「赤ちゃん用ベッドガード」です。 そこで今回は、1つ目の「ベビーベッドガード」について詳しくご紹介します。ベビーベッドガードを用意した方がよい理由や、使用する際に注意すべきポイントを知ることによって、本当に必要なアイテムを用意することができます。 1. ベビーベッドガードを用意すべき4つの理由 ベビーベッドで赤ちゃんを寝かせる場合、ベッドと布団と一緒に用意する事が多いのが「ベビーベッドガード」です。ベビーベッドガードとは、ベッドの柵の内側に取り付けるクッションです。このクッションがあることで、赤ちゃんの手足が柵に挟まってしまったり、硬い柵に頭を直接ぶつけないように保護することができます。その他にも、ガードを使用するメリットはたくさんあります。こちらでは、ベビーベッドガードを用意すべき4つの理由を詳しくご紹介します。 1-1. ベッドの柵に頭や手足をぶつけないように保護できる 動くことが少ない新生児の頃はあまり気にならないかもしれませんが、寝返りをはじめる頃には活発に動くようになり、赤ちゃんの頭や手足が柵にぶつかってしまうことは多いようです。 そこで、厚みがありクッション性が高いベビーベッドガードを設置することで、赤ちゃんを危険から守ってあげることができます。 1-2. 柵の隙間を埋めて、手足を挟まないようにできる 一般的にベビーベッドの柵の隙間は8㎝程度あり、想像以上に広いものです。赤ちゃんの小さな手足が隙間に入ってしまい、身動きが取れなくなってしまったり、ママやパパが気がつかずにそのまま抱きかかえてしまう危険性もあります。ベビーベッドガードがあれば隙間を埋めることができるので、赤ちゃんもママも安心です。 1-3. エアコンの風が直接当たらないように防ぐことができる 赤ちゃんは体温調節機能が未熟です。夏場の熱中症や冬場の低体温を防ぐためにエアコンを使用して温度や湿度調節をすることも多いかと思います。エアコンの風が体に直接当たっている時間が長いと、過剰に体温が奪われたり、肌や粘膜が乾燥し体調を崩してしまう原因となることがあります。 そこで、ベビーベッドガードを取り付けることにより、赤ちゃんにエアコンの風が直接あたることを防ぐことができます。ただし、ガードは保温性にも優れているアイテムです。ベッド内も暖かくなりやすいため、温度や湿度をこまめにチェックしましょう。夏場など気温が高い時期は特に注意が必要です。 赤ちゃんにとって快適な室温は(夏)26~28度、(冬)20~23度です。外気温との差が5度以内くらいが適切だとされています。湿度は40%~60%の間に設定するようにしましょう。 1-4. 上の子やペットのイタズラから守ることができる 小さなお兄ちゃんやお姉ちゃんは、赤ちゃんが新しい家族になったことが嬉しくて仕方ないですよね。柵の中に手を入れて、赤ちゃんをなでなでしてあげたり、自分のお菓子やおもちゃを赤ちゃんに分けてあげようとしていたという話もよく耳にします。ママのお手伝いをしようと真似をしているのでしょうか。子どもの優しさにほっこりしますね。しかし、力加減がまだ分からなかったり、間違えて目をつっついてしまう、赤ちゃんがお菓子を口にしてしまうなど、事故につながってしまう可能性もあります。 また、家族の一員のペットも同じく赤ちゃんの存在に興味津々です。他の家族同様に遊んでもらいたくて、柵から手を入れたり、顔を舐めてしまったり、ということもあり、まだ抵抗力の弱い赤ちゃんにはリスキーなことも多く起こります。そこで赤ちゃんを囲って守るベビーベッドガードがあれば、そういったリスクを減らすことができます。 2. タイプ別ベビーベッドガードおすすめ4選 ベビーベッドガードは、主にベビーベッドを柵を全て囲む「全周タイプ」と半分のみを囲む「半周タイプ」の2種類があります。それぞれのおすすめベビーベッドガードをご紹介します。ガードを選ぶときにぜひ参考にしてみてください。 2-1. 全周タイプ 全周タイプのものは、赤ちゃんの周りをすべて囲むことができるため既に寝返りをしている子や寝相が悪く活発に動く子におすすめです。全周を囲むので保温性に優れていますが、どうしても風通しは悪くなってしまい、夏場などは熱や湿気がこもりやすいためクッション性と通気性を両方兼ね備えているものがおすすめです。 【通気性抜群】Weegoamigo(ウィーゴアミーゴ)エアーラップ ベッドの四隅を開けて取り付けできるので、空気を循環させ熱や湿気をためない工夫がされています。また、隙間からは赤ちゃんの様子を伺うこともできるので安心です。冬の寒い時期は、四隅を閉じれば保温することもできます。さらに「マジックテープ」を使用しているため、様々なベッドの形に対応しており、紐がないため赤ちゃんに絡まったり、口に入れる心配はありません。 出典:Amazon 【お肌に優しい綿100%】PUPPAPUPOベビーベッドガード (トゥインクルスター)120サイズ お肌に優しい綿100%を使用しており、赤ちゃんをやさしくガードします。中綿は通気性のあるポリエステル綿を使用しておりムレにくいという特徴も。 上部に付いている紐でベッドに括りつけ、四隅がマジックテープですべて取り外せる設計になっています。お世話をする際に扉側のマジックテープを外して手前にくるんと回せば、ガードを外すことなく開閉することができ手間がかかりません。紐とマジックテープの2重構造になっているため、外れにくくより安全で安心です。 出典:Amazon 2-2. 半周タイプ...
ベビー用品のプロが本気でおすすめする究極のベビーベッドはこれだ!
この記事を読んで頂いている方は既にお気付きかと思いますが、ベビーベッドには様々なタイプがあり、GoogleやYahoo!などで検索すると非常に多くの種類がヒットします。初めてベビーベッドを購入するにあたって、何を基準に選べばいいのか、どれが自分にとって最適な機能を持ったベッドなのか、数ある中から見つけ出すことはとても困難かと思います。 ナイスベビーではベビーベッドを年間2万台以上出荷している実績があり、その中でも本当におすすめできる究極のベビーベッドをプロ目線で特徴と併せてご紹介します! もちろん、ライフスタイルやお部屋のスペースなどによってご家庭にぴったりなベビーベッドは異なりますが、これだけは外したくないという機能を持ったベッドを知っていればきっと後悔のない選択ができるようになります。 1. プロが本気でおすすめするベビーベッドの5条件! 年間2万台以上出荷しているナイスベビーだからこそ自信を持っておすすめするベビーベッドのタイプをご紹介します。数あるベビーベッドの中でプロが本気でおすすめする「これだけは外したくない5つのポイント」をまとめました! 1-1. 腰に優しいハイタイプがおすすめ 子育てママに聞いた産後の気になる体の不調として最も多い回答が慢性的な「腰痛」です。今まで腰痛に悩まされた経験が無い方でも産後急に痛みを感じるようになってしまうことがあるので注意が必要です。 妊娠と出産により腰に負担がかかってしまうことも要因のひとつですが、一番の原因は赤ちゃんを低い位置から抱っこする動作や逆に低い位置に寝かせる動作、また腰をかがめてお世話をすることにあると考えられます。 ベビーベッドには赤ちゃんを寝かせる役割の他にオムツ替えやお風呂上がりのお着替えなど、ベビーベッドでお世話をする機会が多くあります。 ハイタイプのベビーベッドは床板の高さが最大70cmほどあるので、腰を大きくかがめない姿勢でお世話をすることができますし、赤ちゃんを抱き上げる時や寝かせるときも楽な姿勢を保てます。毎日の積み重ねが腰への大きな負担になってしまうので、ベビーベッドを選ぶ上で最も重要なポイントであると考えます。 中でもとくに腰へ大きな負担をかけてしまう動作は抱っこしている赤ちゃんを低い位置に下ろすときです。 腰が曲がっている状態で、自分自身の上半身の重さに赤ちゃんの体重が加わるため腰の筋肉に負荷がかかります。また、赤ちゃんを起こさないようにそーっと下ろさないといけないので余計に負担がかかってしまいます。赤ちゃんが生まれてから毎日何回も何回もこの動作を繰り返していたら腰痛が悪化したり、ぎっくり腰になってしまうことも考えられます。 ハイタイプのベビーベッドであれば腰を大きく曲げる必要がないので負担は小さくて済みます。写真のように腰を曲げず腕の力で下ろすことができるので、ロータイプと比べて腰がとても楽です。腰痛が悪化してしまうと赤ちゃんのお世話が苦痛になってしまい、せっかくの赤ちゃんとの幸せな時間も半減してしまいます。 また、赤ちゃんにとって害のある、ダニ、カビ、様々な菌やウイルスは床から30cmくらいまでの高さに多く存在することが分かっています。 ハイタイプベッドであれば害のある「ホコリゾーン」から赤ちゃんをより遠ざけて寝かせることができます。赤ちゃんは抵抗力がまだ未発達なのでダニや花粉などのアレルギー物質の影響を大きく受けてしまうので、ハイタイプによってそれらのリスクから遠ざけることは赤ちゃんの健康面にとって大切です。 これらの理由によりプロ目線としてベビーベッドはハイタイプを強くおすすめします。 1-2. お世話スペースが広い標準サイズがおすすめ ベビーベッドは一般的に標準サイズ(内径120×70cm)とミニサイズ(内径90×60cm)があります。 市販のベビー布団がぴったり収まるのが標準サイズです。対してミニサイズはお部屋のスペースが限られている場合などに省スペースで設置できるコンパクトなベビーベッドです。 標準サイズ(左) ミニサイズ(右) 毎日のオムツ替えやお風呂上がりのお着替えなどベビーベッドには赤ちゃんをお世話する場所という役割もあるので、できるだけ広いスペースの方がスムーズにお世話をすることができます。 例えばオムツ替えをする時を想像してみてください。用意するものは新しいオムツにおしりふき、使い終わったオムツを入れるビニール袋、場合によってはベビーオイルなども使います。 ベビーベッドでオムツ替えをするときはこれらをベッドの上に置く必要がありますし、また、お布団も端に寄せることになるので、できるだけ余裕のあるスペースの方が便利ですよね。 こちらの写真は標準サイズでおむつ替えをシュミレーションしてみた様子ですが、お布団を端に寄せると結構なスペースを取られてしまい、実際に使えるスペースは狭くなってしまいます。さらにおしりふきなどを置くとお世話するスペースはかなり限られてしまうことが分かります。 標準サイズ(内径120×70cm)に対してミニサイズ(内径90×60cm)になると、さらにこんなに狭いスペースになってしまうので、やはりおむつ替えやお着替えなどお世話のしやすさを考えると標準サイズが良いでしょう。 設置スペースに問題がなければ、標準サイズを選択することをおすすめします。 1-3. お世話をしやすいツーオープンがおすすめ...